|
我孫子の塗装店 千葉県我孫子市我孫子1856-18 |
|
 |
 |
|
我孫子の塗装店 千葉県我孫子市我孫子1856-18 |
|
 |
 |
| 私(若月塗装:責任者)の職歴と一言 東京/京橋/ 中谷塗装工業所kkにて修行 ☆ 先々代社長が塗材で塗り面に凹凸模様をつける塗装工法を発案~ 今から数十年前になりますが【ラフォール(ラフコート)工法】で特許も取った程の会社で、 現在の外壁スタッコ模様・タイル吹き付け模様・ほか、ビニールクロス(壁紙)凹凸模様など、 壁面等に塗材で色々な凹凸柄を作り、その上に色付けをし拭き取り(2色ぼかし工法等も含む) 塗装工法を考案した原型・発祥元祖の塗装会社。 *当時、室内の壁に張る素材は本物の壁用クロスで、(ドンゴロス=麻袋のような生地)等を使用し、 下地に袋張りを施しその上に本物のクロスを貼っていました。 現在のビニールクロス張りには袋貼りはしません。 本物の壁用クロス=(ドンゴロス)等を張った後にクロス表面の毛羽を 焼き=(炙り)その上に塗装する工法も有りましたが、 今ではビニールクロスが主流となっており 1回貼れば終わりと完成も速い。 その他、木目塗装工法・変わり塗り塗装工法など、 素晴らしい腕(技術)を持った職人さん達が、常時30人程いた会社です。 ☆会社の専務+職人として戦前、皇居内の仕事も手掛けた事のある私の父もいて 東京に住んでいても皇居内の仕事をするには、田舎の役場にも通達が行き戸籍も全て調べられ 村役場でも我が村から、実家でも身内が皇居内に入るとの事で大騒ぎされたとも聞いています。 大工職人から塗装職人まで各会社から選抜され、 それぞれの技能を持った素晴らしい職人さん達が集まり工事したとの事です。 戦前は台湾出張でラフォール=ラフコートの仕事受注も数ありその中で仕事振りを認められ 台湾在中時は一時、塗装職を休止して浅野物産(現在の浅野セメントkk)で 終戦帰還まではかなり大きな工事現場の現場監督として勤めていたり、 また、2代目社長は東京都塗装高等技術専門学校の 5代目学校長(昭和59年5月~平成4年5月)を務めており 私の父は東京都塗装高等技術専門学校の特殊塗装の講師を務めた事もあり、 塗装材メーカー主催の盛大なレセプションにも招待されたり、 歌舞伎座/松竹関係の塗装工事も数多く手掛けていた関係もあり、 人間国宝さんや一流企業の社長さん会長さん方達から直接仕事の依頼電話が有ったりと、 素晴らしい職人さん達に囲まれている中で修業出来た事は、もの凄く自分にとり宝となっています。 *私が塗装業をおぼえ修行した会社は現在、跡継ぎが無く、2代目で終わり会社は存在していません.。 東京で昭和34年~63年頃まで町場 (住宅等)や 、野丁場 (大手ビル等)の仕事をしていました。 電通/大東京火災海上保険kk(あいおい損保となり現在は、合併し会社名は変わっている)/市政会館/時事通信社/ 都市センター/町村会館/参議院議員会館/三菱重工(丸の内ビル)/歌舞伎座(旧)/文学座/etc などの室内外塗装を経験し、ある方に見込まれ昭和52年に若月塗装店を開業、 大東京火災海上保険kk~「あいおい損保」~(現在は、合併し社名は変わっています。)関東地区(各)事業所室内の 塗装工事が主な作業現場でした。 *野丁場で大きな作業現場だと半年以上も仕事に通う事も有ります。 平成に入った頃より我孫子、湖北台、新木(新木野団地;長太郎団地)、つくし野、他、東葛地域の お客様よりのご紹介が除々に増え、住宅塗装専門で、こちらの仕事に切り替え現在に至ります。 「町場」=一般住宅塗装歴 33年 & 「野丁場」=大手ビル、塗装歴 20年 (2010年現在) |
||
  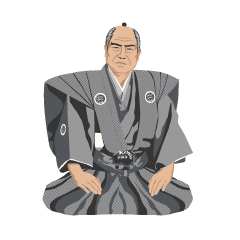 |
技術(腕)の良い職人さん達の事を 同業職人仲間達は、お侍さんと云っていました。 お侍さん=並の職人さんより技術(腕)が より優れて仕事を何でもよく知っている職人さんには 一目置いていた時代(昭和30年~40年代)もありました。 ただし、どんなに仕事が出来ても仕事を何でも知っていても 口の軽い職人さんの事を、お侍さんとは言いませんでした。 注・口の軽い=べしゃり(符丁)=つまらない事を何でもしゃべる事が多いい人の事、 互いに腕を競い合い自分を磨く お侍さん と云われたような塗装職人さんに 近年、お目に掛かる事が無いのは同業者として少し寂しい気もします。 *日本でも最大手、塗装店の仕事を経験して来た中で当時、通じた言葉(符丁等)であり 塗装業界の符丁や呼称名は地域/職場/渡り職人/その時代等により多少変わります。 |
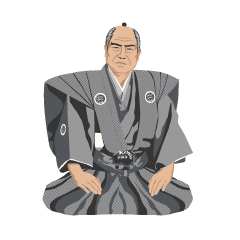 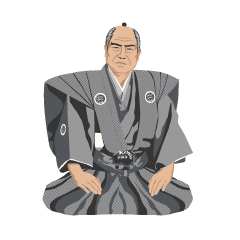  |
私の一寸、懐かしい思い出話 *私の小僧時代(昭和34年頃)先輩諸士から物を盗むとドロボーになるけど 仕事(腕=技術)はいくら盗んでもいいんだよと言われた事を思い出します。 ☆最近では、油性用の寸胴(熊毛刷毛) 水性用の大平刷毛などは使用しなくなり大面積は殆んどローラー使用で、 一般の方でも簡単に塗装できるようになり、刷毛で塗っていた昔ほどの塗装技術も心要が無くなって来ていますので 今は塗装会社に入ると直ぐローラーで塗らしてもらえますが、昔の小僧時代で最初の1~2年は掃除やペーパ当てや手元作業ばかりで 手の空いた時には先輩たちの仕事振りを目で見て覚えるのも仕事の内で刷毛をなかなか持たせてもらえませんでしたが 仕事を覚え一人前になって来ると最初の基礎を覚える事が如何に大事かがわかって来ます。 ↑ 現代このような事を言って若い人を育ててくれる腕の良い塗装職人さんは果たしてどの位いるだろうか? |
||
| また上記、電通・銀座本社(現在は港区に本社があり、日本最大の広告会社)を 塗装工事していた昭和34年頃、 屋上には優秀な伝書鳩が数百羽もいる大きな鳩小屋があり鳩を調教する専属社員もいて 日本中の事件・事故ニュース等の記事配信に伝書鳩が通信の手段として一役かっていました。 又、西別館(現在の首都高速道路下、銀座ショッピィングセンター街)には コマーシャル撮影の写真スタジオもあり芸能人たちとも遭遇しました。 ビル室内天井や壁に使用する水性塗料は現在のように溶解され石油缶に入っているような品では無く、 厚紙袋入り専用粉末(本代=胡粉に似た粉末)に 棒状ニカワ(煮詰めて溶くと糊状になり、木工品などの接着の役目をする物)や 板フノリ(やはり糊の代物)を入れて作った塗料を塗る為、2~3年すると塗料を固める役目の糊状が効かなくなり 壁面に洋服など擦ると白く付いてしまうような塗料しか当時はありませんでした。 又、数年で粉末状の塗膜となり2~3回塗り替えする度、 全てその古い塗膜に水を含ませ専用工具を使い剥がさないとナコ剥き=(粉状になった塗膜を剥がす事)を しないとすぐに剥れてしまい、次の塗り替え塗装が出来ないような時代でした。 私の小僧時代、トタン屋根の塗装にはコールタール塗りや、木の塀等には防腐剤(クレオソート)塗りがまだありました。 屋根や外壁に使用トタン板も亜鉛引きトタンで、まだ現在の様なカラートタンは見掛けませんでした。 油性塗料でもジンクロメート(ペースト状の顔料をボイル油で溶解して使用する)ような 塗料もあり乾燥時間も丸一日しないと触れなく、 又、耐水ペーパーも鮫の皮を乾燥させた物を使用したり今では考えられない時代が懐かしくも思います。 私が塗装業に入った昭和34年頃の足場は、丸太足場・荒縄での結束も一般的、 荒縄での結束は3ヶ月位で腐食してしまうので住宅新築工事などでは、 塗装工事に入る頃には部分的に荒縄を取替え締めなおさなければならなかった。 昭和30年後半~40年代になると丸太足場の結束にはカットしてない生(なま)番線を使用する様になって来た。 今では、結束と言う 使いやすくカットし加工した結束番線もあり、 又、ビケ足場やブラケット足場などと多種多様で、 昭和30年代の足場・塗料・塗装機器や工具・作業安全具など、 今では比べ物にならない程進歩している。 ↓下記、表 参照 |
||
| 塗料と塗装 一例 |
■水性塗料は専用の粉末(本代=胡粉に似た品)に、ニカワやフノリを煮詰めノリ状にし それを混ぜて固める役目をさせ使用。(今のように石油缶で溶解された塗料ではなく厚手の紙袋入りの粉末に水や糊を混ぜ使用) ☆数回目の塗り替え時には、必ず厚く粉化した旧塗膜の注-1、ナコ剥きが心要でした。 粉末水性塗料~水性エマルジョン~水性アクリル~水性ウレタン~水性シリコンと塗料も進歩している。 ■油性塗料はペースト状の塗料(ジンク)にボイル油で溶解して使用する塗料や油性調合ペイント等は非常に乾燥が遅かったが、 合成樹脂~溶剤系アクリル~溶剤系ウレタン~溶剤系シリコン~溶剤系フッソ、 二液塗料などと進歩し光沢や乾燥も物凄く良く成り作業効率も格段に上がっている。 注-1、 ナコ剥き =厚く粉化した旧塗膜を水で湿らせてから専用工具にて剥がし落とす作業。 *現代では「ナコ剥き」と云う言葉すら知らない職人も時代の流れで数多く成って来ています。 |
| 足場の一例 | ■荒縄結束での丸太足場~番線結束での丸太足場~クランプやブラケットを使用した単管足場~ビケ足場などに移行。 歩み板(足場板)も木板/合板~スチール板~アルミ板に移行。 以前は足場の掛け払い工事は鳶職人さんしかしなかったが、次第に塗装店でも自前の 丸太・単管・ブラケット足場等を持つようになり足場の掛け払い工事も塗装店独自で行う会社も増えましたが、 今は、安全な足場を組み立てる足場専門会社も数多くあります。 ■ピン無し単管やボンジョイント使用で人が乗る単管足場は 作業中の死亡事故等が発生し、法律で禁止されています。 (ホームセンター等で販売のピン無し単管やボンジョイント使用で人が乗る足場としての使用は「労働安全衛生法違反」となります) *万が一にも上記、単管足場作業中に事故の有った場合、 お客様に御迷惑も掛かりますので 当店は法律で禁止(昭和62年9月18日付け基発第549号の2及び第549号の3)を知った時点より、 ビケ足場を使用し、安全な作業を心がけています。 |
塗装機 私が 初めて使用した エアレス塗装機 と 作業現場 |
■私が最初に使用したのは昭和40年代、当時はエアレス圧送圧力釜(ドラム缶を小さくしたような形状)に 18ℓ缶塗料の天を切り缶ごと入れ密閉、コンプレッサーに繋ぎ、エアレス圧力釜に空気圧をかけ 18ℓ塗料缶の塗料を吸い上げエアレス塗装となり使用。 コンプレッサーでペイントガン塗料カップから塗料を吐出するエアースプレーとは違い、 18ℓ塗料缶から直接塗料ホースを経てエアレスガンから塗料を吐出させ大面積への塗装が出来、 ものすごい機械が出来たと思いました。 私が最初に使用した現場=日比谷:市政会館、内部の大改修工事で吹付時の養生が殆ど無く、 全階、天井や壁の吹付で、手元職人は付きますが一人で1日に10缶単位の塗料を使用でき、 全館塗装には塗料も数百缶に上りました。 同じ建物内には日比谷公会堂や時事通信社があり使用している時事通信社や 他の事務室やトイレ/給湯室等の小部屋もありそのような部屋は現代の様なローラーはまだ未熟品で 使用できず刷毛塗り作業。全館のトイレや給湯室内だけでもかなりの数量がありました。 *現代のエアレス塗装機は多機種販売され、性能や移動も楽でとても使い易くなってきています。 *当時、一般住宅では殆ど、(木)板張り外壁かトタン張り外壁かモルタル外壁で塗装も現代とは違い、 高圧洗浄機はありませんでした。 |
| 塗装具の一例 | ■パテに使用するヘラは(25cm横巾x30cm縦巾x5mm板厚)位で板状の専用檜材などが販売されており、 それを数日間~トロ(油)付けし、しなり(腰)を良くして、丹刃=タンバ(刃先に角のある匕首のような刃物)を 職人さん達はいつも腰袋に入れ持ち歩いて作った木ベラの先にキズが付いた分をカットしたり 削ったりして使用していました。 ☆もちろん丹刃(20cm~30cm位の長さのある刃物であり、所轄警察署の所持鑑札登録をし皆さん所持していました。 ☆今は、木ベラ、金ベラ、プラスチックヘラ、ゴムベラ等と多様。 ☆下地付け様にはオイルパテ,、塩ビパテ、ラッカーパテ等ありましたが、一般的な穴埋めにはガラスパテの使用が殆んどでした。 現代は硬化剤使用で乾燥も早いポリパテやシーリングボンド等多種多様にあります。 ■塗装ローラーは、ピンで留めるタイプで塗料にローラーの全体をつけてしまうと塗料が筒の中に入り込んでしまい 塗料が零れ落ちるような物でローラーが沈まない程度の塗料を入れる船を作り使用し、 まだまだ刷毛が全盛期の時代でした。 ☆今では柄にキャップが付いていたり、またスモールローラーのように塗料が ローラーの芯に入り塗料が零れ落ちるような事はありません。 |
| 安全具の一例 | ■作業履物~表が畳状・裏が自転車のタイヤを利用した草履と足袋で作業か、地下足袋使用。 野丁場(ビル等)や町場(住宅等)作業では一般的でした。 今、作業はズックに変化 ■ヘルメットや安全ベルトは無く、ビル建物(当時のビルは銀座で高くても8階位までしか無かった)外部塗装でも 運動会で使用するような太いロープに手製の座席を付け(ブランコと云う)屋上から補助ロープも無く、ロープ一本で降り、 命掛けで外壁やスチール(鉄)サッシ等を塗装するような状態でした。 ☆ビルの窓は鉄のサッシで今のようなアルミサッシはありませんでした。(住宅の窓は殆んど木製) ☆日本で最初の超高層ビルは浜松町の貿易センター。現代は、各地にそれ以上の超高層ビルが連立。 ☆ビルの屋上には、必ず「カンカン」と云うロープ等を固定する丸い鉄の輪が各所に添えつけてありました。 ☆但し、この「ブランコ」高所作業には危険も伴うので日当(手間賃)も良く、 自ら進んで作業する職人さんもいた程です。 *運動会で使用するような太いロープでもロープにペンキをこぼしたりするとロープが硬化してしまい下に降りるのも 一苦労したり、最悪の状態ではロープ折れとても危険な作業でした。 今ではワイヤーロープの電動式と進歩。 ■梯子は木製か竹製でしたが、今はアルミ製で、2連や3連伸縮梯子と多様。 ■作業着や軍手等はペンキの付着で汚れが酷くなると苛性ソーダーに暫く付け置き、 付着塗料が溶けだした頃を見計らい洗濯し使用していました。 (当時、作業着や軍手の値段は職人からすると、簡単に取り替えられる程、安くはありませんでしたので穴が空くまで再利用していました) |
| 時代 | 「おまけ」 ■昭和30初年代ころは現場への塗料等の資材運搬もまだ街の塗装店では、自社用車も少なく、 出入りの問屋さんや運送会社に依頼している会社も沢山ありました。 「現代では車を持たないと仕事はなり立ちません」 ■当時、東京/京橋で地下鉄銀座線/京橋駅の直ぐ近くに私が通っていた会社があり車も1台ありましたが、 銀座や新橋あたりの作業現場には自転車や自転車の横にサイドカーを付け(横付けと呼んでいた)で 2間=3.6mの歩み板や3尺=約90㎝から10尺=約3mの木製脚立や塗料等を積んで運搬していました。 現代では銀座のど真ん中には車や人通りも多くこのような乗り物での走行は昔だから出来た事で 現代では一寸、不可能な運搬方法となりました。 ■昭和34年当時、私が始めて貰った日給は忘れもしません200円、 仕事の出来る一人前の職人で日当=600~800円でした。 大卒の初任給が12.000~13.800円位といわれ今は亡きフランク永井さんが歌いレコードも発売されました。 ■昭和30年前後には、小学校の高学年くらいから家計を助ける為、新聞配達をする少年が(私も含め)沢山いました。 当時、私が配達した事のある「読売や朝日」新聞配達店では、夕刊配達だけの月給は150部位を配達して600円位で、 朝夕刊の配達をしても、少年たちの月給は1.500円前後位でした。 不着=配達漏れがあるとその分は差し引かれてしまいます。 *朝刊の配達は、AM 4:00前位には近くの(私たちは山手線の田端駅)へ新聞を乗せた電車が到着する時刻に合わせ 先輩(大人)の漕ぐリヤカーで行きは乗せてもらい戻りは販売店までリヤカーを押したり、 朝刊には折込広告が沢山あり重く、また風雨日など配達はとても少年たちには大変でした。 (私の通った学校(クラス)では先生から新聞配達少年たちの為に放課後の教室掃除は配達時間に遅れる為、免除された程でした) *給料日の嬉しさ、家に着くまでは私のお金、家の中に入ると家の手助けにと内職をしている母へ、 それでも朝の早起きや風雨日での配達がいやだな~と思った事は私は一度もなかったなー。 *歌手の山田太郎さんの新聞少年の歌が出たり、井沢八郎さんの「ああ上野駅」という集団就職列車で上京する 中学生達(当時は金の卵と云われていた)の歌が私たち時代の少し後になりますが、 レコードも発売されヒットしました。 終戦後、昭和20年代後半~30年代は、貧乏でも映画/歌/生活と世の中には夢や人情もありとても良き時代で良き思い出と成っています。 * 仕事に関係無し=子供たちに昭和60年頃、夏休みプレゼント。手作り神輿 「私的な画像=PDF」 * 兄から届く素敵な年賀状 「版画年賀状」 |
| * ↓ 当時はまだ丸太足場の使用 ↓ (旧)歌舞伎座、昭和30年代の室内外 塗装工事 | ||||
 正面梁 |
 屋根上での塗装工事 |
 正面入り口 |
 舞台稽古風景 |
 正面、絵看板前 |
| 歌舞伎座の室内塗装(楽屋など)には何度も行き、色々な役者さんとも会い、 舞台稽古で来ていた先代(二世)の尾上松録さんには、ご苦労様とタバコなど頂いた事を思い出します。 興行中には客席全望の舞台裏から芝居を見たり、役者さん(人間国宝)の御自宅等にも 工事に伺ったりと一般の人にはなかなか出来ない経験もしています。 私たち塗装職人は役者さんから町のえのぐ屋さんとも呼ばれていました。 そのほかにも歌舞伎演目以外で1日興行での特別興行等もたまにあり 舞台裏から拝見すると出演歌手の人達は楽屋裏では、 ものすごく緊張し歌詞を口ずさみ何度も繰り返し練習している姿も見ています。 文学座に工事に行った時には同じ敷地内に住んでいた杉村春子さんや三津田健さんなど、 ご自宅にも工事に伺った事も何度かあり、とても気さくに挨拶してくれた事を思い出します。 その他、一流企業社長(会長)さんのお屋敷など、普通では拝見出来ない重厚感と品のある立派な室内等の 塗装工事にも伺い職人として素晴しい物を見たり仕事をさせていただくという事は とても良い経験をし、勉強にもなっています。 |
||||
|
息子の職歴と一言 親の書入れで如何かと思いますが、若さ、体力と真面目が有ります。 仕事も町場(住宅)塗装専門ですが、 一級建築塗装技能士(国家検定:労働大臣認定)や 職業訓練指導員(労働省:告示第28条3項)の免許も取得済みで、 建築塗装業に従事し21年の塗装歴(2014年現在)に至っていますので、 腕(塗装技術)も着実に進歩し、お客様の受けも良い様ですので、 現在 職人の減少している世の中でも有り、 次世代を荷って行く貴重な人材に期待が持てるかと思います。 |
|
 |
資 格 所 持 |
| ■ 職業訓練指導員免許 (労働省:告示第28条3項) | |
| ■ 一級建築塗装技能士 (労働大臣認定) | |
| ■ 石綿取り扱い作業者、特別教育終了証 | |
| ■ 足場組立等作業主任者、技能講習終了証 | |
☆ 悪質な訪問販売や営業など一部に悪質な業者もいますのでご注意下さい。 国民生活センター、(ホームページ) |
当店は訪問営業員等の業者が間に入らない分、 お客様との直接受注工事ですので、同じ使用塗料と同じ工程で ペンキ塗り替え工事費もお安く出来ます。 親子で安心・親切・丁寧・信頼を売り物に頑張っています。 |
| 当店バナー | バナー アドレス |
| |
http://www.fan.hi-ho.ne.jp/wakatsuki/wakabnr2.gif |
| |
http://www.fan.hi-ho.ne.jp/wakatsuki/smibanr5.gif |
| |
http://www.fan.hi-ho.ne.jp/wakatsuki/banrwaka.gif |
| * リンク歓迎、トップページアドレス : http://www.fan.hi-ho.ne.jp/wakatsuki/ | |
| ↓事業案内↓ 他 | ↓画像も入れて工事説明↓ 他 | ↓作業を画像で紹介↓ | ↓個人的 (HP)↓ |
| 事業案内 | アメリカ・ダラス、工事見学 | モルタル外壁施工写真1 ~塗装アルバム | 気まま 便利リンク集 (個人) |
| 職歴紹介 | サイディング外壁の腐食や目地ボンド処理等、 | 窯業サイディング外壁施工写真-1 ~塗装アルバム | 千葉県リンク集 (個人) |
| 塗装工事 Q&A | 高圧洗浄 | スレート板外壁-1 ~塗装アルバム | 我孫子市情報 (個人) |
| お客様より嬉しい便り | カラーベスト(コロニアル)の縁切りとは ? | 色々な外壁、施工写真 ~塗装アルバム | 手賀沼 散歩 (個人) |
| 所持、機械 / 用具 | ローラー塗装は本当に塗膜の厚い塗装なのか? | 現場写真2 ~外壁、目地付2色塗装や透明仕上げ | |
| 保証書 | 中塗りと上塗の色変え塗装は何の為? | 現場写真3 ~色々な工事写真 | |
| 作業現場、範囲 | 塗り替え塗装時の色について | 現場写真5 ~屋根の洗浄や塗装工事アルバム | |
| 当店、地図 | |||
| サイトマップ | 小柄平板屋根(アーバニー等)の塗装に関し | お客様より当店を推薦紹介され塗装 | |
| TOPに戻る | 築後10年程度で屋根に浮き剥がれや崩れが | YouTube掲載、動画で紹介 |

