☆やっとの思いで、吹奏楽曲のガイドブック
私が高校3年生の時、母校の吹奏楽部は3学年合わせて90名以上いました。全校生徒は1,000名以上いましたが
それでもかなり多い割合です。これに匹敵するのはテニス部ぐらいだったと思います。
どんな高校でも吹奏楽部があれば30名以上のメンバーがいたと思います。まして中学校では40名以上は確実でしょう。
最近は少子化が進んで中高生自体の人数が少なくなっているのでしょうが、全日本吹奏楽コンクールともなれば、演奏者・
聴衆の数たるや並大抵のものではありません。5,000名収容のホールがすんなり満員になってしまうのですから。
私のように最初にトロンボーンに触れてから20年以上経っていても、なんらかの形で楽器演奏に携わっている人がいる
一方で、残念ながら(原因はともかく)楽器を触らなくなってしまった人が大勢いることもまた事実です。これには吹奏楽が
かなり狭い世界で完結してしまうことが一つの要因となっているような気がしてなりません。
たとえば「吹奏楽コンクール」もしかりです。「いい演奏をする」ことに対して「賞」が与えられるはずなのですが、実際
には「賞」を競うために「演奏を磨く」ことになってしまって、本来音楽にはなじまないはずの「競争」が重要な関心事に
なってきます。このことによって「演奏する楽しみ」より「競争の苦しさ」の比重が高くなり演奏者を音楽から遠ざけて
いくような気がしました。私は闘争嫌いなものですから...運がよかったのかも知れません。
もう一つは吹奏楽人口(やっている人も聴くだけの人も含めて)の多さの割に、参考となる演奏のCDの数が少ないような
気がするのです。もちろんプロフェッショナルな吹奏楽演奏団体が少ないこともあるのですが、それでなくても少ない吹奏楽
CDコーナーの大半を占めているのはやはり「全日本吹奏楽コンクール実況録音」なのです!
「いけない!」といっているのではありません。私だって自分の演奏のCDがあるんだったら手に入れたいです。でも
吹奏楽コンクールで演奏される曲の中でいったいどれくらいの曲が楽譜の完全オリジナル編成で演奏されているのでしょうか?
吹奏楽コンクールには演奏時間制限があったり人数制限があったりしますので、無惨なカットや勝手な楽器編成の変更は
「やむを得ない」範囲で黙認されています。これでは吹奏楽曲の真価を楽しむにはもの足りないと思います。そして演奏者も
聴衆も育たなくなってしまうのではないでしょうか?!
最近の私は吹奏楽曲を聴くことが多いのです。機会は多いのですがCDの数はたかが知れています。懐かしいあの曲、
最近聴いたイカすこの曲。聴きたい曲はたくさんあるのにいったいその曲がどのCDに収録されているのかを知ることが
至難の業だったのですが、なんともまあ、図ったかのように「200CD吹奏楽名曲・名演(立風書房)」という本が発売
されました。編者は音楽プロデューサーの磯田健一郎氏です。彼は吹奏楽曲に造詣が深く様々な吹奏楽CDにライナーノーツを
提供していて、それはどれもがとても軽妙な語り口でけっこう読み物としても楽しめます。この本では執筆者としても活躍して
います。他の執筆陣もプロの演奏家から大学教授、評論家など多彩です。
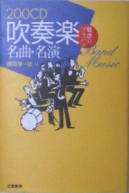 鮮やかな黄色い表紙が目印!
鮮やかな黄色い表紙が目印!
今現役で吹奏楽をやっている人にも、かつて吹奏楽に青春をかけていた人にも、純粋に吹奏楽曲が好きな人にも、きっと
この本に載っている曲でやりたい・聴きたい曲が見つけられると思います。私といえば、なんだか自分の持っているCDの
多くがこの本で紹介されているのでうれしいやら切ない?やら...これってやっぱり吹奏楽のCDが少ないってこと?!
(1999.12.2)
☆テナーサックスのバッハ
ちょっとしゃれた婦人服(この言い方はしゃれてない!)のTVCFでハイブロウなサックスが無伴奏で曲を吹いている
ものがありました。そのCFの音楽をプロデュースしたのは清水靖晃という多才な音楽家です。実はこのテナーサックスは
彼自身の演奏です。
私はバッハの無伴奏チェロのための組曲が好きです。オリジナルのチェロによる演奏ももちろんいいのですが、バッハの
音楽の奥深さとでもいいますか、その他の楽器による演奏もいいものです。中でもこのテナーサックスによる演奏はお行儀が
よいだけではない、一種の凄みをも感じさせるものとなっています。
すでに無伴奏チェロ組曲の1・2・3番がリリースされていましたが、今回残りの4・5・6番がリリースされ、待望の
全曲録音となりました。(ビクター:VICP60887)ここではまったく期待どおりの不思議な音世界が繰り広げられて
います。特に管楽器による無伴奏作品の演奏には高い集中力と精神力、そして体力が必要だと思うのですが、このCDでも
なかなか「味」のあるテナーサックスの音色も相まって、新しいバッハ像が築かれています。
この演奏を聴くとなにかの「商品名」が思い浮かんできそうですね。実はポピュラーな音楽なんですよ、バッハは。
(1999.11.21)
☆モーツァルト(子)のトロンボーン協奏曲?!
ソロ・トロンボーンの名手、クリスチャン・リンドベルィがイケナイことをやってしまいました。われわれトロンボーン
奏者がしたくてもできないアレを...
それはモーツァルトのホルン協奏曲4曲をトロンボーン(アルト)で演奏するというアレです。やっぱりこういうご無体な
ことをするのはリンドベルィですね、いつの時代でも。トロンボーン奏者はいつも、ホルン奏者がパラパーラと吹いている
この美しいモーツァルトの旋律をとてもとてもうらやましく(時には恨めしく)思っていたのですよ!
さて演奏です。ずいぶんとまあ、あっさり違和感なく吹いてしまうものだなというのが第1印象です。演奏スタイルも
ホルンをイメージさせるオーソドックスなもので、先入観なく聴いたら「ナチュラルホルン?」と勘違いしてしまうかも
知れません。
この名人芸を聴くにしたがって、音域的にはアルトトロンボーンでないと確かにつらいのですが、実はかなりの頻度で
低音域が登場するのでそれもまた大変なのだな、と思えてきました。もちろんリンドベルィの演奏からはそんな苦労は
みじんも感じられませんでしたが。むしろあまりにもすっきりしすぎてなんだかちょっと物足りないと思うのはイケナイ
ことでしょうか?
こうなったらリンドベルィにはぜひ「バッハ:無伴奏トロンボーン(チェロ)組曲全曲」を録音してもらいたいです。
聴いたCD:BIS−CD−1008/ジャン=ジャック・カントロフ指揮タピオラ・シンフォニエッタ
(1999.11.7)
☆イギリスの軍楽隊
久しぶりに、(しかも急に?)コンサートに出かけてきました。「英国女王陛下の近衛軍楽隊」。吹奏楽です。
吹奏楽のコンサートも久しぶりのことです。前回はフランスの軍楽隊「ギャルド・レピュブリケーヌ」でした。
イギリスの近衛兵といえば真っ赤なジャケットに背の高い黒のモコモコ帽子で有名です。まさかそんな格好で
演奏するわけはないだろうと思っていましたが、サービス満点!おなじみのあのスタイルで、いきなり客席入り口
から入場行進。もちろん演奏しながらです。かっこいい〜!先だってステージではトラディショナルなスタイルで
行進曲を演奏していました。
さすがに金管王国イギリスのバンドだけあって、6本のコルネット軍団をはじめ、3本のピストンチューバ、
2本の紛れもないユーフォニアムの柔らかい独特の豊かな響きに魅了されっぱなしでした。やはりコルネットによる
コルネットらしい音はトランペットとかなり違うものですね。今回の大収穫となりました。
プログラムは行進曲から始まり、オリジナルの作品やイギリス民謡調のもの、ジャズっぽい曲や様々な国の典型的
な作品など、実に様々です。すべてにおいて言えるのはとても楽しませてくれたということです。まさにエンター
テインメントです。演奏会場が東京文化会館というわりと堅めの会場というのが何ともアンマッチではありましたが。
今回の演奏会では普段めったにお目にかかるチャンスのない「バグパイプ」も登場しました。軍楽器?だけあって
ドローンという常に一定の音程で鳴り続けるパイプ3本?とメロディを奏でるパイプ1本がかなり大きな音を出して
いました。演奏者は指の操作の他に、常時空気溜の革袋に息を吹き込み続けるという相当過酷な作業をもこなさなくては
なりません。どちらかというと素朴かつ優雅な音色からは想像もつかない重労働であることが見て取れました。
演奏後の敬礼!がなんともかっこよかったですね!
プログラムが若干変更になり、ユーフォニアムのための難曲、スパークの「パントマイム」という曲を聴くことが
できました。見事な独奏に思わず大拍手をおくりましたとも!いやはやハイレベルでした。
ややクラリネット以外の木管楽器がまとまらなかったかな?と思いましたが、吹奏楽伝統国の余裕を感じさせる
とても楽しい演奏会でした。やっぱり演奏会にいかないと心が枯れてしまいます。
(1999.10.14)
☆コントラバスな話(その後)
YAHOOに自分のHPを推薦しました。載せてもらえるかどうかはまだわかりませんが...その時に自分のページが
どんなカテゴリに属するのかを調べる必要がありました。そこで「エンターテインメント」「音楽」「楽器」「管楽器」
「トロンボーン」と調べていきました。すると「管楽器」のところでなんかソソるタイトルのページがあったのです。
その名も「希少管楽器博物館」というページです。それこそコントラバストロンボーンなんて普通の楽器扱いです。(ウソ)
中でも「Contrabass Mania」というページには前回紹介した「ミラフォン/BB管コントラバス
トロンボーン」の所在?が明らかになっていました。なんと4000ドルで売っているのです。安すぎます。欲しくなります。
こんな特殊楽器は日本でお目にかかれる機会なんてないでしょう。それをインターネットが実現してくれるなんて!
(IBMのCMみたい)ダブルスライドの細工を目の当たりにしてみたいです。
それにしてもインターネットの世界にはすごいマニアがいるものです。それより同じような嗜好をした人がいることに
ちょっとだけ安心しました。危険ですか?
(1999.10.6)
☆コントラバスな話
私は相変わらずこの手の話題に目がないのです。まずはCDから。渋谷のタワーレコード6階でコントラファゴット
2重奏!のCDを発見しました。「THE 2 CONTRAS(Crystal Records CD349)」です。
以前からコントラファゴットソロのCDをリリースしていたSusan Nigro女史が再びやってくれたのです。
当然ながらこの編成のためのオリジナル作品は極少です。多くは低音楽器2重奏(コントラバスとかチェロ)の編曲なのですが、
演奏は見事!のひとことです。低音域は想像どおりの図太い響き。病みつきになりそうです。高音域は(とはいっても十分低音域)
何ともいえない柔らかい響きでこれも外観からは想像できない不思議な体験となるでしょう。問題は...オーディオでしょう。
クルマのオーディオではまったく太刀打ちできません。自宅のオーディオでも音量を上げないとイマイチ。う〜ん。
少なくともファゴット吹きの方には一度聴いてみていただきたい逸品です。不思議だ!
管楽器専門雑誌パイパーズ。並の本屋には売っていません。池袋のジュンク堂では「そんな本が出版されているんですか?」と
いわれる始末。200m北の楽器屋に売っています!といいたくなりました。というようにマニアックな、私の愛読書に見逃せない
記事が!佐伯茂樹氏の「トロンボーン・マスターピース」という連載です。とかくクラシック音楽では「音がでかくてうるさい」
楽器と認知されがちで、レパートリーもお決まり!と考えられているトロンボーンが活躍する作品を紹介・解説しているもので、
毎回「こんなことがあるのか〜」と感心しているのです。ここで「本当のコントラバス・トロンボーン」が紹介されていました。
以前にも紹介したように、今私たちが使っている、いわゆる「バストロンボーン」は「F管付きテナートロンボーン」で、
「F管コントラバス・トロンボーン」は「コントラアルト・トロンボーン(アルトの1オクターブ下)」というのが本当のところ
です。では真の「コントラバス・トロンボーン」とは?最新の10月号に写真付きで掲載されています!テナーの1オクターブ下
のBB管ダブルスライド式の「コントラバス・トロンボーン」が!
かなり興味がわきました。パイパーズ編集部にメールを送ろうかと思います。ワクワク。吹いてみたいなぁ。
(1999.9.23)
☆楽器による向き不向き
最近はアンサンブルに一生懸命取り組んでいます。苦手なのですが...で、藤沢市民交響楽団には
チューバのメンバーがいないので必然的に私が極低音域を担当させていただくということになっています。
そこで、トロンボーンでチューバパートを演奏する際の問題点について考えてみたのです。
1.いくらダブルロータリーのバストロンボーンといえども基本はB管なので、チューバ(F・C・BB)の
常用音域を同じように吹きこなすには多少無理がある。
2.トロンボーンはトランペットと同様の仲間であるのに対して、チューバはサクソルン属(円錐形の管形状)
であることから生じる音色の差異があまりにも大きい。
3.スライドアクションのトロンボーンには、バルブ・ロータリーアクションのチューバパートのフレーズを
滑らか〜に演奏することが(きちんとした奏者にはできなくはないのでしょうが、私には...)非常に
厳しい、というか向いていないことが多い。
チューバの代わりにイタリアオペラなどでよく指定されているチンバッソという低音楽器がありますが、
これも一種のコントラバストロンボーンです。管形状的には類似していますから。
やはりチューバが指定されている楽譜は演奏面でも聴く方にとってもオリジナルがよりふさわしいと思うのは
決して私だけではないはず?ですよね。
参考までに、来年の藤沢市民オペラで上演予定の「プッチーニ/ラ・ボエーム」は3本のトロンボーンの他に
「トロンボーン・コントラバッソ」の指定があります。「トゥーランドット」もそうだったのですが、実際には
コントラバストロンボーン(もしくはチンバッソ)で演奏することはできません。楽器がないですから...
でも試しにオリジナルでやってみたい気はしますね。すごく低音の立ち上がりが早くて結構快感です。
(1999.9.6)
☆極低音楽器のアンサンブル
「ギコギコギコギコギコギコギコギコ」...
今度やるアンサンブルで最大の難曲「テレマン:4声の協奏曲」はもともとヴァイオリン4本のための作品
なのですが、昔からいろいろな同族楽器のために編曲されています。もちろんトロンボーン用にも編曲されて
いて、特にスローカートロンボーン四重奏団の演奏によりその筋ではかなりの有名曲となっています。
今日オーケストラの合宿から戻り、その足でアキハバラへリサーチしに(物色という)いったところ、
なんだかんだ言いながらもブラスアンサンブルのCDが気になって柄にもなくCDを探していましたが、
ブラスアンサンブルばかりのはずのCDコーナーになぜか「コントラバス四重奏」という私好みの?CDが
混入されていたのでした。(MDG 603 0634−2「Quattro contra bassi」)
「なんだよこれ〜」またまた柄にもなく元の棚に戻そうとして(やんなくてもいいのにねえ、わざわざ)
そのCDを手に取ってみるとその中の1曲に前出のテレマンの四重奏が入っているようなのです。
「まさか?でも合宿の時に、今幸せの絶頂にある後輩が『この曲コントラバスでやってたんですけどもう
グチャグチャ!』とかいってたし...」と、昨晩の寝不足が災いして思考能力が極度に低下してしまった頭で
いろいろ思いを巡らせて、根拠のない確信を持ってこのCDを購入してみました。
そして聴いてみると...冒頭のようなありさまです。アンサンブルは当然のことながら完璧。しかも
ジャケットを見てみるとなんと!このアンサンブル「フランクフルト・コントラバス四重奏団」は全員
「いいお姉ちゃん(北野武風)」だったのです!
実際にはとてもコントラバスとは思えないなめらかな音色で、実にオリジナルっぽく聞こえます。その他
当然オリジナルの委嘱作品と思われる現代の作品(意外と聴きやすい)が収録されていてバスフェチ??
には必携の一枚といえます。
偶然にしてはあまりにも間が良すぎて怖くなりましたが、それにしてもなぜこのCDはブラスアンサンブル
のコーナーにあったんでしょうね?一瞬、輸入楽譜屋「アカデミア・ミュージック」で見かけた「コントラバス
トロンボーン4本・ハープ・打楽器のための音楽」(どう見ても現代音楽!)が入っているのかと思いました。
(1999.8.22)
☆バストロンボーン購入ツアー
7月25日の日曜日、久しぶりに楽器屋めぐりをしました。とはいっても別に私が楽器を選ぶわけではなくて、
オーケストラの仲間がバストロンボーンを調達したいとのことでしたので私もあやかった?ということです。
まずは当初の目的地である渋谷の「アクタス」へ。ここはアメリカ製トランペット・トロンボーンのトップメーカー
「ヴィンセント・バック」社の製品を輸入しているノナカのショウルームです。お目当てはダブルセイヤーヴァルブ搭載の
バストロンボーンです。この機種はかなり人気が高く「あるものを試奏できるだけでもめっけもん!」という貴重な楽器です。
ここでかなり長い時間居座りましたが、せっかくなので(神奈川県からお越しです)管楽器の聖地?新大久保へいくことに。
さっそく駅のすぐそば「山野楽器ウィンドクルー」へいきましたが、お目当てのバストロンボーン自体がほとんどなく、
しかたがないので簡易型防音室の中から大声を出すことによってストレス発散をする始末。やれやれ...
それでは、ということで開業20周年の老舗?「ダク」へ行きました。ここには様々なバストロンボーンだけではなく、
あの「レッチェ」のテナーバストロンボーンやアルトトロンボーンの中古、まだ売れていないチェルヴィニー?の楕円形
バリトン(テナーチューバ)も置いてありました。一緒に行ったトロンボーン仲間はアルトトロンボーンを吹いて非常に
欲しがっていました。それじゃ「ミイラ取りが...」じゃないのでしょうか?
このツアーで私が一番感銘を受けたのは「ダク」であの!!ファゴットのトップブランド「ヘッケル」の実物を見ることが
できたことでしょう!「ヘッケル」は通常フルオーダー制で発注から納品まで2〜3年かかるというシロモノです。
(発注の際には「手型(手の型)」をファックスで送るらしいです。)お値段のほうも次元が違っていましたが、
引き合いは多いそうです。楽器自体の仕上がりも素晴らしく芸術品としての風格まで感じさせるところがまたすごいです。
その他、アメリカのフルートメーカー「ヘインズ(Tシャツメーカーとは綴りが違います)」の14kゴールドフルートも
美しいできばえで感動しました。日本の高級車がフルオプション付きで買えそうなお値段でしたが...
で、結局バストロンボーンの方は???わたしも「ミイラ取り」?(意味深)
(1999.7.28)
☆音楽を聴かせてくれるモノ
楽器といえば「演奏するモノ」と相場が決まっています。つまり楽器を通して音楽を聴かせるということ自体がそれを「楽器」に
しているのですね。ちょっとややこしいことを書いていますが、そうなるとオーディオ装置もパソコンでも広〜い意味では「楽器」と
いうことになるのでしょうか。
とあるオーディオ評論家が「レコード演奏」という言葉を使っています。要するにオーディオ装置を駆使してレコード(CDでも
OK!)をその人が考えているように鳴らすことが「演奏行為」である、という考え方です。確かにこれぐらいの人になってくると
非常に積極的にアグレッシヴに自発的に信念を持ってレコードの中に記録されている音楽を表現していきます。なにもプロでなくても
世の中には大勢こういう称号を得られそうな人がいるみたいです。私はほど遠いですが...
当たり前のことですが、オーディオ装置によってレコードの音楽は「!?」というぐらい変わってしまいます。「こんなにいろんな
音が入っていたんだ!」とかがわかるようになってきます。このことがその音楽性を高めることに役立つのは事実なのです。
もし、音楽好きな人で自分の使っているオーディオがちょっと寂しいという人は思いきっていいオーディオに替えてみるのも
いいかもしれません。楽器をやっている人にはわかりやすいですが、ちょうどそれはいい楽器に買い換えるようなものです。
少しでもいい音を出したい、いい音楽をしたいという気持ちでみれば共通点がありますよね。たしかに。
ちなみに、ノート型パソコンのスピーカーで注目すべきなのは、コンパック:JBL、IBM:アルテック・ランシングという、
オーディオ好きならそれだけでもつい購入の対象になりかねないような名門スピーカー会社がユニットを供給している事実がある
ことです。これなら十分に「楽器」といっても差し支えないほどのインパクトがありますね。
ところが、「楽器」でなら数十万円をスパッと出せるのにオーディオでは財布の紐が堅いのはいったいどうしてなのでしょう??
はやくEAR859よ!カムバック〜!!
(1999.7.18)
いま私が使用しているバストロンボーン(と一般的には呼ばれていますし、そう認知されています)は、厳密には
「F−Esインラインダブルロータリー付き極太管極大ベルB管テナートロンボーン」というべきものなのかもしれません。
と、いうのも本当の意味では「低いF管」がバストロンボーンのはずだからです。今ではこれを「コントラバストロンボーン」と
いっています。これはどちらかというと「コントラアルトトロンボーン」というのが本当?になるのでしょうか?
管の長さが変わると劇的に変化するのは音色です。当然倍音の順序が変わってきますから。いくらF管のバルブが発達したと
いっても、直管とは比べようもありませんし、もし作曲者がその管長の楽器の音色を念頭に置いていたとすると...
オリジナルがブームの昨今では興味深いところです。
もっとも、今でいうF管のコントラバストロンボーンでは第7ポジション(低い「H」の音が出ます)にスライド直持ちで
持っていくことは不可能です。そんなこともあってF管付きB管トロンボーンに置き換えられていったのですから、よほどの
理由がない限り元の鞘に収まる?のはムリだといえます。
とか何とかいっているのは、私の修行不足のせいに他なりません。かつてレッチェのコントラバストロンボーンの中古を
買おうか買うまいかさんざん迷ったあげく、その巨大なマウスピースに恐れをなしてついに断念したのは私です。
プロのバストロンボーン奏者は実に豊かな素晴らしい音色で私を魅了してくれます!彼らの楽器は決して特別なものでは
ありません。ちょっとがんばってお金を積めば私のような半端モノにも買うことが可能な楽器を使っていながら
(トロンボーンの世界は実に経済的にできていまして、超一流のプロが使うような楽器でもそんなに高くないのです。
弦楽器やフルートの値段と比べたら、比べられませんが...100万円を超えるモノはめったにありません。)
その音色だけをみても...とてもとてもかなうものではありません。あったり前なのですが。
素人さんでも新しいポルシェに乗れば時速250キロ出すのは可能でしょう。でも...私がレッチェを吹いても
チースリック師匠(勝手に仰いだ!)にはなれないからなぁ、絶対。
何がいいたいのかと?要するに楽器はあくまでも道具であってそれを使うのは人間なんだから「その人なり」になっていく
のが自然の道理なんだなぁ〜と、ドムス教授のバストロンボーン用オーケストラスタディ(10000円超!!)を前にして
妙に深く考え込んでしまう今日この頃なのです!といいたいのでした。
(1999.7.8)
☆ロンドンのフレンチホルン軍団
フレンチホルンという楽器があります。ムーミン谷の学者ヘムレンさんが吹いていたり、ヤングサンデーというちょっと若者向けの雑誌で連載
されている「ブラブラバンバン」というちょいとエッチ?な学園マンガのヒロインが吹いていたりしていま注目!?の楽器です。
元々は狩の角笛から発展していった楽器ですが、金管楽器の中ではソロでもトゥッティでも花形の地位を築いていて、トロンボーン奏者としては
かなりジェラシィをもっています。トロンボーンより管の長さが長いくせに高音域はトランペットなみ!そして低音域はチューバなみときています!
オーケストラの中でも出番は多く、室内楽でも引く手あまた。ホルンをひいきにしていた作曲家もたくさんいます。バッハも「ブランデンブルク協奏曲」
の中でソロ楽器として対で使っていますし、モーツァルトは4つもコンチェルトを書いているし、リヒャルト・シュトラウスは過剰なまでな愛情を持って
この楽器を様々な場面で使用しています。
この憎き(???)ライバルにはまた、数多くのアンサンブルCDがリリースされています。今回は「THE LONDON HORN SOUND」
というロンドンで活躍するホルン奏者32名が様々な組み合わせで「?!」という曲を演奏しているCDを聴きました。
最初の曲は「タイタニック」ファンタジー。あの大ヒット映画の音楽をホルン12本で奏でています。いかにも映画音楽はホルン向きですね。
その他、クラシックの序曲やらジャズのスタンダードナンバーやらが並んでいます。私はグリンカ「ルスランとリュドミラ」序曲聴きたさにこのCDを
買ったのですが、なんといっても驚きはベルリオーズ「ローマの謝肉祭」序曲でした!16本!!のホルンと打楽器でほとんど違和感なくこの
大編成管弦楽曲を堂々のスケールで演奏しまくっています!びっくりしてしまいましたとも!またジャズホルン奏者の演奏はその軽やかなことと
いったら!比類ないです。こういう世界もあり、なんですね。とにかく驚きの連続でした。独奏者にはマイケル・トンプソンとかフランク・ロイドとか
デヴィット・パイヤットとか、そうそうたる面々の名前が...すごくて当然。
このシリーズにはトロンボーンアンサンブルのもありました。「76本のトロンボーン」という曲を本当に76本で演奏するという企画がなかなか...
ロンドンの音楽界はかなりいい線いっているんですね、ヘンデルの昔から。「ドイツやアメリカばかりがメジャーじゃない!」といったところです。
(1999.6.27)
☆楕円のやつ
リヒャルト・ヴィルヘルム・ヴァーグナー(ワーグナーのことです)は彼の思い通りの音楽芸術を実現するために実に様々な楽器を
創造しました。有名なのはヴァルト・ホルン(フレンチホルン)の低音域を拡張するために造られた「ワーグナー・チューバ」(そのまんま!)
でしょう。ブルックナーもこの楽器がお気に入りだったようで第7番以降の交響曲に効果的に使用されています。
その低音域の響きはまさに地を這うような、地鳴りのようなものです。一方高音域では独特の柔らかい音色で音楽全体を包み込むような
響きがします。聴く者の想像力をかき立てる楽器です。形は題名の通り、楕円形のちょっとユーモラスな外観です。
この形はこの楽器だけのオリジナル?というわけではないようで、ドイツなどでは軍楽隊で用いられるバリトンがよく似た形をしています。
私のようにミーハーな人間はその形を見ただけで吹きたくなってしまいます。実際吹いてみたのですが、まあ、吹奏楽でおなじみの
ユーフォニウムよりも吹奏時の抵抗感が少なくてトロンボーン奏者的にはそれこそ抵抗なく吹けました。おまけにロータリーバルブなので
ドイツ管好きにはもってこいです。
いままでに吹いた楽器のメーカーはチェコのチルヴィニー(?)とドイツのマイスター・アントンです。特に前者はなんといってもお値段が
よろしかったのでなんだか物欲を刺激されてしまいます。
でも、なにに使うんですか?またもや自問自答です。チューバ欠席時の代奏ですかね。それともマーラーの交響曲第7番とか、
ホルストの「惑星」とかリヒャルト・シュトラウスの「英雄の生涯」とかストラヴィンスキーの「春の祭典」とかやるんだったら
出番がありますね...結構出番があるんじゃないですか!
吹奏楽団になぐり込みとかも...へんなの扱いされそうで怖いです。
(1999.6.16)
★麗しの低音
コントラバス(マイクロバスの反対語←大ウソ)ほど「麗しい」という言葉が似つかわしくないものもないでしょうね。
それでも低音はいいですよ。アルトフルートの低音はドキドキします。(ラヴェル:ダフニスとクロエ、ストラヴィンスキー
:春の祭典など)コールアングレは心を落ち着かせます。(ドボルザーク:交響曲第9番「新世界より」など)
バスクラリネットは以外と飛び跳ねています。(ストラヴィンスキー:春の祭典など)コントラファゴットは踊っています。
(ラヴェル:ダフニスとクロエなど)...なんだかんだでおどろおどろしい曲ばっかり?ですね。
自分が低音楽器をやっているせいか(実は声も低いのですが)低音は好きです。今日買ったCDはタイトルがズバリ
「低音王」(笑)です。これはコントラバス(弦楽器)のさまざまな演奏形態を集めたCDです。なかなか泣かせる演奏で
うれしい限りです。妙に軽快な音楽なのが不思議といえば不思議なのですが。
かなり昔(20年ぐらい昔!)NHKで「音楽の広場」という番組をやっていました。そのなかで低音楽器ばかりを特集した
回があって普段そんなにわからない極低音楽器の音色や低音楽器だけのアンサンブルを聴くことができてなかなか楽しかった
記憶があります。
しかしながら、普通のオーディオで低音楽器の迫力あるサウンドを満喫するのはかなり困難を極めます。
やっぱり生演奏が一番!?バスドラムのピアノ1発もコンサートホールなら空気の動きを感じることができますからね。
それにしても...前回はフルートで今回はコントラバスか...わやくちゃだ。
(1999.5.23)
☆あこがれのフルート
小学生の頃、音楽の時間に聴いた曲で当時の自分のマイブームとなった曲がありました。
それは、ビゼーの「アルルの女」の「メヌエット」でした。フルートとハープの美しいデュエットと、
突然その会話を打ち破るオーケストラのトゥッティ!再びデュエット...母親に「レコードを買ってくれっ」と
ねだったのはいうまでもありません。考えてみるとこれが私のクラシック音楽事始めだったのかもしれません。
その後、中学生になって吹奏楽部に入部し、一応男の子らしくトランペットをやりたい!ということにしてみました。
結局、比較的大柄な体格を買われて(?)トロンボーンを吹くことになったのはご想像の通りです。
そういえば、フルートを吹いていた子に初恋をしたのもこの頃だったか...
このようないきさつから(???)かなりのフルート好きとなっていたのです。
オーケストラの中のフルートは相当ソリスティックな(ソリストなんですけどね)演奏を楽しませてくれます。
それぞれがあらゆる面で名手なのですが、当時オランダのアムステルダム・コンセルトヘボウ・オーケストラの
首席フルート奏者で現在ボストン交響楽団(小沢征爾が音楽監督!)の首席となったジャック・ゾーンの演奏を
忘れることができません。
そのときの曲はラヴェルの「ダフニスとクロエ」第2組曲でした。2曲目にフルートの技巧的なソロがあるのですが、
そのソロのすばらしいことったらなかったです!突然ステージが真っ暗になって彼にだけスポットライトが当てられたかの
ように感じました。まさに「パントマイム」そのものでした。
彼の使用している楽器は一般的なフルートのように金属製ではなく木管のフルートだったのですが、その音量、音色
表現といい、ほとんど理想的な、めまいを起こしそうなくらいに強烈な印象を私に与えてくれたのです。
その彼のフルート・ソロ(つまり無伴奏!)のCDが発売されています。おまけに曲目はバッハ!!なのです。
集中度の高い、中身の詰まった名演です。(ポニー・キャニオンより発売中。「だんご」と同じだ...)
あっという間に時間が経ってしまいますよ。
(1999.5.16)
☆マイスター来日!(行ってきました)
大雨の中待ちに待ったレッチェ工房のマイスター、ニーンアーバー氏の技を見に行ってきました。
とはいっても、場所を間違えていていきなりダクさんの店舗に行ってしまいました。本当は同じ新大久保に
ある楽器商社?のグローバルさんの地下スタジオ特設会場が目的地でした。が、案の定、道に迷いに迷って
適当な路地裏をさまよっていたら偶然にも発見できました。(吉野屋奥)
期待に胸膨らませ、地下スタジオに入るとそこはまさにレッチェのワンダーランドと化しておりましたぁ!(古い!)
 ←ポザウネ(トロンボーン)だけでもこんな感じ!
←ポザウネ(トロンボーン)だけでもこんな感じ!
中でも異彩を放っていたのは、なんと11インチ(27センチ)もの大型銀製のベルを持つバストロンボーンでした!
 ←左側が11インチ銀ベルです。
←左側が11インチ銀ベルです。 ←比べてみると...でかい。
←比べてみると...でかい。
最初の写真では5本のテナーバスが見えますが、それぞれボアの太さが違ったりベルクランツの幅が違ったり、
ロータリーアクションがレバーかひもか、などシンプルな中にも個性豊かなレッチェの真髄を垣間見せてくれます。
 ←同じように見えてもそれぞれ明確に違いがあるのです。
←同じように見えてもそれぞれ明確に違いがあるのです。
わたしのお目当てコントラバスもありました。
 ←ダクの方にご協力いただきました。巨大です。
←ダクの方にご協力いただきました。巨大です。 ←バスとの比較です。
←バスとの比較です。
マイスター・ニーンアーバー氏は物静かな、まさに「職人」といった感じの方でした。
荒天の中、プロ・アマチュアとも実に多くの人が、またとない(かもしれない)機会を逃すまいとこの会場を訪れて
いて、楽器談義に花を咲かせるといった場面もあり、そちらもかなり楽しいイベント?となっていました。
「レッチェ」を必要としているトロンボーン奏者は世の中に大勢いるんだなぁ、と感心したり納得したりと、
トロンボーンのドイツ管の代名詞ともいえる「レッチェ」の醍醐味を存分に楽しめた一日でした。(5/5まで開催!)
それにしてもほとんどの楽器が「売約済」だったのには驚きましたな。グラリ...
(1999.5.4)
☆マイスター来日!
もう1ヶ月も前に「はぁ...」とため息をつかせたレッチェですが、なんと!その工房の
マイスター、ニーンアーバー氏がゴールデンウィークに来日するという情報が!!
それにあわせて、招聘先の楽器店「ダク」(東京都新宿区)でトロンボーンの小さいの(アルト)から
大きいの(コントラバス)まで展示されるそうです。おまけに新作のトランペットまで。
レッチェといえばトロンボーンというイメージがあるのですが、金管楽器のマイスターともなると
だいたいのものは作れてしまうんでしょうね。チンバッソ(縦型ロータリーヴァルブ式コントラバス)
は持ってこないんでしょうかね?需要がない?一度吹いてみたいものです。
今回の目玉はニーンアーバー氏による楽器クリニックです。こうなるとなんか楽器の調子悪いところを
見つけたくなりますが、幸か不幸か?絶好調なのでどうしたものでしょうかね。
エキサイティングなゴールデンウィークを迎えられそうです。
(1999.4.25)
☆「レッチェ」マジック
「はぁ...」
今日はいまいちの天気でしたが久々に銀座へ行きました。
「パイパーズ」という管楽器の専門雑誌を求めて「ヤマハ銀座店」へ。結局その他いろいろの
本・楽譜・CDを買い込んでいつもどおり3階の楽器売場へ。
そこで私は「ヤマハ製ドイツ式トロンボーン」を眺めて、「わざわざ値段の高いドイツ製を買わなくても
これでいいのかも...作りも仕上げも抜群だし。」と妙に納得しながら奥へ進んでいくと、なんと!
珍しく「レッチェ謹製純正ドイツ式ポザウネ(ドイツ語で『トロンボーン』のこと)」が展示されているでは
ないですか!思わず値札に目がいきましたが...「か、買えるわけないだろ〜」のお値段でした。
しかし見れば見るほどその造形美に心奪われること15分。
「管はかなり細いな。」「ベルクランツが10センチぐらいあって吹いたらキツそ〜。」「ヘビ飾りフル装備か。」
「テナーボーゲン付きか。」などと執拗にチェックを重ねましたが吹く勇気もなく(マウスピースを持っていないんです。)
呆然と立ちつくすのみでした。
「楽器は吹いてみてナンボ」というのが一応信条なのですが、レッチェに関してはまさに見る者をも圧倒するような
すばらしいルックスです。美術工芸品として手に入れたいぐらいですね。
「はぁ〜」出るのはため息ばかり...ですか。
(1999.3.21)
☆私の楽器紹介
せっかくですから、私の楽器遍歴を紹介させていただきます。
1.ヤマハYSL841(#002824)
〈太管テナー 8.5インチイエローブラス(確か?)ベル〉
・高校(愛知県立横須賀高等学校)入学の際に両親に買ってもらいました。
もう18年も前のことです。この楽器で昭和を乗り切りました。(ほんと!)
今の自分には軽すぎますが、当時ヤマハが総力を結集して開発しただけのことは
あってなかなかいい楽器です。
2.ホルトンTR159(#?????)
〈太管デュアルボアテナーバス 9インチゴールドブラスベル ライトウェイトスライド〉
・自分の稼いだお金で買った初めての楽器です。「太管」「アカデカベル」という
私の好みを決定づけた記念碑的な存在です。いまはもう手放しています。
この楽器でオペラ(グノー:ファウスト)ではトップを、ワーグナーの「さまよえる
オランダ人」序曲ではバストロンボーンパートを吹いたりとムチャのきく楽器でした。
3.バック50GBH3(#?????)←型番はよくわかりません!
〈バス F/GesインラインWロータリー 9.5インチゴールドブラスヘビーベル LWスライド〉
・順当にベル径が大きくなっていますね、実は。
この楽器はきつかったです。当時ヘビーが流行っていましたね、マウスピースとかも。
ホルトンでバストロンボーンパートを吹くのに限界を感じていたところに出会いました。
じっくり試奏・即購入がモットーのわたしは、購入直後にブラームスの第2番が控えていたにも
かかわらず、さっそくその本番で活躍させてみました!Good!いまはもう手放しています。
この楽器で藤沢市民オペラ「プッチーニ:トゥーランドット」にも出演したっけ。懐かしい。
4.ヘルムート・ホイクト バストロンボーン
〈バス F/GesインラインWロータリー 10インチゴールドブラスベル〉
・初めてのドイツ管です。その割に値段がお手頃だったので「じっくり試奏・即購入」でした。
プロコフィエフ:「ロミオとジュリエット」で低音域の音程に悩まされてつらかったです。
不慣れなだけだったのかもしれませんね。吹き心地は抜群だったのに...青かったのかも?
5.ユルゲン・ホイクト テナーバストロンボーン
〈テナーバス テナーボーゲン付き 9インチローズブラスベル LWスライド〉
・一番本番に恵まれていない不遇の楽器。残念です。
かなりくせが強いのですが、自分の好みに合っているだけにつらいところです。
いつになったらオーケストラの本番に使ってあげられるのやら...
6.ヘルベルト・レッチェ モデル チースリック
〈バス F/GインラインWロータリー 10.5インチゴールドブラスベル LWスライド〉
・バストロンボーン界の「ポルシェ」とでもいうべき最高の楽器です。
名前の由来はベルリンフィルハーモニー管弦楽団の名バストロンボーン奏者「ジ−クフリート
チースリック」氏が設計したことにちなみます。
「ポルシェで250キロ出せないドライバーにならないよう、精進するつもりです。」とでもいえば
おわかりいただけるでしょうか。がんばって練習しないと鳴らなくなることこの上ないです。
それにしても...いい楽器なんですよ。これ!!結果出さなきゃ...
次回はマウスピースについてお話します。
(1999.3.14)
☆もう買うまいぞ!でも...
「楽器屋めぐり」の中で「もう楽器は買わないと思う」なんて書いて
いますが、最近気になる楽器があるんです。(...)
それは、アメリカ製の「オールズ(中古じゃないです新品です)」と
いう楽器です。パイパーズという管楽器専門の月刊誌に広告が載って
いました。
わたしと同年代の方にはおなじみのデニス・ウィック著「トロンボーン
のテクニック」でほんの少しだけ紹介されていた楽器ですが、現物は後にも
先にも見たことがありませんでした。
その幻の楽器が新品(「オールズ」でも。)で存在するらしいのです!しかも
お手ごろ価格(30万円弱)のようですし。でも楽器は吹いてみないことには
何もわからないし...う〜ん。とりあえず広告を出していた楽器屋さんへ。
あった!想像よりもかなり赤いベル。マジ好みッス。吹いてみると、思った
よりしっかりした吹き心地で音色も柔らかい。惚れたッス。しかもドイツ管
愛用者には涙モノのスプリングスライドストッパー!!おぉぉ!!!
でも、だいたいバストロ奏者がいつテナーバス使うんですか?
(1999.2.28)
☆楽器屋さんめぐり
今使っている楽器は確か4年前に東京の新大久保の楽器屋さんで買いました。
「新大久保」ってちょっと色っぽい(はぁ...?)イメージがありますが、
実は管楽器を扱う楽器屋さんが集まっているんです。
自分で買った楽器第1号(ホルトンのTR159です。懐かしい。)も、
第2号(バックの50BG3HB。重かった。)も、第3号(ヘルムート・
ホイクトのインラインダブルロータリーB.TB。好きだったのに...)も、
第4号(ユルゲン・ホイクトのT−B.TB。実はいい楽器。)も、第5号
(レッチェ!のチースリック・モデル。もうこれ以上は...)もすべて
新大久保で買ったのです。結構ブッ込んでますね。こう見ると。
もうしばらく楽器は買わないとは思いますが、やっぱり楽器屋さんにいって
ピカピカの楽器(トロンボーンに限らず)を見るのは楽しいもんです。
銀座に行くと、もっと上品(?)な楽器「フルート」をいっぱい見ることが
できます。こんな私(オトコ)でも小学生のころはフルートが吹きたくて
しかたがなかったんですよ。これ、ホント。
特に、5メガ円(5,000,000円!!)超級のプラチナ製フルート
ときたら...ため息が出ますね。はぁ。
(1999.2.26)