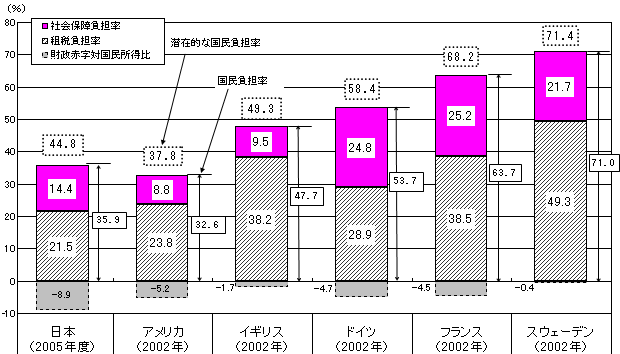| メス! | 税調は何をやっているのか?批判する為にも、税制を真剣に考えよう! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | H17年8月1日付.郵政民営化審議の真最中である.それを他所に、税調では税金改革の論議で、サラリーマンの所得税控除額を減らす案を諮問した.既に「配偶者特別控除」廃止.「消費税免税点1000万円」「所得税の特別控除枠」半減が実行された.消費税も10%になどと増税論議である.が、増税は本当に必要か?結論を言えば、本元の税調が「一般会計82兆」とのたまっている間は、増税の道しか残されていない.又、「足りない分を、何かで補う」式の発想では、何の方策も打ち出せないと考えている.目先にこだわらない真剣な論議が必要だ.国民の意識調査をどんどん行い、論議を高める必要がある.我々はもっと税金に関心を持つべきである.高校生の教育から論議する必要があるだろう.納税の義務を、今、心新たに考えるべきである. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 納税は憲法上納付義務を負わされており、納税しないと責任を問われる.その納付は、租税法で決められている(通常は税金といわずに租税という).租税は、納税の性格上、直接税と間接税に分けられている.用語的には下記の区別がある.
るが、その際はその物を管理所有する個人や会社となる.**担税者とは税を払う本人である. 消費税は財の消費者が税を支払いう.税徴収の代行である事業主が納税する.目的税は、目的財の購入者が直接納税するが、消費税も上乗せされ課税されている.消費税は、国税4%・地方税1%の計5%である.下図、H17年度予算で税収額を見る(単位:億円). ***累進課税の是非も必ず問われる. 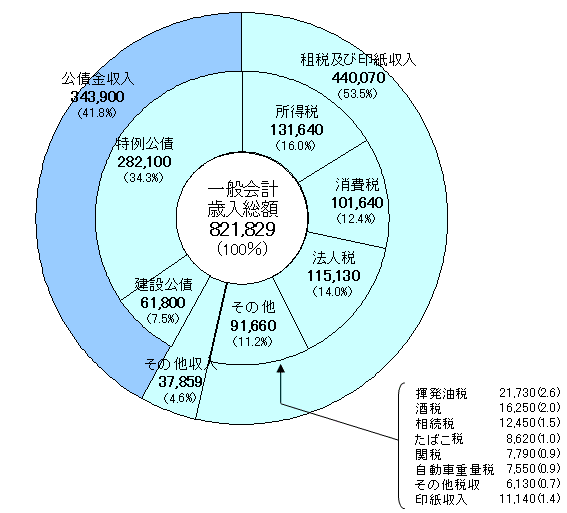 租税を考える場合、直接税と間接税の比率が基本となる.現在は60:40%(2000年、61.3:38.7である)で直接税の方が多いが、流動的である.戦前は35:65だったが.1980年度は70:30であった.敗戦後のシャ−プ税制改革で米国よりの税制になったのである.米国は直間比率93.3:6.7である.仏の直間比率は43.3:56.7である.従って直接税の参考は米国に、間接税は欧を参考としている.特に、付加価値税とみなされる消費税は欧州(EU)を模倣した税制であるが、単に財に掛けている税でこの点は欧州(EU)と異なっている.直間比率、僕は50:50で良いのではないか?と考えている(後述). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 租税を判断する場合、次の2つ尺度が用いられる.
では、国民負担率(%:下図)を比較してみよう.国民に対する国の姿勢が学べる.日本は35.9%で、米国と並び先進国の中では低いというが、国際間での評価は低福祉・低負担である.医療に関しては医療費抑制と皆保険が評価されている.英国47.72%.福祉大国といわれるスウェーデンは最高水準で71%(地方税の重複部分を割引いても突出しているが、要は中身.後述).日本の福祉水準が低いといわれるのは、福祉に関する社会保障費が少ないからで、ウサギ小屋にすんでいると言われる所以.では、同じ負担率の米国が低福祉と言われないの何故かというと、医療保険費が入っていないからである(米国の公的医療保険は低所得者用のメディケイド..4人家族の年収140万未満なら国の保険に入れる..と、高齢者と障害者用のメディケアがある.約7000万人に恩恵が有る.通常、一般人は任意の民間保険に入っており1億7000万人.保険に入っていない人口が4000万人.つまり人口の75%は公的保険の恩恵がない).日本の社会保障費率14.4%に比し、米国8.8%で民間医療負担分を算入すれば日本よりは高比率なるが、正確な金額は不明.英国は、社会保障費率を9.5%となって負担率を上げた(2000年から医療費を1.5倍に増やし独・仏並みとした.サッチャー首相時は、医療費を抑制して負担率が低くなっていたが、これにより英国医療の質が低下し、社会問題となったので改革雅行われた結果の数字である). 但し、財政赤字分を考慮すると、日本の国民負担率(%)は44.8%となります.日本の社会保障費とは、強制徴収の健康保険と年金、労働保険、介護保険等である.北欧は財政黒字なので、国民負担率(%)はやや数字が下がるが高負担は変わらない.では、福祉対策にどのような違いがあるかといえば、スウェーデンの事例では、出産費用は無料.育児休暇中は、80%で給与保障あり.18歳までの医療費は無料.16歳まで児童手当あり.大学までの教育費は無料.老後の年金は確保され、介護も万全.日本の年金破綻?とは無縁です.どちらが国民を向いているか歴然としているのがお分かりでしょう.日本は単に財を求め、財政の無駄遣いをしているのです.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 税金の問題.平等に課税することが建前であるが、累進課税を基本とするので平等にはならない.ここが北欧と異なっている. 1)所得税 この税の問題点は、徴収方法にも税の平等性がないということ.所得補足率が異なるので、自己申告制は虚偽が多くなる.クロヨン(9割・6割・4割)問題という.消費税のない国は、当然ある.
2)法人・事業税 法人・事業の種類により、不平等がある.大きな問題となっているのは公益法人(特殊法人を含む)、特別行政法人、いわゆる法人. 3)消費税 間接税は定率課税なので、低所得者ほど負担率が高い(負担感は強くない).消費税は、申告制度(簡易課税制度)の違いによりみなし仕入れ率の選択や免税点で益税が生じる.つまり、消費者が支払った消費税が納税されないで収益になる. 4)目的税 「普通税」は使い道を特定しないで徴収されるものをいいますが、この「目的税」は言葉の如く、使い道を決められて徴収される税金です.通常間接税の中に含まれて徴収されています.この場合消費税が更に課税されているので、二重課税になります.
2002年度、直接税は、所得税32.4%・法人税22.9%・、相続税3.1%他で28.5兆である.間接税は23.5兆で、消費税はその20.1%を占めている.消費税導入の重要性はこの比率に表れるが、計48.8兆円.2005年度に、その所得税の定率減税を50%カットしたなら、消費税は数年は手をつけれない.小泉首相の財務期間は消費税を上げない公約なので先に定率減税カットになり、配偶者控除を認めず、サラリーマンの控除額をカットということで、とりあえず「足りない分を、何かで補う」という手法となった.本来、付加価値税として消費税を導入したのではないので、財消費のみの税は財の価値が下がっていることを考えれば認めることはできない.本来、EU諸国のように福祉目的税を加味させたいのであろうが、介護保険を別枠で創設したので新たな税の創設ということになるのだろう.先ず、老人医療保険になりそうである.もとに戻ろう! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 次に税金の使われ方を見てみましょう.これは一般会計の歳出から見ます.H17年度歳出.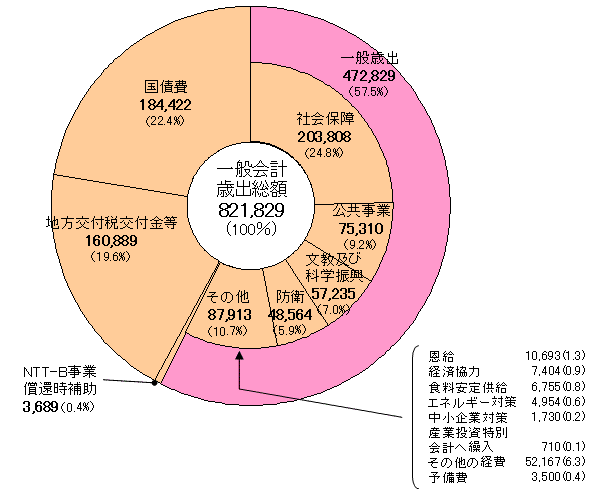 税金は何に使われているかというと、第1位:社会保障関係費、2位:国債費*、3位:地方交付税交付金で以下順に、公共事業、分教及び科学振興費、防衛費、・・・となっているが(*国債費とは借入金の返済費用です)、問題はその使われ方.国の政策の重点は公共工事にあり一般会計で7.5兆.交付金を受けた地方自治体の公共事業費が24.5兆で併せれば32兆です.社会保障は二の次という事が判ります.公共工事全体を削減しない限り、ここでの無駄遣いは直らないということです.本邦の公共事業のGDP比は、5.1%であり、欧米は平均2%です.比較的多いフランスでも3%.一方、社会保障費はGDP比9.9%.欧米の15.2%比べてかなり低い.高齢化で社会保障費は必ず増加するが財源がないといって増税するのはナンセンス.今のままでも、公共事業を1/2に削減すれば16兆の財源が生まれるますし、特別会計を廃止すれば47兆の持ち出しは1/3は吸収できる.結局は、政治家・役人が「民を大切にするか」だけの問題. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 「払った税金は有意義に使われているのか?」を考える.国と地方の総歳入は160兆.歳入で問題なのは公債費(公債依存率40%なんて国は、産業国では日本だけである.英国0.2%,米国8.8%、イタリア13.9%、ドイツ18.3%である.しかも累積赤字はGDP比140%である.近年イタリアはGDP比125%の借入金を解決しつつある.日本も習うべきである). 歳出の方は、先ず公務員人件費26兆、地方交付金16兆、特別会計繰入47兆円、公共事業32兆である.中でも人件費がもっとも削減が難しい.公務員給料は、人事院勧告に基づいて確実に伸びている.確かに大手民間会社を対象とした民間ベースで増加率を決めているだろうが、不況の時は民間給与は下がる.しかし公務員は微増している.その結果、今や地方公務員の平均年収は大手民間の1.5倍である.加えて、特別会計下の公務員にはかなりのお手盛り(優遇手当)が付いている.さらに定年退職後も、給与がもらえるポストが容易されている.そういう網の目のような官僚システムの中に無駄が潜んでいる.日本は財政面から見れば60%社会主義国家であるから、6割は官僚システムに飲込まれる.この6割が無駄である.官僚システムは、監査機能のない特別会計や財政投融資を介して動くのである.特別会計は直ちに廃止すべきである.特に社会資本整備関連の特別会計を真っ先に廃止すべき. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考 | 1)「財務省HP」 2)「日本を駄目にする税金のカラクリ」平野拓也著.日経ビジネス人文庫 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||