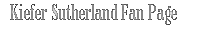プレミア
author Rinz
今年の夏はいつも以上に暑いらしい。地元の労働者からそんな話を聞かされた。確かに服の上からでも全身に突き刺さってくる太陽の熱は、最近過ごした熱さの中でも群を抜いている。それでもジャック・バウアーは空を見上げてうんざりした声を上げたり、暑さについて他の人間と辛さを分かち合ったりする気にはなれなかった。今のジャックにはすれ違う人間も、町角にたたずんでいる人間もすべて信じられない、ロスを出てからずっとそういう生活を送って来たのだ。労働向きのゆったりしたジーンズはかなりくたびれており、太ももあたりの生地が薄くなっていた。汗の滲んだベージュのTシャツの襟や裾もほつれていた。少し長くなった髪の毛は額にかかり、横も後ろの方へ流している。本当は短くしておくのがいいのだが、それでは探している者が一目でジャックだと分かってしまう危険性があった。この髪形はこのあたりの男性には多い髪形である。スコットランド系の顔はこの当たりでも多いから、髪形さえ合わせれば、それほど目立ちはしないのだった。
あれから自分はフランク・フリンという名前で生きている。いつまで自分はこうやって名前を変え、姿を隠していなければならないのか。それはまったく答えのでない疑問だった。なぜなら自分はもう世間的に死んだ人間なのだから。そしてそういうふうにしたのは、娘のキムに危害が及ばないようにする為だ。自分で選んだ道なのだ。ジャックは逃亡生活を送りはじめてからずっとこの2つの事を考え、浮き沈んでいたのである。丁度いい事に、この町には日雇いの労働が何かかしらあった。そして地域的に、中国人の住居者がほとんどいない為、逆に見慣れない東洋人をこちらから見つけやすいのだ。ジャックは久しぶりに押し潰されそうだった恐怖をほんの少しだけ解放させていたのある。
汗だくになった顔をシャツの袖で拭き、ジャックは日雇いの仕事場に近いダイナーのドアを開けた。といっても仕事の中心はほとんどこの近辺だから、週に何回かはこの店を利用していた。あまり地域に顔なじみを作るのはよした方がいいのだが、都会と違い、あまり店は選べないのだから仕方がない。中にはやはり同じように労働を終えた男達が、ぐったりとカウンターやテーブルに両膝をついてコーヒーと、ハンバーガーを食べていた。カウンターの中では、二人の女性がピンク色のミニスカートにひらひらのついたエプロンをして、気だるそうにコーヒーのおかわりに回っている。田舎のウェイトレスなど年齢層が高いのが当たり前だが、このダイナーは比較的まだ若い女性がやっている。といっても20代後半だが。都会の上等のサービスには程遠いが、それでも労働者達は彼女達がやってくると、顔を上げにこりと笑顔を向けた。彼女達もそうされると一瞬笑顔をつくって返している。
「なあ、ディーナ。そろそろ俺との事考えてくれよ?」
窓際のテーブルの客の注文を取ってた1人のウエイトレスに男達がじゃれている。ウエーブのかかった長いブロンドの髪を1つに結び、ピンクのユニフォームから覗く形のいい足の足元にはグリーンのローヒールを履いていた。このディーナというウェイトレスはダイナーでも美人で気のいいウェイトレスである。
「俺との事ぉ?そういう事は捨てて来た奥さんにいいなさい」
口調はぞんざいだが、表情は常に笑顔である。会話を楽しんでいるのだ。
「なんか欲しいものがあったら言えよ」
「そうねえ、ティファニーのネックレスなんてどうかしら?」
「ハイ、フランク」
ディーナはジャックの姿を捕らえると、ウソのない笑顔で声を掛ける。
「ハイ、ディーナ。コーヒーとバーガーを頼むよ」
ジャックはカウンターに肘を付き、ディーナににっこりとほほ笑んでオーダーした後、組んだ手の上に顎を乗せた。ディーナはカウンターに入り、コーヒーを注ぐとそのマグカップをジャックに差し出す。
「はいどうぞ」
「ありがとう」
ジャックはちらりとディーナに視線を向け、マグカップを両手で包み込むように持つ。そんな一見シャイな様子をディーナはうっとりと見ていた。
「もう、あなたを見ていると高校の彼を思い出すわ!」
ジャックがまた顔をあげると、すかさずディーナは顔を覗き込んで来た。
「きっとどこへ行っても女には苦労しないタイプね」
ジャックは声を上げずに笑って、首を振った。
「苦労しっぱなしさ・・・・」
ディーナは片眉と口端を釣り上げて笑った後、腰からくるりとターンすると、他の客のオーダーを取りに行ってしまった。一人になったジャックはまたコーヒーに視線を落とす。しかし体に染み付いた習慣はそう簡単には抜けないものだ。こんな通い慣れたダイナーの中でさえ、不穏な空気というか他と違った雰囲気をとっさに見つけてしまうのである。 右後方の壁際のテーブル。 ジャックは顔を動かさず、目の端に神経を集中させてそちらを見た。三人の男がすでに食事を終えタバコを吸っている。しかし他の客達のように陽気にしゃべったりしてはいない。こそこそと小声で話し、ちらりと視線を店内に巡らせている。
そして今、その視線を自分が浴びている事に気が付いていた。ジャックはなるべく気にしないように見せるため、背中を丸め顔を伏せたのである。
「バーガーよ」
ディーナはテーブルにバーガーをおいた後、コーヒーサーバーを持ってきて、追加に注いだ。
「それでフランク?今まで女でどんな苦労をしてきたの?」
ジャックはバーガーをかじりながら、少しだけおどけた口調で返す。
「とても・・・人前で言えはしないね」
「ううーん、人は見かけによらないって事かしら」
そう言い残してディーナはまた他の客の所へコーヒーを注ぎに行った。ジャックは感心したようにため息をつき首を振る。本当に頭の切れる女性である。それがもしディーナが気がつかないで言っているとしたら、とんでもない宝の持ち腐れだ。ロスのCTUへいた頃は、こういう女性は回りに沢山いたからそれほど気にもしていなかったが、久しぶりにこういう女性に会えた事で何か癒させるのである。だからこのダイナーに、ディーナに会いに通っているのかもしれない。ジャックは少しだけいい気分でバーガーを食べ始めたのだった。
ある小型のジェット機が晴れ渡ったアメリカ国土上空を飛行していた。飛行機の中は普通の旅客機のように整然とシートが並んでいるのではなく、革張りの大きなシートや机が並んでいる。そして仕切られた壁がありその中は簡易オフィスのようになっている。
「到着してまず始めに福祉施設へ向かいます。空港で施設長が迎えに来るはずです。それから別の施設を2つ程見た後、ホテルで記者会見に入る予定になっています」
「記者会見の原稿はもう大筋はできているんだろうね?」
「ええ、今回の訪問についての箇所を除いて、すべてできあがっています」
女性秘書が差し出した原稿に、大きな褐色の手が伸びた。低くよく響くゆったりとした声は、かつて全世界がその言動に注目し、影響を与えたものだ。大きな体で少々いかつい印象だが、その目は非常に愛情にあふれている。強さと優しさを同時に表現できるかつての大統領、デビッド・パーマーは今でも国民からの人気は高い。パーマーとしてもまだまだやれる事があると分かっているし、大統領への返り咲きの道をあきらめたわけではない。今でも以前に力を入れていた労働者や低所得者層への支援活動を続けている。
デビッドの活動範囲は国土全土に及び、今回の町の訪問で貧困層の支援の為の視察は最後だった。この地は他の地域と違い、白人の貧困が集まっている。権力を持った黒人が乗り込むのは少々危ない試みではあったが、デビッドは人種の垣根を越えた、分け隔てない支援をアピールする為には欠かせない場所だと認識していた。
「分かった。それじゃもう1度今回の視察の焦点をまとめてみよう」
そんなデビッドの打ち合わせの横で、彼宛てのメールの整理をしていたウェイン・パーマーは、そんな大統領だった時と変わらないデビッドの物腰や態度を頼もしく思いながら作業をしていた。デビッドより細身だし目も対照的に切れ長で、常に情熱を持った顔をしている青年だ。大統領時代、少々孤立気味になった兄を支え、そして今日に至る。今でもウェインは精力的に人々の中を回り、訴えてゆく兄を見るのが大好きだった。
「ウェイン、ちょっといい?」
入り口から顔を覗かせて、ブルネットの髪をボブにした四十代ぐらいの女性が小声で声を掛けた。ケリー・レインというデビッドのスタッフだ。ウェインはメールツールを閉じるとケリーの側に行った。
「どうした?」
「今事務所から連絡があったんだけど、数日前から事務所のサーバーに一分間に百回の不正アクセスのアタックをされている事に気が付いたそうなの」
最近はどこのネットサーバーでも不正アクセスのアタックなど当たり前のように起きている。ウェインはさほど重要な事ではないと言った口調で聞き返した。 「何か情報を取られたのか?」
「主要なファイルが保存されているサーバーは大丈夫だったようだけど、バックアップが保存されたファイルサーバーはもしかしたら見られているかもしれないって」
「バックアップって何日前の?」
「それはまだ分からないわ」
ウェインはちらりと部屋の中にいるパーマーを見た。その後なにか考えを巡らせるように少し黙り込んだ後、ケリーの顔の前に人差し指を立て、念を押すようなそぶりで指示した。
「とにかく、アタックの送信先を突き止めるのと、情報が盗まれたのか、盗まれたとしたらどんな情報が盗まれたのか、早急に探してくれと伝えてほしい」
「わかりました」
ケリーが行ってしまうのを目で追った後、ウェインはふと心配になって眉を寄せる。アタックももしデビッド・パーマーの事務所のものだと分かってやっていたのだとしたら・・・。何かよくない事があるのではないか。だからと言ってまだ何の証拠もないうちにデビッドに警戒するように伝えるのは早すぎる。それにもし伝えた所でデビッドが日程を取りやめるという事はしないだろう。今までもそういう事が何度もあったからだ。とりあえずウェインは調査の結果を待つ事にしたのだった。
14時30分で仕事が終わったディーナは、早速着替えを済ますと店を出てフランクを探した。 ディーナはずっと前から奥の男たちがフランクを見てこそこそ話しているのに気が付いていた。この町の頭の悪い奴らは子供と一緒で自分より弱そうで、言う事を聞きそうなのを物色して狙うのだ。きっと奴らはフランクを恐喝する気だろう。いつになく真剣な面持ちでディーナは足を速めたのである。
「ハロー、色男」
建物の裏側にある駐車場まで来た時。とうとう男たちがジャックに声を掛けて来た。自分の車まであと少しだったのに、とカギを取り出そうパンツのポケットに手を入れてたままジャックはため息をつき、渋々振り返る。三人の男は親しげな笑顔で近づいて来ていた。不気味である。
「ダイナーでずいぶんディーナと親しげだったよな?俺達もディーナの友人なんだよ」
その割にはディーナと1言も口きいていなかったじゃないか。そう思いながらジャックは黙って三人を見つめていた。しかし見つめていてふと思った。もしかしたらこいつらただのカツアゲヤローか?何かの組織に関わる奴らか、と睨んでいたがどうやら取り越し苦労だったようだ。黙って動かないジャックを、男たちは恐怖で動けなくなっていると思ったのか、警戒もせずに寄りジャックの肩に手を掛けた。
「俺達金がないんだよ。少しばかり都合してくれないか?」
ジャックはフンと鼻で笑う。
「たかる相手を間違えてないか?俺に金があるわけないだろう?」
「俺達は今日の仕事にあぶれたんだよ。ほら早く出せ」
一人の男がナイフを弄び始めた。ジャックの肩に手を掛けている男がくちゃくちゃガムを噛む音が耳に不快に響く。しばらくジャックは三人を順番に見つめていたが、めんどうな事にはならない方がいいと判断し、ポケットに手を入れて今日の賃金を差し出した。
「ほら、これで全部だ」
男たちは喜び勇んで金を引ったくった。そこでやめておけばいいものを、ジャックをやりやすい男と踏んだのか、手を掛けていた男が笑いながらさらに言う。
「こりゃお前の車か?」
車の方へ視線を移している隙に、すっとポケットからキーが抜かれた。
「おい!」
ジャックは声を上げたが男は不快そうに見ただけだ。男はガムを噛みながら余裕の動作でキーを車に差し込み、ドアを開けた。そして車の中を物色し始める。暑さのせいでどうでもよくなっていたジャックは、成り行きにまかせるつもりでいた。しかし、男が車のダッシュボードに入れていたジャックの手帳を見つけたのを見た時、ジャックは顔色を変えた。
「それはだめだ!」
手帳には唯一自分の身分を証明するもの、家族の写真が入っているのだ。ジャックが手を伸ばして奪い返そうとすると、二人の男がジャックを後ろから拘束した。
「へえ、よっぽど大事なもんが入っているんだな」
そう言って手帳を開こうとした時。男の腹に強烈なキックがヒットした。ジャックが体を延ばし、足を振り上げたのだ。手帳を持った男は唸ったまま、くの字に体を折り曲げ後ろへよろめいた。それからジャックはそのままの反動で、自分を押さえていた男の顎にひじ鉄を食らわせこれも引きはがす。後ろで見ていたナイフを持った男は、それを見て慌ててジャックにナイフを突き付けようとした。ジャックは突っ込んで来た男を半身で避けナイフを持つ腕を掴むと、そのままねじり上げた。
「くそ!離しやがれ」
「いいぜ」
ジャックは涼しい顔のままそう答えると捩った手首を両手で持ち、その態勢のまま勢いをつけて押し出したのである。悲鳴をあげた男はナイフをぽろりと地面に落とし、よく見るとその手首は変な方向を向いたままだった。
態勢を直した二人の男も怒り狂ってジャックの方へと拳を振り上げて突っ込んで来る。ジャックのガードは強固でむちゃくちゃなパンチなどあっさりとかわし、かわりに鋭いパンチが男のボディに突き刺さる。男の手から手帳が弧を描いて宙を飛び、地面を滑って行った。もう一人もジャックの襟首を掴んだものの、体を捻り倒された。まともに腰から落ちた男はうめいて起き上がれなくなってしまった。 ジャックは三人がもう動けなくなった事を確認し、大きくため息をついた。手帳を探して顔を地面に向け手帳が結構遠くまで飛んで行った事に気づき、ゆっくりとそちらへ向かった。が、その前に手帳に歩み寄り、それを取り上げた人物がいたのである。シンプルな黒いワンピースは見覚えがないが、グリーンのローヒールに見覚えがある。手帳を取り上げ身を起こしたのはダイナーのウエイトレス、ディーナだった。ジャックははっとして足を止めた。ディーナも気まずそうにジャックの方をちらりと見、軽く手を上げる。
「あの人達、よくお店で恐喝できそうな人を探してるの。あなたの事見てたから心配で・・・・・全然問題なかった見たいだけど」
あはは、と無理やり笑う。一方ジャックは無表情でディーナに近付くと手帳を返せと言うように手を出した。ディーナはジャックの顔をまともに見れず、うつむき加減で手帳をその手に渡した。ジャックは何かディーナに言おうか考えたが、やめる事にした。きっと混乱しているだろう。それなりに人畜無害にふるまっていた男が、三人の男達を一気に殴り倒したのだから。これからはもう少し悪ぶって置いた方がいいかもしれないな、と反省をしてみる。その方がこういう場面に遭遇した時ギャップがない事だろう。ジャックは何も言わずにディーナから離れ車へ向かった。ディーナはジャックが離れて行くのを察し、はっと顔を上げた。 ディーナはジャックが車のキーを取られた所から見ていた。車を物色され手帳を見つけられた時、押さえ付けられたジャックを見て出て行こうと足を踏み出した。その直後である。ジャックの表情が一変し、温和そうな顔にすごみが増した。そして押さえ付けられた態勢からかなり重いキックがヒットしたのである。その後はあっと言う間だった。ディーナはすぐにジャックの動きがちゃんとした訓練を受けたものだと分かったのである。この町にはいろんな事情を持った人間が集まって来る。過去を捨てたか、捨てなければならないか、それとも何かから逃げているとか。それを詮索されないからこそ、みんなここへやってくるのだ。きっとこの男もその通りの男だろう。それでも・・・ディーナはさっきのジャックの姿を見て心が動いていたのだ。彼の能力は自分の目的に使える。自分がウエイトレスとして働いていたのはもちろん金の為ではない。ダイナーという場所はいろんな男を見るのにうってつけだった。ジャックのように何かしらの訓練を受けた男も見てきた。しかし、人格的に問題があったりして、見極めるのに時間がかかり、結局だめだったりという事ばかりだった。しかし自分にはもう他を探す時間はない。ディーナは直感を信じた。この男は大丈夫だ。それはディーナ自身の本当の姿を見せなければならない事でもあった。
「フランク!」
ジャックはぴたりと足を止めた後、ゆっくりとディーナを振り返った。何か思い詰めたような、縋るような表情で自分を見ている。ジャックは、それがやっかいな事に巻き込まれる前兆だととっさに感じ取った。
「私に力を貸してほしいの」
ジャックは自分に向けて、ふんと鼻で笑う。
「悪いが俺は何もできないよ」
「1万ドル払うわ」
のらりくらりと逃げようと決めていたジャックの表情が驚きで固まった。1万ドルだって!?まさかダイナーのウェイトレスからそんな言葉が出るとは思わず、ジャックはいぶかしげにディーナを見つめていた。ディーナの顔や態度は何1つ変化しておらず、そういうならず者を金で釣る行為には慣れている感がある。ジャックはわざと頭の悪い男の様に振る舞った。
「どういう意味だ?」
ディーナは両手を組んで、挑発的にジャックを見る。
「私はあなたのその・・・・彼らをやっつけたその腕を借りたいの。今日一日でいいわ」
ジャックはにやりと笑う。
「うっとうしく付きまとう男を追っ払うんだったら、相当やばい相手だな。それとも相当の人数か?」
ディーナもふふっと笑う。とてもアンバランスな笑いだ。身なりはダイナーのウエイトレス、しかしその立ち振る舞いはスキがない。
「そうね、相当やっかいで相当の人数かしら。今日一日・・・いいえ、いまから四時間でもいいわ。終わったらすぐにお金を渡すから、どこへ行ってもいい、本当よ」
ディーナはじっとジャックを見つめる。ジャックもその視線を受け止め続けた。ジャックはうなじに何か虫が這い回るようなざわざわ感を感じていた。好きな感覚ではないが、今までいろんな場面で感じた感覚でもあった。これは危険だと告げるシグナルなのだ。ただし、普通の人間が逃げ出す所をジャックは向かって行きたくなる性分だった。今ジャックが格闘している理由はただ1つ、自分は身を隠している所なのだ。ややこしい事に巻き込まれたら、今日までの苦労が無駄になる可能性もある。ジャックはもう一度ディーナを見た。ディーナはそれ以上何も言わずに、ジャックがイエスかノーか答えるのを待ち続けている。彼女は相当賢い、きっと男のタイプによってこの交渉術も変わるのだろう。金の金額を釣り上るか、色を仕掛けるか・・・。とにかく人の本質を見抜く目も持っているようだ。だからジャックにはシンプルな条件を突き付けるだけの交渉にしたのだろう。金や女の色に簡単になびくタイプではない。この男を動かすのは興味がすべてだ、と感じ取ったのだろう。ジャックはまったく動じない彼女を見て、その興味の部分を突き動かされていた。彼女の事をすごく知りたくなってしまったのだ。一体このダイナーのアイドルウェイトレスが何者で、一体何をしようとしているのか。ジャックの心の奥に押し込めていたスリルを求める感覚と、それを乗り切るために使うリズムの早い脳波にスイッチが入った。
ディーナはじっと見つめていたジャックの表情が変わった事に気が付いた。もし今までの陰はあるが害はなさそうなフランク・フリンがこの男の演技だとしたら、アカデミー賞ものの名優だ。いつも足元ばかりに視線を落としていた体が、ゆっくりと伸ばされた。くっと吊り上がった口端、何を見るにもうつろだった目はとてつもない眼力をみるみる湛え、ディーナは心持ち後ろへ下がってしまったほどだ。今のこの男だったら襲って来た二人をやっつけたって不思議はない。
「いいぜ、4時間で1万ドルだな?やばいと思ったら抜けさせてもらう。それでもいいな」
ディーナは両手を解くと、みるみるうれしそうな笑顔になった。それは普通の女性が普通に彼氏と仲直りをした時のような無邪気な顔だった。
「いいわ」
ディーナはジャックの脇を擦り抜け、車のドアを閉めてキーをキーを抜く。
「家に戻ってゆっくりしてからって言ってあげたいけどだめなの。すぐに一緒に来て」
ディーナはそう言うと、先頭に立って歩き出した。ジャックは知られないように深くため息をもらすと、ディーナの後について行ったのだった。
ディーナはそれから一度も振り返らず、先を歩き続けた。ダイナーからそれほど離れていない閑散とした住宅街は、空き地が多く歩道と車道の間のガードには、ゴミ袋がひっかかっていたりする。風が吹く度に埃が舞い上がる中、色あせた家の前の洗濯物が長いロープに連なってはためいていた。ディーナはそこから人の家の間を抜ける小道を通り、日当たりのないクリーム色の平屋の家に向かって行った。その家の外装はヒビだらけで、窓も砂埃で中が見えなくなっている有様だ。ディーナはチラリと来た方向を振り返り、誰もいない事を確かめると、キーを取り出しドアの鍵を開けた。
「ようこそ、我が家へ」
おどけた口調でドアを押さえてジャックを中に入れる。ちょっと笑ってディーナを見た後、ぐるりと中を見渡した。何の変哲もない家だ。居間には普通にTVがありコーヒーテーブルもある。キッチンも女性らしくレースのカーテンが掛けてあり、質素だが清潔な様子だ。
「こっちへ来て」
ディーナはさらに奥にジャックを導く。いぶかしげに着いて行くジャックを背にしてそディーナは裏口へ向かい、キッチン横のドアを開けた。そこにはまた木々に囲まれた細い通路が続き、まるで森の中に隠れて建つ小屋のようなものが見え隠れしている。ディーナは道なりに進み、その小屋までやって来た。
「こっちが本当に招待したい場所だったの」
ドアを開けると、見た目よりも重い感じでゆっくりとドアが開く。そしてその中は・・・。
「君は・・・スパイか何かか?」
ジャックの唖然とした物の言い方がよっぽどおかしかったのか、ディーナはふふっと失笑した。建物はとても頼りない。しかし部屋の中には最新のコンピュータが数台、そして大小の液晶モニターも数種類あった。コンピュータのシステムが稼働しているものもあれば、どこかの防犯カメラの映像が写っているもの。見たことのある国防省の機密情報へのアクセスしているものもある。コンクリート剥き出しの床にはケーブルが縦横無尽に這っており、前からこの場所をアジトにしている訳ではなく、急ごしらえのものだと伺えた。近くにあるテーブルには、プリントアウトした紙や茶封筒に入った書類や写真などが無造作に置いてある。紙にはラインが引かれていたり、黒く塗りつぶされていたりしてある。ジャックはつい無意識にそれを見ようと机の方へ吸い寄せられた。その時である、自分の背後でガチャリとトリガーと引く音がして、後頭部にコツンと冷たい物が当てられた。
「念のためよ。テーブルに両手をついて足を広げなさい」
ディーナは手慣れた様子で片手で銃を握り、ジャックが言うとおりにテーブルに両手をついて足を広げると、その上半身から下半身を無造作に叩き、武器などを持ってない事を確認する。
「いいわ。クリアよ」
トリガーを戻し机の上に銃を置く。一瞬拳銃に目が行ったジャックだが、そ知らぬふりをしてゆっくりと姿勢を戻した。そして半分本心でこう言った。
「いや・・・本当に驚いたよ。何だこれは?どうやらただの町のごろつきをやっつけようとか、強盗をしようとかそういうもんじゃなさそうだな」
「言ったでしょ。そうとうの人数とそうとうにやっかいな相手だって」
と突然、本当に突然机の下から1人の男がひょっこりと現れた。ジャックと目の合ったその男は一瞬驚きで固まった後、わぁ!と声を上げながらあわてて背中に手を回した。思わずジャックも思わず身構えてしまった。
「誰だこの男は!」
「落ち着いて、今日の仕事をしてもらう最後の仲間よ」
それだけ言うと男は緊張を解いた。警戒はしているものの、銃を腰に収め姿勢を正した。
「へえ・・・てことは腕がいいのか?」
ディーナはそうよ、という表情をして2度頷いた。ふーん、と男はジャックを上から下まで眺める。ジャックはなんだかこの男に不快感を覚えなかった。彼はアメリカ人だ。薄茶色のクセのない髪の前髪を上に上げ、日焼けしている丸い顔はしばらくいぶかしげにジャックを眺めていたが、納得して気が済んだのか一転してにっこり笑うと、手を差し出した。その顔は何にでも興味を持ち突っ込みたがる子供のような顔をしている。背もそれほど高くはないから実際の年齢より若く見えているだろう。
「オレはマックだ。よろしく」
「フランクだ」
ジャックもとりあえず笑顔でその手を握り返した。なんなんだ?今までの流れから言って、彼らは何か大きな事をしようとしていると分かるのだが、ディーナにもこのマックという男にもそういう類いの人種、いわゆる自分が長年接して来て、抹殺して行った奴らにある冷酷さや、命を掛けたような切羽詰まったような気負いが薄いような気がする。マックを見る限り、まるで子供がスリルのある遊びに首を突っ込んでしまったようだった。
「それで準備はできた?」
「ああ、ばっちりだ」
そう言うとマックは悪戯っ子のような含み笑いを残して、また机の下に消えていった。ジャックがそこへ近づいてみると、地下へ続く階段がそこにあった。マックの気配が部屋から消えて、またディーナと二人になると、ジャックはディーナの方へ向き直りきっぱり切り出した。
「一体何をさせようって言うんだ?」
「そんな難しい事じゃないわ、きっとあなたにはね。突破しなければならない場所があって、そこに一緒に行ってもらうの。そこには訓練を積んだ人間もいるだろうからその時はあなたの出番よ」
聞けば聞くほど解せない。本当に何をさせようというのだろうか?
「つまり、何かする為の用心棒って事か?」
あまりにも本質をつかない会話にディーナの方がうんざりしたのか、決意したように言い切った。
「とある人物を誘拐するのよ」
「誘拐?」
誘拐するのに相当やっかいで相当な人数という事は、普通の誘拐ではない。一体誰を誘拐すると言うのか。ディーナは1台のコンピュータのモニターの前に行くと、マウスを使ってビデオライブラリの中の1つをクリックした。それは今朝の地元のニュースだった。
「今日、デビット・パーマー元大統領がこの町の経済状態を把握する為、視察に訪れます。パーマー元大統領は辞任後もアメリカの地域格差の解消の為に精力的に各地を訪れていますが、今回はこの為の視察の最終地という事もあり、今後どのような活動をするのか、その発表にも注目が集まってます」
ふっと画像が止まる。ジャックは何も言わずに画面を見ていた、いや何も言えずに見つめていたのだ。ディーナがゆっくりジャックを見返すと、しばらくたってジャックは画面とディーナの間で目を泳がせながら、やっと言った。
「何・・・・、何だって?」
「誘拐するのよ。デビット・パーマー元大統領をね」
ジャックは真っ青になって知らず知らずのうちによろよろと後退りしていたのだった。
飛行機は空港内の外れの方へ着陸して停止した。そしてSPや迎えの車がやって来ると、降ろされたフラップを囲むように止まり、それぞれに人たちも迎えにタラップの周りに集まった。
「ウェイン」
ケリーが他のスタッフとタラップに向かうデビッドの背中を見送っていたウェインに声を潜めて声を掛けて来た。何を言いたいか分かっていたウェインはケリーを人影のない場所へ誘導し、顔を付き合わせた。ケリーは1枚の紙を手にささやくように早口で告げる。
「発信元が特定できたわ。ロシアのサーバーを経由して1件アメリカから発信したアドレスがあったの。ドメインとIPを特定してみたら、場所はワシントン郊外だったわ。それでFBIが住人を調べて、ジョシュ・フランシスコという人物が浮かび上がってきたの・・・」
ケリーはその人物のパスポートの写真を見せた。パスポートはアメリカのものだ、年は25才。スパニッシュ系の青年だった。
「それでこのジョシュ・フランシスコなんだけど」
そう言ってケリーはもう1枚の紙を心配そうな顔で差し出してきた。それはサウスウエストジェットの搭乗記録だった。
「数週間前にこの空港に降りているの。偶然だといいけど・・・」
確かに乗客名簿のケリーが指さす場所にはジョシュ・フランシスコと言う名前がある。日にちは1カ月近く前になっており、すでにここを出ているという可能性もあった。しかしこの流れから言って、何かあるのではないかという不安は拭いされなかった。
「それで、アタックされたコンピュータバックアップには何があった?」
「何があったかまでは分からないけど、バックアップは毎日取られていて、対象はサーバーだから、サーバーに上げてあったファイルとか見られている可能性はあるわ」
という事は今回のスケジュールももしかしたら見られているかもしれないという事か。ウェインは指示を待つケリーの鋭い視線を受けながら、どう対処しようか思案したままだ。ちらりと振り返った窓の外には丁度フラップを降り切ったデビッドが報道陣やカメラのライトを浴びて手を上げている所だった。
何も知らないデビッドは、実に堂々として大統領時代の威厳はそのままだった。
まさかこんな場所でこんな時に、その名前を聞くとは思わなかった。パーマー元大統領の誘拐?つい数十分前までダイナーのウェイトレスだと思っていた女性がそんな大それた事を顔色1つ変えずに言い退けた事にも驚いていた。
一体この女は何者だ?元大統領の誘拐を企てている程だから、政治的な組織の者だろうか?ジャックのディーナを見る目が険しくなった。しかし同時に今パーマー誘拐というこの企てに参加したら、必ずどこかで自分の知る人間に自分が生きているという事実が知れてしまう事になるだろう。そうしたら今までの逃走が水の泡だ。ジャックの中で激しい格闘が起こっていた。 そして何かしら結論を出したジャックのその顔は、引きつった笑顔が昇っていた。
「は、はは・・・・冗談だろ?そんな事できる訳がないじゃないか。今は違うと言っても元大統領だ。シークレットサービスもついているし、地元の警備だって万全のはずだぜ。どうやって?どこからあの大男を誘拐できるって言うんだ!?」
ジャックは話にならないと言うように、ふんと鼻で笑い出て行こうとした。どちらにしてもこの件に係わらない方がいい。怖じけづいてしっぽを巻いて逃げたと思われておいた方がいいだろう。まあ、逃げ出せるかどうかは別の話だが・・・。
「できるのよ。じゃなきゃ行きずりのあなたなんかにこんな事言わないわ」
そこへ先程のマックが上に駆け上がってきた。そして二人を楽しそうに見た後、にっと笑い言った。
「待たせたな。主役のご登場だ。驚くぜ」
マックが階段を見ると、ゆっくりだが重々しい靴の音が聞こえて来た。その男はジャックに背を見せ、頭からだんだんとその姿を現してゆく。背格好の大きい黒人男性・・・髪の毛は短く頭の形は丸い。紺色の上等のスーツを着てゆっくりと動くその姿はどこかで見覚えがあった。男が階段を昇りきり、そしてゆったりと二人の方へ振り返る。
「あ・・・」
ジャックはもうそれ以上声が出ない。目の前に立っていたのは、デビッド・パーマーその人だったからだ。デビッドはいつものように目と口元に笑みをたたえ、ジャックを見つめていたのだった。
凛子
シーズン4の終わりとシーズン5の間って、すごく妄想掻き立てられませんか?潜伏中にジャックは何かやっていたんじゃないかと!という訳で、シーズン4.6ぐらいの話で書いてみました。続きは今の所予定なしです(はっはっはー)。どんな話になりますか・・・。ぜひ、ご想像で24シーズン4.6を作ってくださいませ。