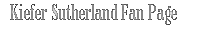
|
カラカラカラっと真後ろから椅子が近づいて来る気配を、背中で察知する今日この頃・・・。 「モーガン先生」 「なんでしょう、スタージェス先生?」 ちらりと目線だけその声の方へ向けると、いつもの情熱的な眼差しが意味深に自分を見つめてきていた。この表情は何かを企んでいるな、とピーター・モーガンは思った。リチャード・スタージェス医師は、この退役軍人記念病院では知らない者はいない名物医師だ。医師仲間や患者からは正義のヒーローとして、逆に上層部からは反逆児として。ピーターとしてはもちろん彼はこの病人のヒーローで腕のいい外科医で、そしていい兄貴分だ。 「今夜あたり、調達に行こうと思うのですが?」 リチャード・スタージェス医師は、まるで重大な話を切り出すかのように、声を抑えまわりに聞こえないようにゆっくりと言う。ピーターは顔を上げずに頷いた。 「じゃ、あとで作戦会議と行きますか?」 大きく手を上げてすーっとリチャードの椅子が自分から離れて行った。自分たちには上層部には言えない、いろいろな「キーワード」があった。「調達」というのもその中の1つだ。それを踏んで、いつもの事だろうとリチャードの顔さえ見なかったピーターの誤算は、戻って行くリチャードの顔ににんまりと笑顔が昇った事を見逃した事だろう。 「で?今回理事長どもはどこに何を隠したんだ?」 「いただくものは、ペースメーカー。場所は2棟の9階の元外科部長室だ」 ・・・・。 突然全員が押し黙ってしまった。黒人医師シド・ハンドルマン医師も一見科学者のような風貌のルビー・ボブリック医師も、その大きな体をかっちりと固めてしまっていた。状況が分からないのはピーターが、眉をひそめて二人を交互に見つめた。「調達」とは、上層部が経費削減と称して配給された医療機器をリチャード達から隠しているのだが、それがどこに隠されているか突き止め、いただきに行く事だ。ま、平たく言えば院内で泥棒をしている訳だ。向こうも向こうで隠し場所をいろいろ考えて来るのだが、事情を知らないピーターからしてみれば、今回は特に工夫されていないように思う。 「その手できたか・・・・奴らも考えたもんだな・・・」 シドは険しい顔で顎を押さえた。ルビーもうーんとうなってのけぞってしまった。ピーターは理由が分からずその冷め切った空気の中、全員を見渡す。 「どうしたんだよ?9階なら地下の霊安室より逃げ場も多いし、取って来やすいじゃないか?」 シドもルビーは無言で首を振る。解せない顔でもう一度リチャードに顔を向けると、リチャードもまた顔がこわばっていた。 「お前はまだ新人だから知らないかも知れないが、2棟の9階の元外科部長室がどうして今は使われていないかって言うと・・・・」 「あそこは出るんだよ・・・・。幽霊が」 リチャードが声を潜めて言った言葉に、シドが強面の顔をピーターに近づけて言ってきた。しばし固まってしまったピーターだが、やっと2度ほど瞬きをした後、無理やり口を横に開いて笑った。 「は、ははは。本気で言ってるのか?おかしいぜ、そういうのって病院にはよくある話だろう?」 そころが誰よりもその言葉に反応したのは、意外にもリチャードだった。 「いいや、あの2棟の9階の元外科部長室は本物だ!なぜならオレも見た!」 神妙な顔でそういい切ったリチャードをピーターはまた凝視した。もともとリチャード・スタージェスの目はかなり怖い。彼を見ると犬というより狼を想像してしまう。それが下から睨みあげるように自分を凝視し、恐ろしげな表情をしているのだから、ピーターごときが逃げられるものではないのだ。リチャードはゆっくりと低い声で話始めた。 「まずあの部屋で起こった惨事の噂を話さないといけないな。 十年前あの部屋にいた外科部長っていうのは、傲慢チキで患者を実験台としか思っておらず、賄賂も受け取るような極悪医者だったそうだ。ある日彼の医療ミスのせいで片手を切り落とすハメになった退役軍人が、彼の所へ乗り込んで来て、持っていた大型の拳銃でいきなりその外科部長の頭をふっ飛ばした。外科部長は多分何が起こったのかも理解するまもなく即死したはずだ。それからだよ・・・」 リチャードの目がもう1段据わった。ピーターは思わず身を後ろへ引く。話の怖さよりスタージェスの凄みに青ざめ始めていた。 「ある日、ナースが夜中見回りに行くと、その部屋の中から誰から歩き回る靴の音が聞こえてきたそうだ。あの時以来閉鎖になっていた場所だから、変だなぁって思って、そっとドアを開けてみると・・・・部屋の中には白衣を着た男性が、入り口に背を向けて机に覆いかぶさるように噛り付いて書類を見ていたんだそうだ。彼女が入ってきた気配に気がつくと、その男は体を起こしてこう言った。 『すまないが書類がよく見えないんだ。君読んでもらえないか?』 そして振り向いた姿は、正面の白衣は血だらけで、首から上の頭がなかったんだ!」 「ぎゃぁぁぁぁぁ!」 と大声を出してのけぞったのはルビーだった。大きな体が倒れたものだから、それなりに恐怖を覚えていたシドを巻き込んで椅子ごとひっくり返った、その影響で回りに立てかけられていた物までも、大きな音を立てて崩れる。ワタワタしながらなんとか元に戻ったシドが苦々しそうに言う。 「おいー、知ってるお前がなんでピーターより怖がるんだよ」 シドに椅子ごと立て直されながら立ち上がったルビーの目じりには涙がちょちょ切れている。 「な・・・・何度聞いても怖いもんは怖いんだよ!」 ピーターを見るとさほど様子も変わらずスタージェスを見つめたままだ。もっと怖がったのを想像していただけにスタージェスは一瞬残念そうな顔をした。 「で、これはオレの場合だ。そういう噂があるって聞いた後宿直してた時に、緊急処置をする為にその部屋の階の手術室へ向かったんだ。そしたら、向こうの方から白衣姿の医師が歩いてきて、通り過ぎる時に「すまないね、私では無理だ」って声がして振り返ったら誰もいなかったんだよ。後で考えたらおかしいだろ?宿直で病院にいたのはオレ1人だったんだぜ」 リチャードの話だけでも凄く怖い!ピーターも青ざめるぐらいしているかとも思ったが、まったく表情。そして話が終わると、軽く眉毛を吊り上げた。 「話としては、上出来だね」 「信じないのか?」 いささかムっとした顔でリチャードはピーターを見た。ピーターは余裕たっぷりに言った。 「そんなの信じてたら、医者なんてできないさ」 ふん、と鼻で笑ったピーターだったが、リチャードはピーターが汗ばんだ手のひらを膝で拭うのを見逃さなかった。内心にやりとするリチャード。その表情を隠して怒ったような声で二人を見た。 「よーし、分かった!シス、ルビーお前ら信じるよな?」 「当たり前だよ」 「あれは嘘じゃないぜ」 シスもルビーもコクコク首を上下に振って頷く。リチャードはキッとピーターを睨みつけると、体育会系ばりの威勢で言い放った。 「ピーター!今回はお前一人で行ってこい」 「ええ!」 思わず大声を出したピーター。そこでとうとう化けの皮がはがれてしまった。真っ青になって額に汗が光る。リチャード達はピーターに口を挟ませないようにそれぞれがまくし立てた。 「大丈夫、大丈夫!俺たちも同じ階までは行くから、お前が出てくるまでは待っててやる!」 「持ち出した物品運搬は俺たちに任せろ!」 3人が3人すごい迫力でピーターに迫る。椅子にぴったり張り付く格好で追い詰められたピーターは、頷くしかなかった。 「あ・・・ああ、分かったよ。1人でその元外科部長の部屋に入ってペースメーカーを取ってくればいいんだろ?簡単さ」 2棟の9階の元外科部長室前の廊下。ただ今、真夜中1時20分。 手術室と使われていない部屋しかないこの階は、普段廊下の電気も消えていた。警備員の見回りも3時間ごとで、ついさっき警備員が姿を消したのを確認したから、これで誰も来る事はない。ピーターは一歩踏み出して、ちらりと後ろを振り返る。三人は角から頭だけを突き出して、早く行けと手を振ったり、親指を立ててグッドラックと言ったりしてピーターをはやし立てている。廊下へ目を戻したピーターは腕を上げて、持っていた懐中電灯で奥を照らしてみた。すっと光が広がって奥の方で拡散する。光の届かない奥の方は、どこまでも続いていそうな暗闇が広がっている。今にもそこから足のない○×■な人達がそろりそろりと出てきそうな気がした。ピーターは思わずゴクリと唾を飲み、背中にはサーっと寒いものが降りて行った。 実の所・・・ピーターはめちゃめちゃ怖がっていたのだ。本当に冗談だろうと思う反面、リチャードの話は生々しかった!それに、もしあれが本当の話で、ドアを開けたら首のない△○▽がいたら・・・・・。その前に廊下で誰かにすれ違ったら・・・・。とりあえず今、ぶっ倒れもせず、逃げ出してもいない理由は、怖くなんかないぜ、と言ってしまった手前、ここで彼らに泣きつく訳にはいかないと言うプライドがあるからだ。同じ意味でピーターはもう後ろを振り返る訳にもいかない。なぜなら後ろには行動を固唾を呑んで見つめるリチャード達がいるからだ。ピーターは気付かれないように息を吸い込むと、意を決してここから一番奥にある元外科部長室へ歩き出した。 一方リチャード、シド、ルビーは、頭だけを突き出して出して、奥へと進むピーターの背中を追った。カツン、カツンと革靴の踵の音が響き渡り、それが遠くなるのと同時にピーターの白い背中が闇の中へ溶け込んでゆく。もちろん見ている方も多少恐怖心はあった。しかし三人にはもっと重大な作業が待っている。ピーターが声の届かない所まで離れたのを見計らってルビーが顔を歪めた。 「もっとピーターの奴ビクビクするかって思ったけど、かなり冷静だよな・・・。面白くねえ」 ピーターのその冷静な足音と振り向きもしない背中に舌打ちをする。しかしリチャードマジメな顔で首を振った。 「いいや、ああ見えて結構内心穏やかじゃないはずだ。オレには分かる。だって恋人が診療内科医だからな」 こんな所でのろけなくても・・・と二人は思った。シドは笑いながら、リチャードを見た。 「それにしても、今回のお前の作り話は本当に怖かったぜ」 これにはリチャードもニヤリとした。 「まぁ、おんなじ手口で毎回インターン達を震え上がらせてりゃ、話の完成度も高くなるさ」 今回の外科部長の話はでっち上げ、医療機器の調達もウソ。最初からピーターを脅かす為だけの作戦だったのだ。ただこの話は、院内のよくある怖い噂の1つで、リチャード達が赴任する以前からどこかの話として存在する事だけは確かだった。夜勤をこなすようになり、多少鼻っ柱の強くなったインターンをとっちめる為、リチャード達がしばしば使っていた手だ。しかし、ピーターはインターンと言っても3人のちゃんとした仲間。なのになんでこんな事をたくらんだかというと・・・・最近面白い事がないからだ。ただ、この2棟の9階は初めて使うシチュエーションだ。インターンだとここまで夜中に来ることなんて、ほとんどないからだ。 「しっかし、ここなかなか怖いよな。あそこの外科部長室は確かに今は誰もいないし・・・そういえば、なんであの部屋使われなくなったんだろうな・・・?」 「さあな、きっと経費節減だろ。俺達が来る前からもう使われなくなってたよな?」 リチャードはピーターが外科部長の部屋の前に立ち止まったのを見て、もって来たカードからジェラルミンケースを引っ張りだしてきた。二人もそれぞれ両手で持てる程の荷物を抱えた。 「でも今回はお前の体験談まででっち上げた所まであって、あれも怖かったよなー」 荷物を持ってまた廊下を覗くと、ピーターがその部屋のドアに手を掛けた所だった。シドはリチャードの話を思い出し、笑い出すのをこらえながら言った。 「いや、あれは本当だ」 サラリと言うリチャードに、シドとルビーは固まってしまった。そして恐る恐るリチャードの方に目を向ける。 「・・・・どこで?」 「ここだよ。でも安心しろ、夜中の話じゃなく早朝の話だ」 ピーターが例の部屋に入って行くのを見届けたリチャードはポンと二人の背中を叩いた。 「さ、こっちも奇襲作戦開始だ、行くぞ」 中腰のまま廊下へ飛び出すリチャードの背中を、青くなって固まってしまった二人はしばらく見つめ合い、お互いの背中を押し合いながらリチャードの後へと続いたのである。 古いドアは、かなりスムーズに開いた。長年使われていない部屋にしては、特に傷みなどもなさそうだ。部屋は真っ暗で何も見えない。特にあやしい光とかも・・・・なさそうだ。ピーターは他の部屋の記憶を頼りに部屋の照明スイッチを探した。しかし、カチリと音はしたものの、部屋は真っ暗なままだった。 「やれやれ・・・・」 ピーターは懐中電灯で部屋の中を照らす。部屋は取り立てて違った様子はない。他の管理層の部屋の作りと代わり映えもしない。大きな机の奥が窓にあり、ぴったりとブラインドウが閉められていた。机の上に明かりを照らすと、書類やペン立て、そのペン立てに収まっている筆記用具など、今でもこの部屋は使われているのではないかという雰囲気がある。しかしよく見ると、その上はうっすらと埃が被っていて、長い間誰も使っていない事が分かる。ピーターは今度は部屋の壁に明かりを向けてみた。やはりなんの変哲もない机と同じ茶色の棚が並んでいる。 まぁ・・・隠すとすれば。ピーターはその棚の扉を開けた。ペースメーカー5箱。確かにそこに入っていた。ピーターはほっとしてその箱に手を伸ばし、1つ、2つ・・・と取ってゆき、3つ目に手を伸ばした時。ふっと誰かの手が、手を伸ばした自分の手の上に乗ってきた。ピーターは凍りついたのか、しばらくその自分の手をつかんでいる手を見つめてしまった。懐中電灯でぼんやりと照らされたそれは、とても青白いし、ふやけたような感触だ。それに、この手はどう見ても棚の奥から伸びているような・・・棚の向こうは壁だったんじゃないか・・・・それにこの手とても冷たいし・・・・ 「わ・・・・わぁぁぁ!」 そこまで考えて我に返ったピーターは叫んでみたものの、手を引っ込められず重なった冷たい手を見ながら腰だけ引けていた。やっと手を引き抜く事を思いつき、手を自分の方へ引っ込めると、その手はすがるように自分の方へ手のひらを見せてきている。 よろよろと後ろへ下がった時、今度はどんと何かにあたった。いやーな、予感がする。だってさっきここには何もなかったゾ・・・。ピーターはゆっくりとその足元を見下ろした。案の定、そこには白衣を着てだらりと手を下ろした人が立っていた。そしてその感触は冷たくて・・・・硬い。 「プリーズ・・・・」 低ーい声がピーターの耳元で囁いた。もう限界だ・・・・。 「ひえぇぇ・・・・!!!」 顔を上げる事さえ出来なかった。ピーターは両手を床につけ、這ったまま出口を目指した。が、やっとたどり着いたドアは、入ってきた時と違いノブを回しても、押しても引いてもびくともしない。 「リチャード!シド!ルビー!!!!た、助けてくれー!!!」 バンバンドアを叩いて必死に叫ぶピーター・・・・。 クックック・・・・ どこからともなく、押し殺した笑い声がした。そして次の瞬間・・・・ 「はははは!」 大爆笑が響く・・・・聞き覚えのあるその笑い声、ここでピーターはやっと状況が飲み込めた。 「お前ら・・・・」 パッと電気が着く、まずピーターは目の前の白衣の幽霊を見上げた。幽霊だと思われたのは白衣を着て頭を取ったマネキンだった。台車に乗せ、その台車の後方には棒が付いて延びており、クローゼットの中からルビーがそれを操っていたのだ。ルビーは腹を抱えて笑っている。そしてピーターが叩いていた入り口のドアが開いた。見上げるとシドとリチャードが立っていた。立っていたシドはドアを押さえていたらしい。そして青白くペイントをした手術用の薄い手袋をしたリチャードがゲラゲラ笑ってピーターを見ていた。 「おやおやー、モーガン先生。どうしたんですか?幽霊にも遭遇しちゃったみたいな顔して」 何も言う元気もなく動く元気もないピーターは、ただただ恨めしそうな顔で睨み付けるばかりだ。 「リチャード・・・・なんであんな所から手を出せたんだ?」 我ながらピント外れの問いかけだな、とは思ったが、不思議に思ったのだから仕方がない。リチャードはニヤリと笑うと手を出していた棚に近づいた。 「この隣はこっちと同じで使われなくなった手術室なんだが、ここに通気溝が通っててな、取り外すと繋がるんだよ。変な構造だろう?」 そう言って今度は逆にこっちから向こうに手を突っ込んだ。 「で?どうしてオレがスイッチ入れた時は電気がつかなかったのに、今はついているんだ?」 「ブレーカーを落としておいただけだよ。使われていないんだから、誰も気がつかない」 それはシドが両手をあげて答えた。 「そんなに新人いじめで楽しむ奴らだとは思わなかったよ」 「いじめじゃない。ただ楽しんでいるだけだ」 やっと体に力がみなぎって来だしたピーターは、ふうとため息をついて立ち上がろうとした。笑っていたリチャードが手を差し出して、ピーターを助け起こそうとした時・・・・ パッと電気が消えた。 「え?」 そう言ったのはリチャードだった。思わず三人の目がリチャードに向く。付けっぱなしで放っておいた懐中電灯で、わずかに部屋が薄暗い状態だ。ピーターはすっかり落ち着きを取り戻し、もうだまされない、と強い口調で言う。 「え?ってもうしらじらしいぞ」 しかし今度は本当にリチャードに心当たりがないようだ。 「シド。もしかして今度は本当にブレーカーが落ちたんじゃないのか?」 「ああ、ちょっと見てくるよ」 とドアに手を掛けたシド。 「あれ?」 あれって・・・・。 「どうした?」 「ドアが開かない・・・」 ピーターの怒りはとうとう頂点に達した。 「いい加減にしろよ!」 そう怒鳴った次の瞬間。突然ガタンッと大きな音をたてて窓が開いたかと思うと、ブラインドウがまるで大きな鳥達が一斉に飛び立ったような音を立てて内側へなびき、突風が机の上の書類を巻き上げた。ルビーの顔に紙が張り付いて後ろへ飛んで行ったが、唖然とした顔は全く変わらない。ピーターはもうすでに泣きそうな顔で部屋の隅に張り付いていた。 そして・・・・ 「君たち、人の部屋に入ってきて一体何を騒いでいるのかね?」 全員顔を見合わせる・・・。だって、声は机の向こうの方から聞こえてきたような。 「ここは私のオフィスだ。君達が騒ぐような場所ではない」 その声はとても冷ややかでそして完璧なイングランドなまりだった。この仲間の誰1人、イギリス英語を話せる者などいない。4人は意を決すると、そろりそろりと机の方へ目を向けた。 「!・・・・・」 ピーターは恐怖で涙目になってあんぐりと口を空けたまま呆然としている。そしてシドもルビーも恐怖で引きつった。そしてリチャードは・・・ 「お前、誰?」 疑念の表情を浮かべたまま、リチャードは平然と言ってのけた。 「私はこの部屋を使っている外科部長だが」 げ、外科部長って。じゃ、あの話は本当だったのか。ただ1つ違う事がある。その外科部長と名乗る男にはちゃんと頭がついていた。面長で蒼白、ブラウンの瞳と高い鼻を持った壮年の医師が、少々気分を害したような表情を浮かべこちらを見ている。つまりリチャードが落ち着いていられる思考はこうだ。 噂では頭がなく血だらけの外科部長をイメージ・・・相当怖い。 でも目の前に突然現れた幽霊らしき医師・・・・なんだ頭あるし普通じゃねえか。 という事で、よく見るとその体が透けていようがなんだろうが、すっかり恐怖が吹っ飛んだのである。リチャードはすくっと立ち上がり、そして挑発するように机の上に腰を降ろした。そして自慢の狼のような風貌でその幽霊を睨み上げたのである。幽霊医師の顔がますます険悪になった。 「君!」 ふだんから高圧的に出られると、反抗したくなるリチャードだ。しかし今回ばかりは全員が目を見張る。相手は幽霊なんだぞ!ポルターガイストとか起こして部屋の中がめちゃくちゃになっちゃうかもしれないんだぞ!頼むから幽霊を怒らせないでくれ!しかしすっかり肝の座ったリチャードは、まじまじと相手を見つめていた。 「ここの外科部長は死んだって聞いてるぜ。それにあんた自分が透けているってのに気が付かないのか」 「リ、リチャード!」 恐怖で声が引っ繰り返るピーター。するとその幽霊はゆっくりと頷いたのだ。 「もちろん分かっているさ。さあ、だから机から降りなさい」 高圧的だが穏やかにたしなめられ、さすがのリチャードも静かにそれに従った。不思議な事だが、他のみんなもこの医師が幽霊ではなく、普通の医者にだんだん見えて来だした。ピーターを除いてだが・・・。 「さて、まず訪ねよう。君達はこの部屋で何をしていたのかね」 ちらりとシドとルビーが目配せをした。それでも幽霊と会話する度胸があり、それに答えられたのはリチャードだけだ。 「院内の幽霊の噂を持ち出して、ピーターをちょっと脅かしてやろうと・・・」 リチャードが視線をピーターに投げると、その幽霊医者もつられて視線をピーターに向ける。と、幽霊と目が合ったピーターの顔がさっと真っ青になり、そのまま口をパクパクさせたと思うと無言でばったりと後ろに引っ繰り返ってしまったのだった。 「・・・こいつはこれでも医者か?」 呆れ返ったような幽霊の声に、リチャードはぶっと思わず吹き出してしまった。幽霊にまでバカにされている。 そこで幽霊医師が、口調を変えて言ってきた。 「私の部屋で騒いでいた事を許す代わりに、頼みたい事があるのだが」 リチャードはいぶかしげに幽霊を見つめる。 「幽霊が?俺達に頼み事?」 「幽霊だからなんでもできると思っているかもしれないが、できない事もある」 幽霊医者はぐるりと全員を見渡した。リチャード以外の人間は目が合わないように自然と下を向いてしまう。 「ふん・・・・最初はお前にしようと思ってたんだが」 そう言ってリチャードを見た幽霊。 「?」 そして気絶しているピーターに目を止めた。 「あいつを借りるとしよう」 「え?」 すっと幽霊医者が消えた。そしてしばらく静けさが支配していたが、そこにピーターがむくりと起きてきた。リチャードはさきほどの幽霊医者の言葉が気になったリチャードは、恐る恐る声を掛けた。 「ピ、ピーター」 ピーターは苦々しそうに額を押さえてふうっとため息をつく。 「いい忘れていたが・・・・」 いつもはソフトな口調のピーターだが、今は低く鋭い物言いに変わっている。 「私の名前はライアン・フリーだ」 言葉遣いはイングランド訛りになっている・・・。ただの新人洗礼の肝試しがとんでもない事になりそうだ。そしてピーター(?)がとても満足そうにその体を見た後、頷いた。 「さて、まずこれで1つクリアだな」 「おいおい!クリアじゃねえよ。ピーターの体を勝手に乗っ取るな!他の奴にしろよ」 リチャードが慌てて言うが、ピーターを乗っ取ったライアン・フリーは片手を挙げて制すだけだ。 「安心しろ、この体は目的達成したら返すさ。それに他の奴がここにくる事なんてほとんどないからな。お前達みたいなやんちゃな医者がこの病院にいるとは思えない。そうだろう?」 ピーターの顔でイングランド訛りのてきぱきした話し方は、みょーに違和感がある。 「分かったよ。で、何がしたいんだ?」 「明日休みの者は?」 スタージェスが頷いた。 「オレ休みだけど?」 「そうかそれはよかった。では明日私と一緒に行動してくれ」 「は?」 ピーターの顔をしたフリー医者はとてもうれしそうにほほ笑んだ。 「妻を迎えに行きたいんだ」 リチャードは車を運転しながら、隣の助手席に座るピーターを見た。そして大きくため息をつく。あれから何とかあの場所から宿舎へ戻り、さすがにピーターに起こったあれは夢か何かで明日になれば何事もなかったって事になるだろうと思っていた。いや自分に言い聞かせていた。が、今朝ピーターがリチャードの部屋の前に来ていたのだ。完璧なイングランド訛りで、 「おはよう、スタージェス君」 と言って。いつものピーターだったら髪も下ろしたまんまで、シャツの襟も開けている。それに休日なのだから、擦り切れたジーパンにスニーカー姿だろう。しかし、ライアンという医師がとりついているピーターは髪を7:3に分けきっちりとオールバックだ。Yシャツのボタンは上まできっちりと締め、裾もスラックスの中にきれいに収まっている。そして穏やかな笑顔を浮かべて、背筋をぴっと伸ばし、後ろ手に組んでいた。 起き抜けでボッサボサの頭で半分ずり落ちているナイトガウンの前を掻き合わせた姿で出てきたリチャードに、ピーターはすっと視線を逸らして咳払いをした。リチャードの方は一瞬ピーターがどうかなってしまったかとポカンと見つめてしまったが、昨夜すでにどうにかなってしまっていた事を思い出して、がっくりと肩を落としたのだった。 「しかし、よくピーターの休暇が認められたな」 リチャードは休暇でも同科の医師が二人も休むなんてとんでもない事だ。あの鬼婦長が許すわけがない、とリチャードは思っていた。ピーターの顔でライアンはちょっと首を傾げてそれに答える。 「最初は『甘えた事言ってるんじゃないわよ!』って怒鳴られたのだが、しばらく話していたら急に態度が変わって、『少し休まれた方がいいかもしれませんね』ってすんなり認められたのだ」 そりゃかなりピーターらしからぬ発言を繰り返して婦長はピーターの頭がおかしくなってしまった、って思ったんだろうな。リチャードは笑いをこらえて唇を噛む。しかし時間が経つにつれて、このイングランド訛りで振る舞いもきちっとしているピーター・モーガンというのもおもしろいな、と思えるようになってきた。 「あのさ・・・」 「なんだい?」 なんだい?って気取って言われてもなぁ。 「あんたは・・・」 「スタージェス君。私の名前はライアンだ」 「イエスサー、ライアン先生。先生はいつから病院に?」 「ベトナム戦争が終わって、この病院ができた時に入ったよ」 てことは30年以上前か?生きていたらじいさん先生だ。 「奥さんとはいつから会ってないんだ?」 「つい一カ月前だ」 そんなの死んでる可能性が高いじゃないか。おいおい、幽霊が取り付いたピーター・モーガンと一緒に30年前に死んだ医者の家を探しに行こうってのか!勘弁してほしいぜ。 リチャードはそれを伝えようと、ピーターの方を見る。ピーターはきっちりとシートベルトを締め、背筋をピンと伸ばして上面を見つめていた。そしてその表情は、ピーターとは思えない顔。長年連れ添った愛しい妻に会える、それはそれは穏やかな落ち着いた笑顔を浮かべていたのだ。 「ぶっ!」 もうたまんねえとばかりにリチャードは吹き出した。 「なんだ?」 ピーターはケタケタ笑い出したリチャードを少々気分を害されたという顔で睨みつけていた。 「すまん・・・・ピーターの20年後の姿を見た気がしたんだよ」 リチャードはピーターの指示を受けながら運転し、住宅街へと入った。確かにその辺りの住宅は古い家が多い。 「ここだ」 ピーターがはっとして1件の家を指差した。 「・・・・・残念」 ピーターもゆっくりと手を降ろす。家は確かにあった。1階建てでレンガ作りの庭の広い家だった。庭には木々や草花が植わっていて、季節になれば美しいガーデンが広がるにちがいない。ただしちゃんと手入れされていればの話だ。煉瓦造りの家の窓には本来なら清潔で柔らかいカーテンが下がっているはずだ。しかし窓にはカーテンなどなく、真っ暗な四角い口や目がぽっかりと空いているようだった。壁にはツタが這いずり、家の角をびっしりと覆ってしまっている。そして庭も芝が伸び、石畳に整備された通路にまで侵入していた。決定的なのは、入り口の扉にかけられた「for SALE」の文字。やはりもう誰も住んでいないのだ。 「ふん・・・・そうか」 落ち着き払った声でそういう。その声色にはそれほど落胆した響きはなく、ある程度予想していたという感じだ。 「よし、電話をしたいんだが・・・・」 「あいよ」 リチャードがパンツのポケットからおもむろに携帯を差し出すと、ピーターはけげんな顔をした。 「私は電話をかけたいと言ったんだ」 「先生は知らないかも知れませんがね、今の電話はこんなになっちゃってるんです。ピーターなんてオフタイムになるとどこに行こうがずーっと彼女と喋りっぱなしなんだぜ」 ピーターの目が点になる。それでもこの過去から現在によみがえった医師は、そういう事を受け止められる頭を持っているようだ。 「そうか、では申し訳ないが、今から言う番号に電話をしてくれないか?番号は*************」 言われた通り押して、電話をつなげる。数回コールの後、忙しそうな女性の声がぶっきらぼうに出た。 「ジョージウエスト病院です」 病院?怪訝な顔でピーターを見る。ピーターはピーターで本当に電話が掛かっているのかまじまじとリチャードを見ていた。 「もしもし?」 「あ、ああ。うちのじいさんがここへ電話を掛けてくれっていうから掛けたんだ。ちょっと待って、今じいさんと替わるから。」 そう言って、ピーターに電話を渡すとじいさんと言われた事に少々ムッとしたようだ。リチャードは、いいから早く話せ、と手を振ってゼスチャーする。 「もしもし?」 もう一度電話の向こうの声が問いかけた。 「あー・・・・。わ、私はライアン・フリーという者だが」 「フリーさん?もしかしてメアリー・フリーさんの親戚の方?」 「メアリは私の妻だ。妻はまだ病院にいるかな?」 突然電話の女性が、キャーっと声がを上げ、思わず二人は電話を遠ざけてしまった。 「なんて事なの信じられない!ええ、ええ、彼女はまた病院にいますよ。でももう時間がありません。はやく来てくださいな」 それから何か喚くのを聞き飛ばし、ピーターは電話を切った。 「で、その病院に行くのか?」 ピーターは当たり前とばかりに頷いた。 「その前に、なんでその病院に奥さんがいるって分かってたのに、ここに来たんだよ」 「違う。ジョージウエスト病院は妻が通っていた病院だ。元気でいてくれている事を願ったが、やはり無理だったようだな。 うちの病院は退役軍人専門だろう?だから妻には信頼できる医師のいるあの病院を薦めたんだ」 そうだよな、あんな男臭くって危険な場所に奥さんなんか置いて置けないよ。リチャードは再び車を発進させた。 病院についた二人は早速受け付けに行く。 「電話で問い合わせたメアリ・フリーさんを訪ねたいんですが」 すると受付の中にいた女性がぱっと振り返った。 「ああ、メアリさんの旦那様ね。メアリさんは別館の303のお部屋ですよ」 ピーターはにっこり笑って答えた。 「ありがとう、長い間世話になったね」 そしてさっさと言われた部屋の方へ行ってしまう。どうやら来た事があるらしく場所を聞いただけでピーターはさっさとそちらの方向へ向かっていってしまう。と、追いかけようとしたリチャードを受付の女性が引っ張って引きとめた。 「あの?旦那様ってあの人?電話で話した方は来ていないの?」 どう見たって、二十代のピーター。メアリの妻の筈がない。女性の不審そうな顔で、リチャードは慌てた。 「あー、えーっと。オレはリチャード・スタージェス、退役軍人記念病院で外科医をしているんだ。で、メアリさんの旦那さんの・・・・ライアン、ライアン・フリーさんはうちの病院の患者で、頼まれたんだ。あれは孫・・・っていっても親戚の息子さんなんだけど、ライアンさんの事をよく見舞いに来ていて孫のようなもんだ。で、フリーさんにオレと彼が奥さんを探すように頼まれて・・・・」 リチャードの口からでまかせストーリーは、女性が怪訝な顔をしながらも納得するまで、長々と続いたのだった。 どうにか疑いも晴れ、受付の女性から開放されたリチャードは今度は病棟を見つけるのに苦労した。 別館というのは本当にかなり離れていて、中庭を越え丘を越えると、そこにこじんまりとした白い建物が見つかった。中に入ると医者や看護師の姿もまばらで、その作りは驚くほどゆったりとしている。ここはきっと金持ち用の入院棟だろう。303の病室は最上階の真ん中にあった、リチャードはそっと中を覗くと、そこにはピーターの後姿があった。 ピーターの姿のライアンはカルテを手に取って、パラリパラリとめくって読んでいた。リチャードが中に入って来たのに気が付き、ピーターはそちらを振り向き少し肩を竦める。患者の横に置かれた処置用のテーブルの上にカルテを戻し、ゆっくりと彼女の傍らへ椅子を引き寄せ座った。 「メアリ?」 ピーターが呼びかける。ピーターの背中を追うようにして近づいたリチャードも、彼女を見ながらカルテを手に取った。5年前に脳梗塞で倒れてそのまま意識不明。昏睡状態のままだが抗不整脈薬など心拍を保つ薬を使わなくても心臓は安定しているし、脳波も安定している。つまりただ眠り続けているのだ。 リチャードは立ったまま、メアリという女性の顔を見た。何年も意識を失った人間はあやゆる筋力が衰え顔も弛んでしまう。しかしこの女性はもともと肉が薄いせいだろうか、あまり弛みがなく、酸素マスクをしていなければ、いつものように眠っているだけのような穏やかな表情だった。 ピーターはいとおしそうに自分の妻を見つめていた。はた目から見れば、祖母を久しぶりに見舞った孫だと思うだろう。 「すっかり歳が開いちまってるよな」 自分の患者だったら絶対に口にしないような言葉だった。それに対し、特に気分を害した様子もなくピーターは穏やかな笑顔を浮かべたまま答えた。 「会えるかどうか不安だったんだ。会えただけでも幸運だよ」 それにしてもよく病院に五年も治療を受けられていたものだ。大抵の病院では延命治療はしない。そんな疑問を察したのか、ピーターはちらりとリチャードを見た後、説明をはじめた。 「実はね、もともとこの病院は友人と私が設立した病院なんだ。イギリスから移住した直後で、最初は入院施設もない小さな所から始めたんだが、将来は入院病棟を持つ大きい病院にしようと夢を持っていたんだ」 そんな人間がなぜ、軍人記念病院にいたのか?眉を顰めた顔をみたピーターはくすりと笑う。 「なのになんで私はあの病院にいたのかって思ったんだろう?外科医として腕を磨くためさ。当時はベトナムから重症患者がひっきりなしに運ばれて来ていた。器具も機械も最先端で場数を踏むには最適の環境だ。この病院は友人にまかせて、私は外科医としてのキャリアを積み、しばらくしたらここへ戻るつもりだったんだ」 リチャードは静かに聞いていた。そしてピーターはメアリの顔を見つめたまま静かに話し続ける。 「友人もがんばってある程度大きくなり、そろそろ私も辞めようかと思っていた時、心臓発作で突然死だ。死んでも死に切れなかったよ。妻もあまりにも突然すぎて、私がなくなった事を理解できずにいたよ。運良く私がいた場所から管理棟が移転になって、あの場所には人が殆どこなくなった事で私はひっそり留まり続けていた。誰か信頼できる人間がやってこないか待ち構えていたんだ。そういえばいつか発作で心停止状態の患者が緊急に運ばれて君が処置を行った事があっただろう?あれはすばらしい判断と手際だったよ。少々手荒ではあったが・・・」 ああ、じゃあやっぱりあの時に自分に話しかけた声はライアンだったんだ、リチャードはやっと謎が解けて納得した。そしてちいさく「どうも」と呟いた。 「もしあの時、君のような優秀な外科医があの時病院にいたら、私は助かっていたかもしれないと思うと残念だよ」 ピーターはにっこり笑ってリチャードを見つめる。リチャードは一瞬とても変な気分になった。もちろん話をしているのはすでに死んでしまった人間。しかし、目の前の相手は友人のピーター・モーガンだ。まるで友人が手遅れの患者のように見えてしまう。リチャードは一瞬、ライアンがこのままピーターを放さないのではないかと不安に駆られたのである。 「君がいつか部屋に来てくれないかと思っていた。そうしたら、とんでもない計画でやって来たのだから、これは懲らしめ半分出てやるしかないって思ったんだ」 そういたずらっぽく笑う表情は、ピーター・モーガンのものだった。一瞬、正気に戻ったかと期待したリチャードだったが、また妻へ愛情溢れる視線を戻したピーターを見て気のせいだとガックリと肩を落とす。 その時である、脳波計が揺れた。二人ははっとしてメアリの方へ顔を向ける。ピーターは握っていたその白い手の指がゆっくりと握り返してくる事に気がつき、目を見開いた。 「メアリ?」 するとその声に答えるかのように、メアリの白い睫毛が揺れて、薄らと開いたのである。 「メアリ」 呼吸マスクの内側が白く曇る。リチャードはメアリがつながれている計器を確認して、すべてが安定しているのを見ると、ピーターに頷いてみせた。ピーターはゆっくりとメアリの呼吸器を外す。 「・・・・あなた」 ええーーー!!リチャードは思わず仰け反ってしまった。が、改めて彼女が脳梗塞で倒れたという事と、気がついて間もない事を思い出し、人物認識ができていないんだと気がつき気を取り直した。 「ああ、あなた。やっと迎えに来てくれたのね」 「ああ、やっと来られたよ」 二人は見詰め合ったまま、しっかりと手を握り合った。メアリ・フリー夫人は夫のその外見が別人だという事に気が付いていないのか、それとも彼女には最愛の夫に見えているのか、彼女は慈愛のまなざしをピーターに送り続けていた。 こういう場面には医者として幾度となく立ち会って来ているリチャードだ。二人にしてあげようと、そうっと部屋を後にした。 ピーターはいったん彼女の手を離し、窓に向かうと、薄い日よけのカーテンを開けた。大きな窓の外には病院の外側に広がる小川と湿地が見下ろせる。空は青く晴れわたり、まるで風景画のようだった。 「随分待たされたものね。待ちくたびれてしまって、とうとうこんな風になってまで生きていたんだから」 メアリは五年間の眠りから覚めたとは思えないほどしっかりと話した。ピーターにのりうつったライアンもまったくそれに違和感を持たずに話続ける。 「済まなかったね。信頼できる人間が私の部屋にやって来なかったんだよ」 メアリがゆっくりと手を伸すのを見て、彼もベッドの脇へ戻り、手を握り締めた。メアリはまじまじとピーターの姿を見つめ、一言言った。 「今のあなたの姿、高校時代の彼を思い出すわ」 ピーターは軽く笑い声をたてて笑った。 「という事は、私の人選は君にぴったりだったってわけだ」 メアリも頷きながら笑った。そしてもう一度ピーターをまじまじと見る。 「これで私もやっとあなたと一緒に行けるわね」 メアリはにっこりとほほ笑み、そしてゆっくりと目を閉じた。 フラットライン・・・・・ ピーターはその力の入らなくなった手をシーツの上に置きその手に手を重ねた。そしてふっと笑うと自分の体を見つめる。 「この体にありがとうと言わなければならないな、ここまで私を運んでくれたんだから」 フラットな電子音を聞きながら、ピーターはもう一度メアリを見てくすりと笑った。そして、そのフラットラインがまるで自分の心臓の音とシンクロしたかと思うほどに突然ピーターの頭がカクンと前に倒れ、そのままメアリの上に伏せるようにして意識を失ってしまったのである。 部屋を離れて数十分。 ロビーでだらだらしながらコーヒーを飲んでいたリチャードは、ふっと嫌な予感を感じて、身を起こした。医者の感だろうか。おもむろに立ち上がり、最初は足早にメアリの部屋へ向かったが、途中からもどかしくなり走りだしていた。病室へ飛び込んだリチャードが見たのは、フラットラインの平坦な音と、力無く横たわる老女、そしてベッドに突っ伏しているピーターの姿だった。 まさかまさか、と思いながらピーターに近づく。 「ピーター、おい、ピーター・・・・ウソだろ止まってるよ」 首に手を当て脈がないのを確認して、リチャードは凍りついた。その時丁度メアリの心停止に気が付いた医者と看護師が器具を持って飛び込んで来た。 リチャードは、床にピーターの体を仰向けに転がし、シャツを引きちぎった所で、緊迫した声で命令した。 「ショック性心停止だ。オレがやるから器具を貸してくれ!」 一体どうなってしまったのか自分でも分からなかったが、とてもゆっくりと深く、そして暖かい気分に浸っていた。インターンの時から今日まであの病院に来てから、問題が多すぎて気の休まる時なんてほとんどなかった。それが今はまるで長期の夏休みを取り実家に戻ったような、不安もなく懐かしさに浸ったっているような、とても穏やかでいい気分だった。 ・・・・これってもしかして臨死体験か?そう思った瞬間 「ピーター、幽霊なんかと一緒に行くんじゃない!戻ってこい!」 遠くの方で自分を呼ぶような声が聞こえたか思うと、突然息苦しさを感じ瞬発的に大きく息を吸い込んだ。 「ピーター!しっかりしろ!」 耳元でリチャードの大声がし、びっくりして目を開けた。 「ピーター・・・?」 自分を覗き込む複数人の白い人達。そして一番近くにはリチャードが覗き込んでいた。確か自分は病院で幽霊とご対面をしてそれから・・・・。なんて状況を理解する前に飛び込んできたのは、リチャードの手に持たれた除細動の電気ショック、キューイーンと音を立てている。 「・・・・わー!!!何する気だ殺す気か!」 ピーターの普通な反応とは裏腹に、その場にいた全員の肩から力が抜けて笑顔になった。リチャードに至っては半身を起こしたピーターを見つめ頷きながら、がしっと抱きしめてきたのである。 「よかった!本当によかったー」 ピーターが知らない病院の知らない一室の知らない老女の部屋で老女と共に自分が一瞬死んでいたと知るのは、もう少し後になってからである。 それからしばらくして・・・・ 『スタージェス先生が噂の首なし外科部長の幽霊を病院から追い出したそうよ。あの先生は上層部だけでなく、幽霊まで病院から追っ払ってしまうなんて、本当ただ者じゃないわね』 なんていう実は本当の噂が病院内の看護婦の間で飛び交っていた。噂の出所の大半はシドとルビーの言い触らし。 『あの部屋でモーガン先生が幽霊に呪われてあやうく死にそうになったのを、スタージェス先生が幽霊と戦ってやっつけたんですって』 この話は、あの日ピーターと話した看護師長が「そういえばモーガン先生がおかしくなった日があったわね」と言う一言が前の話とくっついて、そして有無を言わせずリチャードからCT検査を受けさせられていた事実が、実は半分本当の噂になったのだ。 そして当のリチャード・スタージェス医師はと言えば・・・ 「なあ、来週新しいインターンが来るんだけど、今度は地下の旧霊安室の血まみれ兵士の話でやろうと思うんだが、どうかな?」 シドとルビーも、そしてピーターも目が点になって固まってしまった。それをどう取ったのかリチャードは顔を輝かしてピーターを指さす。 「幽霊役はお前だ。なぜならシドだと血まみれで立ってもあんまり目立たないし、ルビーだとデカ過ぎて天井に頭をぶつけると生身だってバレるからだ」 あんぐりと口を開けたまま言葉がでないピーター。お前のせいでおれは死にかけたんだぞ、という抗議の言葉さえもでてこなかった。そんなピーターの思いなどおかまいなしで、リチャードは楽しそうにインターンをどうやって怖がらせるか計画をしゃべり出した。 恐るべきリチャード・スタージェス、全っ然懲りてない。いや懲りるという言葉を知らないだけなのかもしれない。 いやー、ギャグは私には無理でした・・・。それに医療ものも私には無理でした、って途中で気がついたんでよねー、遅かった(撃沈)。でもまあ男前リチャード・スタージェス先生を存分に動かせて楽しかったですー。キーファー演じるモーガン先生のちょっと古風な演技を想像しながら書けたのも楽しかったですね。もうちょっと医療ドラマ研究して、再挑戦しようと思います。お付き合いいただきありがとうございました。 |