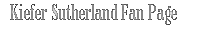
|
12/25 10:00A.M Mogadishu,Somalia (モガディシュ,ソマリア) 酒場というのは、知らない人間が紛れ込むのも知らない人間どうしが出会うのにも絶好の場所である。人でごったがえしてはいるが、誰も自分に関係ない人間に興味を示さないで騒いでいるからだ。酒場の中では人々は陽気に振舞っているが、一歩外に出れば乾いた風に吹き上げられる砂に襲われ、視界の効かないその中で誰もが銃の的になるような国である。 三人の男が、ごったがえす酒場の入り口で足を止めていた。背の高さに違いがあるものの黒髪に顔を覆う濃い眉毛と髭で、誰が誰なのか見分けがつかない。しかし、この酒場を埋め尽くす男たちの風貌のほとんどは彼らと同じであった。交わされる言葉もアラビア語である。 「どこだ」 そう言って男達は意識的に誰かを探すように視線を店じゅうへめぐらした。彼らは噂だけを頼りにここへやって来たのだ。米軍の脱走兵、それもひどく内情に通じている男が、毎日この酒場へやって来ている。そして金さえ払えば自分達に惜しげもなく知りたい情報をしゃべるというのだ。彼らの中の一人が一点に目を留めて軽くアゴを振った。これほどの雑踏とした雰囲気の中で、その男は見事なまでに気配を消して存在していた。柱の影にぽつりと置かれた小さな円テーブルと椅子。そこにまるで暗がりに溶け込むように煤けたモスグリーンの丸まった背中がある。目配せをした後、彼らはするすると人ごみをすり抜けて、その背中へ迫って行った。 「おい」 その男の側により、彼らは短く呼びかけた。座っている男はグラスを両手で包み込み、まるで覆いかぶさるようにうつむいていたが、その声にちらりと顔を上げた。短く刈られたブロンドの髪、日に焼けてはいるが地元の人間とは明らかに違う肌の色、そしてこの男の本質を物語るかのような冷たく鋭い光を放つ青い瞳。今は自分の存在を最小限にとどめたいからか、何気なさを装って席に着く漆黒の髪と眉を持つ彼らに不安げに視線を投げかけていた。しかし彼らがテーブルを囲うように身を寄せ、ポケットから丸めた現地の金をテーブルに投げてやると、ようやくその男もカップから顔を上げた。 「これが何なのか知りたい。ジャハラの奴らに渡して金が取れそうなもんがあるかどうか」 目線だけを店内にめぐらせながら、男はテーブルにバサリと膨らんだ茶封筒を投げてよこした。ジャハラとはこの地域の過激派のテロ集団である。どうやら彼らは手に入れたこれをそこに売りつける気のようだ。なんだただの市民かと内心舌打ちをしたが、男は平静を装い指先だけでその封筒を持ち上げ中身を机の上に出した。 「米軍の機密文書とか、この中にあるか?」 バサバサと色も形も違う手紙の束が出てきた。どれもこれも宛名は英語で書かれている。明らかに本土からの郵便物だ。そして切手なども貼ってなく内文書だとわかる。ただこの国内ではなく宛先はすべて近隣国の米軍の拠点を指していた。 「いったいどこからこんなものを・・・・」 低めでハスキーな声が、手渡した男の目を見つめて囁くように発せられた。 「運搬に雇われたこいつがくすねて来たのさ。・・・・軍を裏切ったお前なら、この中のものがなんなのかわかるんじゃないか?なぁジャック」 ここで彼らの一人がこの男の名前を呼んだのは、目の前の精彩を放たない男が本当に元米軍の精鋭部隊にいたジャックとかいう者かどうか疑問に思ったからだろう。ジャックは答えるかのようにふっと目じりと口端を吊り上げた言った。 「なるほどな」 ジャックは手紙の宛名に目を通してはそれを横に避けて行く。どれもこれも機密というより重要ではない連絡文書などだった。それほどの重要事項を文書でやり取りする訳がない。案の定重要なものなど全くなかった。ジャックがどれか適当に名目をつけて男たちに渡そうと思いながら宛名にざっと目を走らせていた。が、ある手紙にさしかかった時ジャックの指が一瞬だけ止まり、思わずはっと息を呑んだ。 「どうしたんだ?」 至近距離で成り行きを見守っていた男たちはその呼吸に気がつきジャックの顔を見つめた。ほんの一瞬だけ狼狽の色が浮かびそうになったが、男たちの視線が手紙ではなく自分の顔に向けられている一瞬をついて、マジシャンのように素早く前後を入れ替えたのだ。 「これは・・・・・CTUからここのCIAエージェントへの連絡文書じゃないか」 「なんだって!」 嬉々とした表情を浮かべ、彼らはその手紙をジャックからひったくるようにすると、顔をつき合わすようにそれを覗き込んでいる。ジャックはその間に該当の手紙を机の下に滑り込ませ、ジャケットの内側へ押し込んだ。 「あまり大したものはない様だ。まあ組織に持っていけばいくらかの金にはなるだろうが。本当に重要機密を知りたいなら通信網を狙う方が効率がいいぜ」 彼らはすでにジャックから自分たちが手に入れた文書の価値に夢中になっていた。興奮したようなアラビア語で早口に何か話し合い始める。ジャックはグラスの中身を一気に空にし気だるそうに席を立あがると丸められた札束を掴み酒場を後にしたのだった。 自分の姿をかき消すように、薄汚れたジャケットに身をうずめる様にしながら、しかしその歩調は早かった。ねぐらとしている表通りから数本奥に入った裏通りにある安宿に戻り、借りている部屋へと滑り込む。ベッドと簡素な椅子と薄暗い照明以外何もない。薄汚れたボロ布のカーテンは一部の隙もないように閉めたままなので、その部屋は暗く陰湿な気分にさせた。しかしこれは自分から望んだ潜入捜査だ。かなりきわどい機密情報を流し、やっとテロ集団の実態と名前を掴んだ所である。その組織の本拠地を探り出すまでは、米軍や治安部隊から隠れるように生活をしている脱走兵を演じる為、こうやって身を潜めて存在し続けるしかないのだ。部屋に入りジャックは大きくため息をついた。癖になってしまったのか、こういう時でさえもできるだけ音を出さないように勤めている自分がいる。ジャックはそんな自分にあきれつつも、ベッドに腰掛けるとやっと服に押し込んだあの文書を手に取った。きっとミシェルがやってくれたのであろう。本来なら駐屯している軍を通じここへ運ばれているものだったはずだ。 もしあの男達がジャックに文書の事を聞かなかったら、この手紙は一生自分の下へ届かないものだっただろう。そっけない封筒にはどこにもジャックという名前がなかったが、その宛名は自分を指し示す暗号であり、今回のジャックのミッションナンバーを使って解読できるようになっていた。それを使うのはLAのCTUの人間とジャックの連絡の場合のみ。さっきの男たちにも言った通り現在軍では書面での重要なやり取りはほとんどない。しかしジャックにはそれが何であるのか察しがつき、そして絶対に他の誰かの手に渡ってはいけないものだと分かっていた。なぜならミシェルがわざわざ危険を冒してまで、こんな所にコレを送ってきたのだから。無機質な封筒の中からはもう1枚の真っ白い封筒が出てきた。宛名もなにもないが、ジャックにはそれが誰からのものであるかすぐに分かった。慎重に中身を取り出す指先が心なしか震えている。 そこにはカードが一枚、そして写真が一枚入っていた。甘いピンク色の地に金の飾りたてられたMerry Christmasの文字が躍る。カリフォルニアの匂いがした気がした。そうっとカードを開くと、そこには見慣れた愛おしい人の筆跡が並んでいた。 『心配しないで、私は幸せよ メリークリスマス パパ』 思わずその言葉に笑顔を漏らす。寒く暗くて埃っぽいこの場所に、忘れかけていた家族の暖かさと匂いが立ち込める。「キム・・・」と唇だけ動かし、その字をそっと指でなぞった。以前と違ってジャックはこういうものを手にしても不安にかられる事はなかった。それはもう二度と自分の最愛の娘が危険に晒されることがないという確信があるからだろう。あの子の側にはチェイスがいるのだから・・・。写真を手に取ると、そこにはチェイスの後ろから抱きついた屈託のない笑顔のキムがいた。とても落ち着いたいい笑顔だ。知らない間に表情がテリに似てきたな、と思わずジャックは笑顔をこぼしていた。 「メリークリスマス・・・・キム」 言い訳 ファンフィクションなんて久々に書きました!クリスマス企画に出すものがなく・・・というのもありますが、今回私がこれを書こうと思ったきっかけは、ちゃんとした文庫本で出ている「24」の小説の出来があまりにもお粗末で「これなら私の方が絶対いいのが書ける!」と変な意地に芽生えてしまったからでした。だからといってクリスマス企画で長くも書けずこんな中途半端なものになってしましたー。一応企画背景と話しますと、シーズン3の事件の後でジャックが首を言い渡されるまでの間に1つ潜入捜査をこなしていたという設定です。ミシェルもまだトニーと別れていないものとみなしてます。話はどうあれ、ジャックのしぐさが皆さんのジャックの姿と重なってくれるといいです。 凛子 |