■間瀬源七郎君事蹟(白虎隊事蹟)
■間瀬源七郎君の傳
君、慶応四年正月を以て、不時備組に入れられ、五月白虎二番士中隊に遷り、二人扶持を賜った。六月、喜徳公に従って福良村に出張し、八月二十二日、容保公に従って滝沢村に向かい、更に進んで敵を戸ノ口原に迎い撃ちしに戦い利あらず、退いて飯盛山に至り、二十三日、剣に伏して死んだ。年十七。
初めその出陣せんとする時、白木綿の筒袖を内にし、紺羅紗のマンテルを外套にし、紫縮緬紐の義経袴を着て、鷹匠足袋に草鞋を穿ち、ロウ色鞘の大小刀を佩び、ゲベル銃を肩にし、黒革に梅鉢の紋章を記した弾薬胴らんを腰にし、茶筅髷を結い、韮山笠を戴き、(マンテルとはフロックコートの如き洋服で、義経袴は袴の極めて短きもの、鷹匠足袋というのは刺し子の如きもので作ったもの。ロウ色とは黒漆塗で光沢がある。ゲベルは銃の名、茶筅髷とは髪を頂にて結び、四五寸に切り後に下げたるものをいう。韮山笠は紙よりにて編み、漆を塗った編笠である)支度が既に出来たから、別れを家人に告げた。
父新兵衛君、誡めて、「戦に臨んで衆に謀らないで、己独り挺進するな。勝ちに乗じて長追いするな。深入りして敵に捕らわれ、家名を汚すな。よくこれを守れ、他に言うことはない、よし行け」と言った。君、拝謝して、「初陣の一戦に功を彰し、以て君父の御恩に報います。誓って汚名を蒙り、家声を墜さないから、どうぞご心配下さるな」と答え、奮躍して家を出た。
事定まるの後、改装方より戦死者の遺族や、親戚に、その死体を捜索して、各々その菩提所に葬るように命令した。時に源七郎君の遺族は、城南の井手村に居た。その三人の姉君が、相携え戸ノ口方面へ捜しに向かう途中で、知人の石川某に逢い、その事を告げた。石川が言うに、「白虎隊の自刃した者は既に飯盛山に葬ったと聞いた。源七郎君もまた必ずやその中であろう」と。三姉は半信半疑で、念(おもい)を飯盛山に残し、なお衆に従って行く行く強清水を過ぎて戸ノ口に達し、広い原中の此方彼方、或いは木の下、岩の陰など諸処捜したけれども、君の屍が見つからない。因って、笹山を経て、再び強清水に至るに、日暮れて物のあやめも分からない。やむなく一夜をこの村に明かし、早天飯盛山に登って見れば、自刃者の衣服がずたずたに千切れて、地上に堆(うずたか)く積んであり、また袴及び足袋などが松の樹の枝に掛かっているのもあった。近づいて、よくよくこれを調べ視ると、その中に三姉が当時手ずから縫って与えた物があって、君の持ち物であったことが明らかだった。ここに於いて初めて、首途(かどで)の時の辞(ことば)を実行した事を知り、且つ悲しみ、且つ喜び、思うに戦場で死んで戦場に葬られたのは、死者の悦ぶところだろうから、改装の必要はないと、僅かにその遺物を拾い集めて持って帰り、棺に納め、天寧寺の先塋(せんえい:先祖の墓)の側に埋め、石を建てて法号を勇猛院忠誉義進居士とした。
君、人となり温和にして恭謹、容姿頗る美麗であった。此の故に、幼少から君側に伺候することが度々で、かつて戴いたところの玩具が一二、今なお家に残っている。成長するに及んで学を好み、十歳で日新館に入学し、三禮塾二番組に編入された。十六歳で講釈所生に進んだ。四書、小学、近思録等の書を賜り、屡々その勉学を賞せられたということである。
父の名は利貞、新兵衛と称し、食録三百五十石、郭内二之丁に住した。家老組組頭、用人、奉行等に累進し、職に在ること四十九年、良吏の誉れがあった。
慶応四年九月十四日、城中御座二之間で、大砲の破裂丸に中って斃れた。時に年六十七。君はその二男で、嘉永五年四月朔日(ついたち)生まれである。
君の母堂名はまつ子、黒河内図書君の第三女である。まつ子君、容貌端麗、気品高く、賢母を以て称せられた。
源七郎君の令兄を岩五郎君といった。朱雀二番足軽中隊頭に累遷し、各地に出陣し、その後八月二十九日、城西長命寺の戦に衆を励まして奮進し、砲丸その腰を傷つけ起(た)つことが出来ぬようになった。そこで自ら刀を抜き、これを従卒渡部栄吉に授け、命じて首を斬らせた。栄吉、泣く泣くこの事を果たし、首を引提げ、漸く間を得て城に入り、その刀を君の厳父に差し上げ、その最期を報告した。時に年二十九。その刀は長さ二尺三寸、今やその血の痕が錆びついて、陰寒の気が人に迫るようである。碑を萬松山天寧寺に建てた時に、その柄袋を埋めたということである。
補修 會津白虎隊十九士傳
■間瀬源七郎伝
源七郎は間瀬新兵衛の二男にして、兄を岩五郎という。家禄四百石、父新兵衛は三奉行職に任ずること数十年、頗る循吏の誉れあり。郭内二之丁に住す。源七郎、人となり、聡明、多智、大いに衆に異なり居常沈黙、かつて人と争闘せず。
十歳にして日新館に入り、漢学を受け、三等、二等、一等の級を卒業し、屡々賞典を受け、また武芸を習い、慶応戊辰三月、士中白虎隊に編成し、仏式歩法調練を受け、八月二十三日、官軍を戸ノ口原に拒き、激戦の余、飯盛山に退き、衆と倶に屠腹して死す。年十七。
白虎隊勇士列伝 |
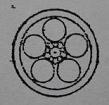 丸に梅鉢
丸に梅鉢