子どもたちにおもしろい本を読んでほしい、楽しんでほしいと願っている大人はたくさんいます。作家、編集者、書店、教師、そして親...。作り手から手渡す人間まで、 子どもの本に関わる大人は、その本と同じ位、いやそれ以上におもしろく魅力的な人が多いと思うのです。子どもと子どもの本の未来は、そういう『おもしろい』大人たちが背負っていると 言えるのではないでしょうか。決して模範的という意味ではなく、感動や驚き、発見を子どもたちと共有し、共に楽しみ、おもしろがる大人たちが...。
また、子どもが時代を映す鏡であるなら、その時代を作っているのは私たち大人です。子どもたちの本離れとは、私たちの本離れにあったのではないでしょうか。 子どもたちにどんな本を与えたいか、読ませたいかというよりも、大人の私たちがこれからどんな本を読み、どんな人間として生きていきたいのかを、自問してみる必要があるのかもしれません。
絵本も含めて優れた本というのは、大人、子どもをボーダーレスに楽しませ、感動させるものだと思います。そして私たち大人は、同じ時代を共に生きるパートナーとして、常に子どもたちの『良き隣人』で ありたいと思います。読書においても、教え導くという関係ではなく、共に楽しむという関係を作っていくところに、子どもの本の魅力と未来があるのだと思います。
今月の本
 |
「鳥の島」 川端 誠 BL出版 1575円(税込み)
●海の向こうの世界への憧れが、鳥を島から飛び立たせる、次の年も、その次の年も...。ある時、飛び続け、力尽きて海に落ちようとした鳥に島が見えた。
今まで思いを果たせず海に沈んでいった鳥たちで出来た島...。小さきものたちの力、そして次の世代へと受け継がれていく生命、歴史の重みを感じさせられます。
壮大なテーマを小さき鳥たちに託した力強い作品です。紙粘土に彩色したという独自の技法もこの絵本に力を添えています。 |
●Vol. 3 はりまリビング 2005年11月5日号
子どもに本をよませたいのはなぜ?〜本から得られるもの〜
私たち大人が、子どもたちに『本を読んでほしい』と望むのはなぜでしょう。理由は数多くあると思いますが、私の考えを述べてみます。
大人も同様ですが、特に子どもたちは本の世界に容易に入っていきます。クマになったり、機関車になったり...本のなかのもう一つの世界を体験します。
本の中は虚構の世界であっても、喜び、悲しみ、驚きを感じるのは、読み手である生身の子ども自身です。本と気持ちを通わせながら、確かな実感を得ているはずです。
『本を読む』ということは、もう一つの世界を生きる、少し大げさに言い換えるなら、もう一つの人生を生きるということではないでしょうか。そして、こういう体験の積み重ねは、
様々な状況に直面した時の『生きる力』となっていくのではないかと考えます。
絵本にせよ児童文学にせよ、優れた作品はこのような『生きる力』を与えてくれるのだと思います。本さえ読めばいいとは思いませんが、幼い頃から本に親しむことによって得られるものの大きさは
計り知れません。
そして長い歴史を生き延びた本も、生まれたばかりの本も、私たちが次の世代、そして次の世代へと伝えてこそ、その価値が高まっていくのだと思います。
今月の本
●山際から太陽が顔をだす夜明けの一瞬、すべてが光に包まれ、新しい一日が始まる。
子どもの目線で本を選ぶ〜幼児の選書会より〜
図書室に入れる本を児童生徒が選ぶ、ジオジオが選書会と呼んでいる活動があります。少しずつですが理解を得て、昨年は加古川市を中心に16の小学校で実施されました。
自分の選んだ本が図書室にあると、行く回数も増え、図書室が活性化していきます。選書会をすると、子どもたちが「本離れ」をしているのではなく、大人が「本離し」をしてきたのではないかと
思うくらい、子どもたちは熱心に本選びをします。先生方や保護者の人たちも驚きの声をあげるほどに。
小学校だけではなく幼稚園でも選書会を行ったことがあります。小学校とは狙いが違いますが、自分自身で本を選べるというので大変な喜びようでした。
ジオジオの店頭でもよく見聞きすることですが、子どもたちが選んだ本に対してお父さんやお母さんが「ダメ出し」をします。「字が多い(少ない)」「絵が暗い」など...。
しかし選書会では自分の好きな本、気に入った本が選べるのです。そして子どもたちが選んだ本はほんとうにおもしろい本ばかりです。もし失敗したとしても、
今後の本選びの貴重な「肥やし」になるにちがいありません。
読書の第一歩は「何を読むか」という本選びから始まると思います。幼い子どもたちに本を選ぶ楽しさを知ってもらうことは、将来の読書体験の大切な土台となるのではないでしょうか。
今月の本
●私のパンツをお母さんがはいたらどうなるか?私がはくとさくらんぼのパンツが、お母さんがはくとリンゴになった!ネズミさんのパンツは、おさかなのパンツは...。
親子で本にふれよう〜一緒に本を楽しもう〜
子どもの本屋という仕事柄、子ども向けの「お話し会」に来てほしいというお声がよくかかります。2・3才から小学生くらいの年齢が多いのですが、会が始まる前には
「静かに聞きましょう」という注意がなされます。
お話は静かに聞くというにが原則ですが、年齢が低かったり、人数が増えたりすると、たまたまムシの居所が悪かったり、興奮の度が過ぎたりと静かに聞けない子どもがいることもあります。
例えば「おおきなかぶ」という絵本では「うんとこしょ、どっこいしょ」という掛け声を出してこそ楽しめるストーリーのなっています。また「へんしんトンネル」という絵本では声に出さないと変身しません。
かっぱが、「かっぱ、かっぱ、かっぱ...」とつぶやきながらトンネルをくぐると、「かっぱかっぱ...ぱかっ、ぱかっ」と元気な馬になって出てきます。
”ぼたん”は”たんぼ”に、えりちゃんはりえちゃんに、という具合です。最近「へんしんトイレ」という続編もでました。
そして実際には、ただ騒ぐだけではなく、子どもたちはどこで声を出そうかと、かえってお話に集中し、メリハリのある流れが生まれたりもします。
多人数のお話し会だけでなく、家庭での親子のお話にも、こういう工夫があるとおもしろいかもしれませんね。
今月の本
●声に出して楽しむ絵本。コミカルなタッチの絵も楽しい。
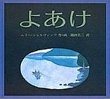
「よあけ」 ユリー・シュルビッツ/瀬田貞二 訳 福音館書店 1260円(税込み)
この夜明けまでの静かなときに流れの中にも目覚めるものたちが
いる。静の中の動、動の中の静を墨絵を思わせるタッチで描いた絵本。作者は唐代の漢詩『漁翁』をモチーフにしたそうです。
子どもだけではなく大人もうならせる絵本です。
●Vol. 2 はりまリビング 2005年9月10日号

「おかあさんのパンツ」 山岡ひかる 絵本館 893円(税込み)
短いフレーズ、シンプルなイラスト、そして意外性。幅広い年齢に楽しんでもらえます。
●Vol. 1 はりまリビング 2005年5月28日号
そういう時は、静かに聞かなくても良い、つまり賑やかに騒ぎながら進行するお話を加えた構成を考えて見ます。
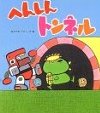
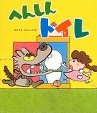
「へんしんトンネル」「へんしんトイレ」
あきやまただし 金の星社 各1260円(税込み)
続編「へんしんトイレ」はトイレに入ると変身して出てきます。