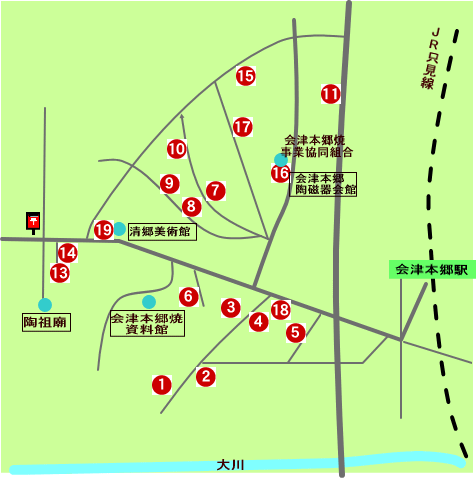 [会津本郷焼マップ] |
[会津本郷焼] 会津本郷焼の歴史は文禄二年(1593年)、蒲生氏郷公が会津の領主となり、若松城の修復のため播磨国(兵庫県)から瓦工を招き、城の黒瓦を製造したのが始まりとされています。 その後江戸時代になり、時の会津藩主保科正之公が天保二年(1645年)尾張国瀬戸(愛知県)生まれの陶工を召し抱え、陶器を本格的に創造した。 陶器の生産は藩の支援を受けて益々発展し、更に寛政一二年(1800年)には、有田窯場に潜入して技術を持ち帰った佐藤伊平により白磁の製法を開発. 幕末には会津本郷町の陶業は目を見張るばかりに発展したが、戊辰戦争後下火となる.伝統的な色釉を基盤とし、みちのくに根ざした素朴な美しさと使い勝手を持った陶器、雪国に生まれた純白の肌と優雅な文様を持った磁器が特徴となっている。昭和34年、ブリュッセル万国博でニシン鉢がグランプリを取り、以後勢いと取り戻した.歴史は数百年あり、伝統的な技術・技法が認められ、平成5年、伝統的工芸品産地として指定された. [会津本郷焼資料館] 会津本郷焼の歴史が垣間見られ興味深い. [会津本郷陶磁器会館] 窯元が共同で組合参加16窯の作品を展即売してる。それぞれの窯元の作品をじっくり堪能できるので、ここから訪ねてみたい作家を決めれるので好都合。窯元案内マップも常備されている. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[所有作品]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||