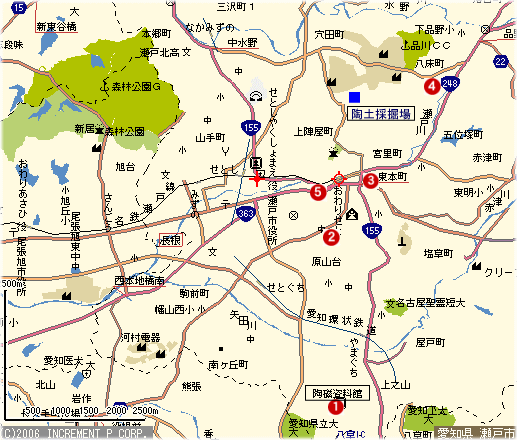 [瀬戸焼マップ] |
[瀬戸焼] 瀬戸焼原点は、瀬戸市近郊の猿投山で見つかった平安時代の窯跡に求められる.平安時代に釉を使って作陶した痕跡で、日本初との旨.陶祖は加藤四郎左衛門景正(藤四郎). 桃山時代に茶陶.江戸時代には、庶民用雑器を焼いたが、美濃焼の押されて沈滞した. 江戸後期に、加藤民吉が有田から磁器の製法を伝え多結果、磁器「新製焼」が盛んになり、染付けなども手がけることで、全国に「せともの」と呼ばれるほどの陶磁器の生産地となった.従って、瀬戸では庶民雑器からノベルティまであらゆる種類の陶磁器が揃う. [瀬戸の地] 公共:名古屋栄から名鉄瀬戸線で尾張瀬戸 名古屋ICから約10km. 猿投山は陶磁資料館より南である(地図南端). |
||||||||||
| ■瀬戸へは何度も来ている.窯元は品野・水野地区にあるが、個別に訪れるのは難しい. |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
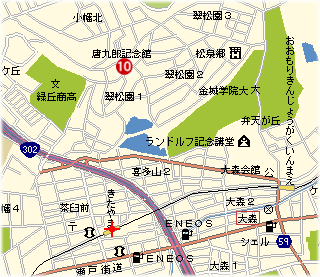 |
氏は、明治31年瀬戸市生まれ.昭和60年没.16歳から作陶.「陶磁大事典」編纂.古窯研究、執筆にも積極的に取組む.景徳鎮なども視察している.織部・志野を得意とし、唐津なども挑戦した.日本陶磁協会、日本工芸会を設立した重鎮.マスメディアにも積極的に参加し幅広い活躍であった.著書も多数. 資料館は、尾張瀬戸線北山駅から徒歩15分くらいのところにある.やはり桃山時代を回顧させる展示である.氏の作品は、どれも焼きこんでいる.造形に重みは有るが軽快であり、デザイン考慮といことでは織部の流れを汲んで、垢抜けている.戦いのない時代の武士好みといった感を持つ. |
||||||||||