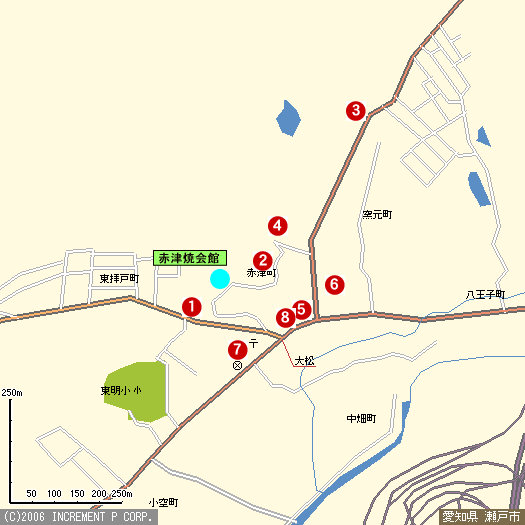 [赤津焼マップ-訪問した窯のみ.窯元は80ほど有る.詳細は下記で] http://www.akazu-kamamawasi.com/kamamotomeguri.htm (名鉄尾張瀬戸から車で10分.バス:名鉄瀬戸線「大松」下車15分) |
[赤津焼] 赤津焼工業協同組合webより 猿投山麓の静かな風土に育まれて、一千年を超える赤津焼は、日本六古窯の一つに数えられ、良質の陶土、赤津地域のみに産出する原料にめぐまれて、すぐれた陶工が生まれ、育ち、その技術や、技法が今日まで受けつがれ、美術工芸品、茶華道用具、一般食卓用品に、脈々と息づいています. 伝統工芸品に指定された七色の釉薬は、平安時代の灰釉に始まり(つまり瀬戸焼が原点:著者注)、へら彫り、印花による華やかな文様によって花開き、鎌倉期、鉄釉、古瀬戸釉の出現により、貼付け、浮彫り等の装飾技法に一段とみがきがかかり、世にいう古瀬戸黄金時代となりました. 桃山期茶華道の発達に伴い、黄瀬戸、志野、織部の各釉が出現し、その優雅な美しさは、茶陶を中心として各焼物に及び、今日も変らず赤津焼の代表的なうわぐすりとして多く用いられています(美濃焼を吸収:著者注). 江戸時代の初期尾張徳川家による尾州御庭焼によって御深井釉が用いられ、玄人好みのうわぐすりが一段と冴えて、見事なろくろ技術や、たたら技術によって他に類をみない多彩さを誇り、十二種もの装飾を駆使して今日も尚、赤津焼に生かして、その伝統を守り制作されています. 後継者の育成も活発化し、「土ねり三年、ろくろ十年」といわれる伝統的技術の継承に二世らが情熱を燃やしており、赤津焼は今後も暮らしの伴侶として生き続けることでしょう. [赤津焼会館] 1階展示室・即売場
高台に建てられた赤津焼会館は、円筒状の建物の周りを七釉のひとつである織部釉の陶板で装飾されています.深い緑色が美しい印象的な建物です.館内には、たくさんの伝統工芸品・赤津焼が展示されています.略.また、館内では展示品の即売も行なっております. |
||||||||
| ■赤津へは、赤津焼会館ができる前から数度と来ている.最初はディスプレーをしている窯元は少なかったが、今は増えている.会館ができてからは多くの作品を堪能することができる.通常は、 |
|||||||||
|
[赤津の地] 東名名古屋ICより40分. 東名三好ICより30分. 中央道多治見ICより30分. 公共機関:名古屋栄から名鉄尾張瀬戸線. |
||||||||

