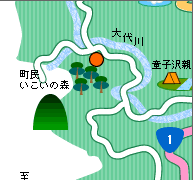 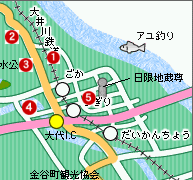 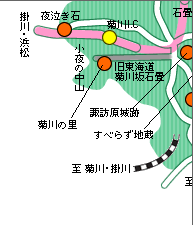 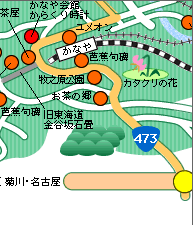 [志戸呂焼マップ 同町観光課マップより]
|
[志戸呂焼] 15世紀後半から始まる志戸呂焼の歴史は、15世紀後半は鉄釉、灰釉による天目茶碗の時代、16世紀後半は筒茶碗、徳利、香炉の時代、17世紀前半から明治にかけて黒釉の壺、瓶、椀、皿の時代と3つに大きく分けられます. ■窖窯(あながま)期 平安時代、応仁の乱で需要を失った陶工が各地に離散した所謂「瀬戸離散」がありました.その離散先のひとつが金谷であり、志戸呂窯はそのときに復興したもとのいわれ、大永年間(1521〜1528・室町後期)頃に葉茶壷を焼いたのが始まりと伝えられます.また、天正年間(1573〜1592) 初期、美濃国久尻の陶工加庄右衛門景忠が、五郎右衛門と改め作陶したとの説もありますが、最近の三ツ沢窯発掘調査では大永年間よりも更に古い15世紀の開窯との説が有力です. ■大窯(おおがま)期 志戸呂焼に再び窯の火が点るのは16世紀後半のことで、大井川をはさんで対岸の二ヶ所に瀬戸・美濃系の大窯が築かれました.家康は天正16年(1588)5月14日、志戸呂窯に朱印状(商売免許にあたる)を授け、伝馬朱印状、13人扶持などを与えて窯を優遇し、志戸呂焼の名は全国に知られた.その後、志戸呂焼の茶壺は将軍家の代々の献上品となり、掛川藩は窯元を手厚く保護した. ■登窯(のぼりがま)期 志戸呂焼がさらに盛んとなるのは17世紀に入ってからで、幕藩体制が確立されると駿府掛川城下を中心に志戸呂焼の需要が高まり、金谷に登窯が築かれ大量生産が行われた.享和元年(1801)には30数軒の窯元があった.天目茶碗、茶入、花生などの茶器から徳利、皿、瓶などの日用品まで幅広くつくられた. 近年の関東における発掘調査で、志戸呂焼の灯明皿や由右衛門徳利(よしえもんとっくり)が数多く出土しており、江戸の市場に広く流通していたことがわかる. 志戸呂焼は、大部分が褐色または黒釉を使った釉調で、古式豊かな風情を漂わせているのが特徴です.金谷地方一帯は昔から良質の陶土が産出し、室町以前より焼き物が盛んに行われていた(数多くの古窯が発見されている).またこの地で産出される陶土が、鉄分を多く含み、堅く焼ける特徴から、湿気を嫌う茶壺には最適な土と言われて、後に、遠州流茶道開祖の小堀遠州の目に留まり、彼の指導を受け、遠州7窯に数えられた.今でも主な製品は抹茶や煎茶の茶器が中心になっている.志戸呂焼は、かつてこの当たりが志戸呂郷と呼ばれており、そこで産出される陶土を使って焼かれる焼き物なので志戸呂焼と名付けられたようである. |