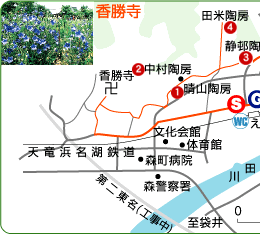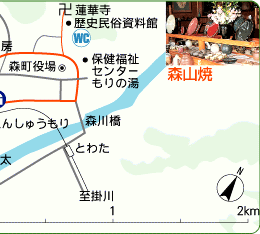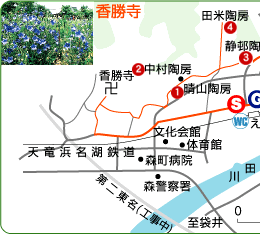 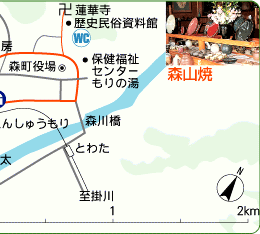
[森山焼マップ 同町観光課マップより]
|
[森山焼]
森山焼は、明治42年初代中村秀吉によって始まった焼物.遠州流茶道の開祖、小堀遠州ゆかりの遠州七窯の一つで、志戸呂焼の流れを汲み、名前は森町森山の地名からとっている.
初代中村秀吉は、瀬戸の陶工藤四郎の物語に感化され、森山の土が陶工に向くことを知り、志戸呂より鈴木静邨を招き、陶業を始めた.そしてその名を不動のもにしたのは、大正4年の天皇即位を祝い、花瓶と置物を献上したことをきっかけに製品づくりに取り組み、今日の地位を得ているという.
[森山の地]
天竜浜名湖鉄道にゆられ、遠州森駅を下車する.窯元散策なら一時間もあれば充分であるが、時間の許す限り作家の話を聞きたい. |
 晴山陶房(松井晴山):日本的な素朴さ、ぬくもりを民芸的に表現する 晴山陶房(松井晴山):日本的な素朴さ、ぬくもりを民芸的に表現する
 中村陶房(中村陶吉):素朴な味わいと豊かな芸術性を備えた焼き物を作り出す 中村陶房(中村陶吉):素朴な味わいと豊かな芸術性を備えた焼き物を作り出す
 静邨陶房(鈴木静邨):先代が生み出した至難の業と言われる赤の表現こだわり、赤焼を得意とする 静邨陶房(鈴木静邨):先代が生み出した至難の業と言われる赤の表現こだわり、赤焼を得意とする
 田米陶房(田米孝雄):新進気鋭、芸術性に富んだ作品で手作りのぬくもりを表す 田米陶房(田米孝雄):新進気鋭、芸術性に富んだ作品で手作りのぬくもりを表す |
|
私は2002年の3月に訪問した. 鈴木静邨赤へのこだわり並ではない.この表現は日本には無く、イタリアンレッド(お休みであったが作品は見る事ができた). 鈴木静邨赤へのこだわり並ではない.この表現は日本には無く、イタリアンレッド(お休みであったが作品は見る事ができた). 中村陶吉今は、夫婦と娘とで作陶.夫人が般若心経の経文を刻んでいる.彫文字の入った焼物も多い.どっしりとした作品が印象的.赤と黄には特徴があり、共に深く退色調で渋い.「ぐい呑みは、一合入らなければいけない」という持論があるので、いつも大き目のぐい呑みを私は求める.賢人、つまり濁った酒をぐいっと呑むため.ここでも一番大振りなのを求めたが、それでも小さい.つまり、聖人用であるから.作家の記した「ぐいのみ楽し」という新聞の切抜きを頂いた. 中村陶吉今は、夫婦と娘とで作陶.夫人が般若心経の経文を刻んでいる.彫文字の入った焼物も多い.どっしりとした作品が印象的.赤と黄には特徴があり、共に深く退色調で渋い.「ぐい呑みは、一合入らなければいけない」という持論があるので、いつも大き目のぐい呑みを私は求める.賢人、つまり濁った酒をぐいっと呑むため.ここでも一番大振りなのを求めたが、それでも小さい.つまり、聖人用であるから.作家の記した「ぐいのみ楽し」という新聞の切抜きを頂いた. |