| 形・こげ・ビードロと言われる三要素が魅力.信楽よりは焼きしめは穏やかに感じるが、火ぶくれに驚く. | |
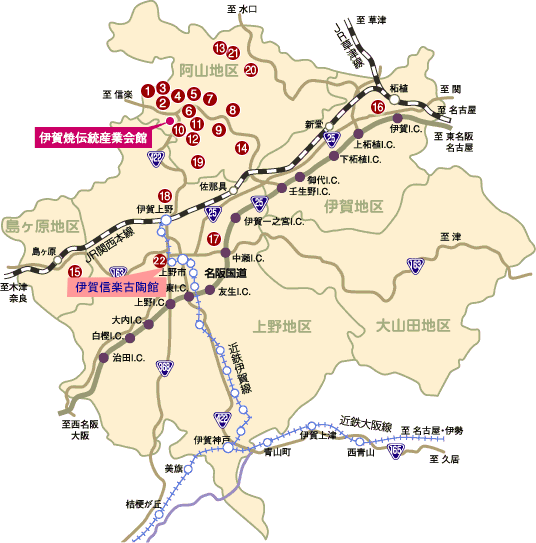 [伊賀信楽古陶館] 伊賀・信楽の地は、焼き物に適した良質の陶土に恵まれ、古くから焼き物の産地として知られてきました.二階に常設展示している古伊賀・古信楽は、郷土の愛陶家故奥知勇氏が、長年にわたって収集された、室町時代から江戸時代初期にかけての名品で、故人の遺志によりご遺族が上野市に寄贈されたものです.また、ご令兄がこの『伊賀・信楽古陶館』を設計、建築後寄贈、さらにご令弟から多数の陶芸図書の寄贈があり、伊賀・信楽陶芸研究に欠かせない資料館となっています。観覧無料となっている一階では、現代の伊賀焼陶芸作家の作品を展示販売しています. [伊賀焼伝統産業会館] 昭和57年11月に通産大臣から伝統工芸品に指定された伊賀焼を幅広く展示する資料館.伊賀焼きの振興と後継者の育成を図るため、伊賀焼の製造過程や古今の伊賀焼の名品の展示を行うほか、伊賀焼の体験教室や技術指導を行う実技研修室を備えています. |
[伊賀焼] 歴史は古く、奈良時代までさかのぼる. 平安時代末期から鎌倉時代の初めごろに本格的なやきものの産地として発展し、室町時代の終わりから桃山時代にかけて侘び茶が広まると、個性的な伊賀焼は茶の道具として注目されるようになった.主として伊賀國を治めた筒井定次や藤堂高虎が茶人であったことから、伊賀焼は茶の湯のセンスや心遣いを巧みに取り入れたのでした. 土の風合いと、炎による変化が生み出す自然な「景色」.整った形に手を加えることによって生まれる、より自由でおおらかで生き生きとした形…「破調の美」.伊賀焼は、日本人だけが見出し、敏感に受け止めることができるやきものの美しさを最も純粋に表しているのです. その後、伊賀焼は江戸時代中期に一時衰退しましたが、18世紀中ごろに京都や瀬戸から技術者を招き、伊賀の土を活かした日用雑器の生産が行われるようになり、現代の基礎が作られました.現在の伊賀焼は伊賀市(阿山地区)の丸柱を中心に造られています.伊賀の豊かな自然の中で、こつこつと堅実に作られ続けてきた伊賀焼には、茶陶から受け継がれた、使う人への心遣いと、良いものを創りつづけていきたいという伊賀の心意気が息づいている. [伊賀の地] 伊賀忍者と松尾芭蕉くらいしか知らないが、伊賀牛は美味しいという評判の方が気になっていた. 荒木又右衛門のあだ討ちと言う史実もあったかな?[焼物探訪:地図参照] JR関西本線、伊賀上野から丸柱、即ち阿山地区に行くのが普通の経路である.窯元はこちらに集中している.しかし、こちらは交通の便が悪い.やはり車が必要である. そこで、近鉄線で上野市に行き、駅直ぐ(1分)の 「伊賀信楽古陶館」を見学すべきであろう.理由は 「伝統産業会館」よりはずっと価値があるから.そして、こちら上野市が、本当の市街地、いわゆる伊賀である.城、芭蕉生誕の地、金谷(伊賀牛)もこちらである. [三田窯:谷本 光生] 大正5年生まれ.昭和20年より伊賀焼きに傾倒.元々は前衛洋画家.現代伊賀作陶の牽引者である.伊賀城下に三田焼即売所「土味」がある. 現在、ここは子息、谷本 洋氏の工房(洋工房:地図22)となっている. もう一人の子息、谷本 景氏は、JR伊賀上野駅近くに「三田窯」(地図18)を開いている.こちらの窯は、線路沿いから窯の煙突が目える.巨匠の子は、さすがにどっしりとした落着きのある器を作るものだと感心した.私は三田焼(光生、景氏、洋)は気に入っている.伝統が全て入っている印象. [常山窯:恒岡 光興:地図14] 作者の窯へ行く時間が無く、「伊賀伝統産業会館」にて拝見した.近年の作家では一番ビードロが出ていると感じた.形もすっきりしているので、親しみやすい.重厚な作品は未だ見ていない.角皿には、伊賀牛をのせてみたいが、購入したのは抹茶の筒碗. ⇒[伊賀所有作品へ] |
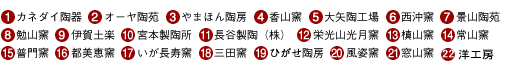 |
|