「一楽 二萩 三唐津」「萩の七化け」といわれる萩.柔らかさと色合いが魅力
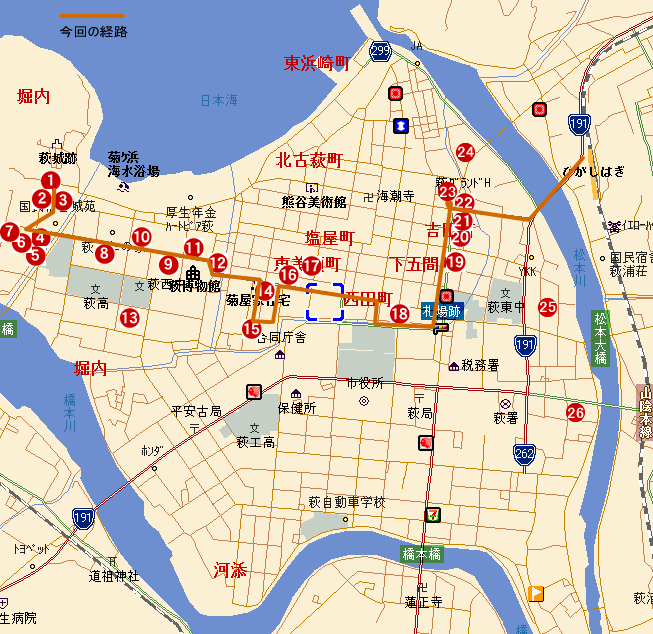
[萩焼窯元(萩駅西部地域マップ]
|
[萩焼]
萩焼の起源は400年前にさかのぼる。豊臣秀吉の文禄・慶長の役(1592-1598年)で、朝鮮の陶工・李勺光(り しゃくこう)と李敬(り けい)の兄弟を伴って帰国しました。後に、毛利輝元が安芸の国広島で2人を預かりました。1600年の関ヶ原の戦いで敗れた毛利輝元は、領地を中国8か国120万石(現、中国5県)から周防・防長の2か国36万石(現、山口県)に減封され、居城を萩の地に移すことになりました。これに併せて、2人の兄弟も萩の地に住まわせました。兄・李勺光は、萩松本村中の倉(現、萩市椿東中の倉)で薪の使用を許され松本御用窯として開窯したのが萩焼の始まりと言われています。李勺光の死後、弟・李敬が後を継ぎ「坂高麗左衛門」(さか こうらいざえもん)に任ぜられました。慶安時代(1648年)に入ると、多くの諸窯が召し抱えられ古萩の全盛時代を形成します。しかし、寛文(1661年)以降はそれまでの高麗茶碗や織部、御手本風以外に楽焼の作風が加わって多様化し、萩焼開窯以来の李朝の作風は遠のき、萩焼独特のものが焼成されました。
萩焼は大きく分けると、坂高麗左衛門の坂窯、三輪休雪の三輪窯、林伴六らの3流派があります。また、明暦3年(1657年)には、深川(現、長門市)に深川御用窯が開設されました。焼き上がりが軽く、素朴で、わび茶によく似合とい。柔らかさの点で京都楽焼には及び難いが、がっしりと焼きが固く、絵付けの華やかな唐津茶碗よりは茶陶としては優れていると言われています。反面で、水洗い、持ち運びなどに際して壊れやすいという難点もある.胎土(原土)に浸透性があり、しかも低火度焼成で焼き締まりが少ないため、使用するにつれて比較的短期間に表面釉薬の貫入を通して茶がしみ込み、器体の内外ともに色合いが変化する。一つの茶碗を長く使っていくと、その色、つやが微妙に変化して風情を醸し出す。
[萩の地]
萩は遠い.栃木北端からは彼方である.東京から夜行で下関に行き、早朝、萩に向かうが二度訪れることがあるだろうか?日本海へと注ぐ橋本川と松本川ににはさまれた町である.毛利家の納める地であった.関ヶ原の役に敗れた毛利輝元が中国地方8カ国112万石を、周防・長門2ヵ国36万石に減封された.以後、幕末の文久3年(1863)藩庁を山口に移鎮するまでの約260年間、13代にわたって毛利氏のもとで栄え、明治維新発祥の地となる。吉田松陰、高杉晋作、桂小五郎、伊藤博文等時代を動かした人を生んだ.町並みは丈が低く、武家塀が残り、みかんがたわわに実る風情は今も変わらない.閑静と緊張の癒合する町である.
[萩陶芸家]
この地には百数十名の陶芸家が在住.歴史には、3流派の流れを汲む.
|
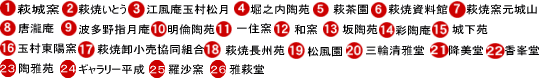 |
[城下近傍]
先ず車で萩城跡迄行き、徒歩にて東萩駅へ戻った.それ程長い距離ではないが、往復徒歩の時間がなかったので.先ず、萩焼資料館へ.城下周辺にも窯元・焼物店は多い.「萩城窯陶焔工房」にてぐい呑みと出あった.このぐ呑み、一合には足りないのだがやはり暖かい.
[堀内]
ここは通り面して窯元があり、順番にのぞける. |
|



