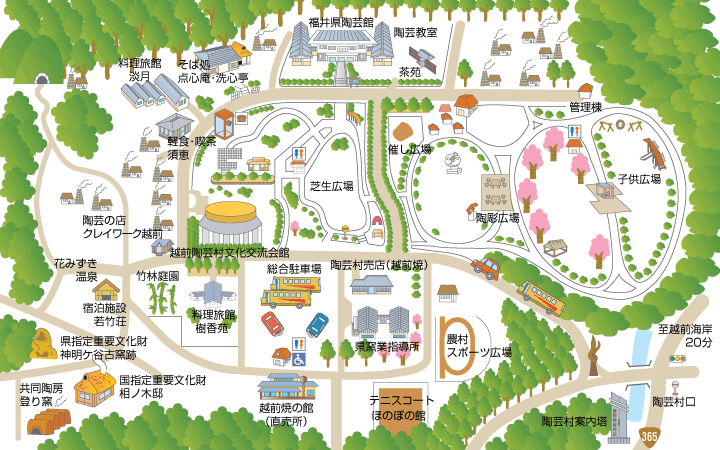 [宮崎陶芸村内マップ] |
[越前焼] 瀬戸・常滑・信楽・丹波・備前とともに日本六古窯の一つ.今から850年前の平安時代末期に宮崎村小曽原の丘陸に最初の窯が築かれたという.東海地方からこの地までやってきた陶工の集団が初期の越前焼の生産を担ったと考えられている.その後、宮崎村・織田町の丘陵各地に窯が築かれ、室町時代後期には巨大な窯(長さ25メートル以上)を、大釜屋の呼ばれる平等村集落(現:織田町平等)から少し離れた丘陵の一画に集めて、大生産基地を作り大いに栄えた.江戸時代中期は、窯は平等村の集落近くへ移ったが、燃料の薪や瓶土(べと)と呼ぶ粘土が不足し生産量は縮小した.明治になり信楽や瀬戸・九谷などから陶工を招いて食器や花瓶作りなどを始めた.また、徒弟養成所を作って後継者の育成にも努めている.伝統的工芸品. [越前の地] 福井県の陶芸家は、30数人を数えるが、その2/3は宮崎陶芸村とその周辺に居を構える.鯖江市、武生市から越前海岸に向かう途中の宮崎村、織田町を中心に窯がある.宮崎村には越前陶芸村があり、窯元も村内と近辺に集中している.左地図は村内窯元マップで20を数え、陶芸品の売店も3-4件ある. |
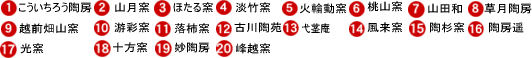 |
[宮崎陶芸村] 村内窯元マップは左図を参照されたい.文化交流会館で展示品を見てから窯元を訪れるのが、一般的.①こういちろう窯は、焼物を始めたばかりであったが、2004年は会えず休窯状態.2点の作品を所有.ぜひ作品をご覧下さい. |
| [越前所有作品へ] | |
| [脇谷窯:西浦 武(敬称略)] 令室の中沢洋子と共に作陶を行っている.窯は福井県織田町脇谷口にある.中々ユニークな方で、作品にも遊び心が表れている.越前焼の中では気になる存在.最近の作品は色合が豊かになっている.窯元2回、個展3回ほどお世話になったが、いかんせん駆け足. [おさごえ窯:ふじの まさよ(敬称略)] 福井福町在住の女流作家.連絡無くぶらりと出かけたので二度ともお休みであった.「火もらいがめ」等の独特の作品がある. |