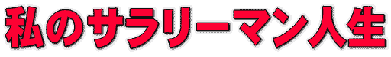
人並みに大企業を目指し、昭和40年に石川島播磨重工業㈱に入社した。
大学で土木工学を学んだので入社後は橋梁の設計をするものと考えていたが、配属
されたのは火力発電、都市ガス、石油化学等のプラント設備構造物の設計部門だっ
た。
最初に担当したのは、当時世界最大容量の 45,000kl のLPGタンク基礎の設計だった。
埋立地の軟弱地盤に大型構造物を安全に支持する基礎の設計で、技術的に難しかっ
たが地盤改良を含む現地工事も監督し、完成の喜びと達成感で充実した仕事のおもし
ろさを知った。
昭和48年に石油、液化天然ガス等を貯蔵する貯蔵タンクの耐震設計の研究開発を担
当する。
旧国鉄技術研究所出身の車両振動の大家である国枝正春氏や波浪中の船体振動の
越智義夫氏及び東京大学生産研の柴田碧教授の良き指導を得て、耐震設計法の確
立を果たすことができた。
研究成果は多くの論文として発表する事ができたが、その中でも地震によってタンク内
容液がどのように振動し、タンク本体の鋼製円筒シェルの振動と連成してタンク本体は
地震時にどのような挙動をし、どのような応力が発生するかを解析し、その固有周期を
求める実用的な簡易式を提案した論文は高圧力技術協会の科学技術賞を受賞した。
昭和49年から退社するまで通産省から委託された高圧ガス保安協会のプラント耐震
設計関連委員会委員を委嘱され、高圧ガスプラント耐震設計の法律や設計基準作り
を行った。
また、耐震設計法規の説明のため多くの地方自治体や民間の技術研修の講師として
多くの講義を行った。
特に、平成2年から通産省の職員及び全国都道府県の高圧ガス担当官研修のため、
耐震設計の講義を10年間続けて行ってきた。
私のサラリーマン人生は、研究開発や社外活動によって一種の会社の「顔」、「タレン
ト」としての役割が多く、論文や国の委員であることによって社内よりも社外で名前が
知られ、会社のために頑張ったはずが、社内では必ずしも正当な評価を受けていない
ような気がしていた。
平成12年3月31日退職。
まだ定年には2年あるが、体力・気力が充実しているうちに第二の人生に踏み出したい
と考え、社内の転進援助制度という早期退職優遇制度に基づいて退職した。
長年勤めた会社を辞める寂しさもあったが、それ以上に第二の人生への期待と解放感
の方が大きかった。
